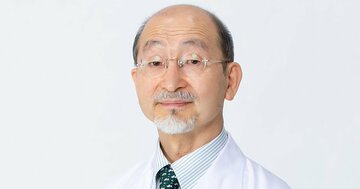イヤホンよりはヘッドホンを!せめて耳に優しいイヤホンを選ぼう
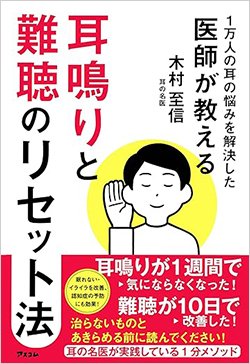 『1万人の耳の悩みを解決した医師が教える 耳鳴りと難聴のリセット法』(木村至信、アスコム)
『1万人の耳の悩みを解決した医師が教える 耳鳴りと難聴のリセット法』(木村至信、アスコム)
とはいえ、忙しいビジネスパーソンがいきなり自分のビジネススタイルや生活習慣を変えるのはそうそうできることではありません。そんな中で難聴や耳鳴りを引き起こすリスクを減らしたり、すでに発症してしまった人が進行を遅らせたりする方法はあるのでしょうか。
木村先生は多くのビジネスパーソンが日常的に使用するようになったイヤホンに警鐘を鳴らします。
「耳の中に入れるイヤホンは、ヘッドホンに比べて鼓膜に近いところで音が鳴るため、耳への負荷が大きくなります。特にワイヤレスイヤホンやゲーミングイヤホンは耳のかなり奥まで入れる構造になっているだけでなく耳を密封して空気を通さないため、耳への負荷が大きくなります。イヤホンの着けっぱなしが原因で外耳炎になる可能性もあるので注意が必要です」
リモート会議などでは、イヤホンではなくヘッドホンを使ったほうが耳への負荷を減らすことができます。もしイヤホンしか使えないのであれば、骨伝導タイプや音量を下げて使えるノイズキャンセリングイヤホンを選んだほうがいいそう。
そしてイヤホン、ヘッドホンともに両耳につけるのではなく、時間を決めて片耳ずつ交互に使い、耳を休める時間を作ることが大切。仕事中にイヤホンを使う時間が長いなら、通勤時には使用しないなどの配慮も必要です。
「日常的にヘッドセットやインカムを使う人も、一般の人に比べると難聴や耳鳴りになるリスクがかなり高くなります。ヘッドセットやインカムの使用をやめることはできないと思いますので、『日頃から1時間おきにつける』『耳を入れ替える』といった工夫をすることで耳への負荷を減らすことができます。ヘッドホンを使っている人も、リモート会議なら片耳ずつ使ってみてください」
音が聞こえていることを脳に伝える細胞は、一度死んだら再生しない
多くの人が悩む難聴や耳鳴り。その原因や症状は一人ひとり違うそうです。私は「低音障害型感音難聴」と診断されましたが、実はまだ難聴や耳鳴りには医学的にわからないことも多いと言います。
「病院で低音障害型感音難聴、あるいは突発性難聴と言われる人は多いですが、正直、これらは“ゴミ箱診断”(注:確定診断ができないあいまいな診断)です。突発性難聴は『突然聞こえづらくなった状態』だし、低音障害型は『低音が聞こえづらくなっている状態』。言い換えれば何でも当てはまってしまいます。たとえば低音障害型感音難聴と診断されても、シンプルにそれだけを患っている方は少なく、耳管が狭窄(きょうさく)気味だったり、鼻炎があったりと、他のさまざまな要因が絡んでいるケースが大半です。だからこそ、病院でしっかり検査をすることが大切です」
人間の細胞は再生を繰り返しているのはみなさん承知の通り。例えば肌の細胞は1カ月~数カ月周期で入れ替わり、再生が遅い骨の細胞でも数年で全て入れ替わっています。しかし音が聞こえていることを脳に伝える有毛細胞は再生が行われず、一度死んでしまうと戻ることがないそうです。
だからこそ自分の耳に少しでも違和感を覚えたら、すぐに病院に行って適切な処置を受けることが大切とのことでした。