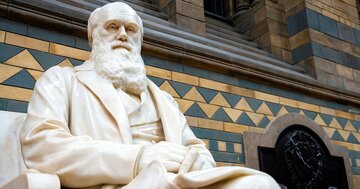ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、読者の「頭の中」に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じような記憶が残る画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊される。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
たった一つの大きな誤解
親が生きているあいだに獲得した形質が子に伝わることを、獲得形質の遺伝という。
この獲得形質の遺伝に関しては、一つの誤解が広まっている。
たった一つだけれど、それはとても大きな誤解だ。そのせいで、さまざまな混乱が生じている。
しかし、その誤解が解ければ、獲得形質の遺伝はかんたんに理解することができるのだ。
ラマルクの主張
かつてジャン=バティスト・ラマルク(1744~1829)は、獲得形質の遺伝を主張した。しかし、その後の研究でラマルクの主張は間違いであるとされた。
それ以来、獲得形質の遺伝は存在しないものとされてきた。ところが近年になって、獲得形質の遺伝と考えられる現象がいくつも見つかってきたのである。
たとえば、セイヨウタンポポは栄養状態が変化すると、DNAの状態が変化することが知られている。塩基配列は変わらないのだが、DNAの一部にメチル化(メチル基が付加されること)が起きるのである。
そして、このメチル化は子に遺伝する。
これは、親が生きているあいだに獲得した形質が子に伝わったのだから、獲得形質の遺伝であると考えられた。
飽食する人の子孫の寿命は短い?
また、スウェーデンの北部で1905年に生まれた99人について、その両親や祖父母と、農作物の生産量との関係を調べた研究がある。
それによると、少年時代に飽食を経験した男性の息子や孫息子は、寿命が短かったのである。これは、飽食によって獲得された何らかの形質が子や孫に伝えられたと考えられるので、獲得形質の遺伝の例とされる。
やはり獲得形質の遺伝は存在するのだろうか。じつはラマルクは正しかったのだろうか。その答えはイエスでもあり、ノーでもある。
『岩波生物学辞典・第5版』で「獲得形質」を引いてみると、丁寧な説明がなされている。そのなかの一部を要約すると、「一般に獲得形質の遺伝といえば、親が生きているあいだに生じた体細胞の変化が子に遺伝することをいう」と書いてある。
体細胞の変化が遺伝する
つまり、「獲得形質の遺伝」というのは、体細胞の変化が子に伝わることなのだ。
これを「狭義の獲得形質の遺伝」と呼ぶことにしよう。
私たちの体を作っている細胞は、大きく2種類に分けられる。生殖細胞と体細胞だ。
生殖細胞とは精細胞や卵細胞のことで、子に伝わる可能性のある細胞だ。
もう一方の体細胞は、生殖細胞以外のすべての細胞のことで、手足や内臓などの体を構成している細胞だ。
そして、体細胞は子に伝わらない。私の指から子が生まれるなんてことは、絶対にないのである。
キリンの首はなぜ長い?
ところが、社会で広く使われている「獲得形質の遺伝」というのは、たんに「親が生きているあいだに生じた変化が子に遺伝すること」を意味しているようである。
変化は体のどこに起きてもよいので、体細胞の変化だけでなく、生殖細胞の変化も含まれる。
つまり、生殖細胞や体細胞の変化が子に伝わることで、こちらを「広義の獲得形質の遺伝」と呼ぶことにしよう。
さて、ラマルクの主張した獲得形質の遺伝は、狭義の獲得形質の遺伝である。
ラマルクは、キリンが高いところにある木の葉を食べようと首を伸ばし続けた結果、首が長くなったと主張した。
その場合、変化したのは首の細胞、つまり体細胞である。
体細胞が獲得した形質は遺伝しないので、ラマルクの主張は間違いだ。一方、栄養状態の変化によって、セイヨウタンポポのDNAにメチル化が起きる場合は、広義の獲得形質の遺伝である。
メチル化は体細胞だけでなく生殖細胞にも起きるからだ。生殖細胞に起きた変化なら、子に伝わることもあるだろう。
伝わる変化、伝わらない変化
ただし植物の場合は、体細胞が生殖細胞に変化したりするので、話が少しややこしくなる。
とはいえ、基本は同じである。要するに、子に伝わる細胞に起きた変化は子に伝わることがあるけれど、子に伝わらない細胞に起きた変化は子に伝わらないのだ。それだけのことである。
「狭義の獲得形質の遺伝」と「広義の獲得形質の遺伝」を区別しないで使えば、話が混乱するのは当たり前である。
それらをきちんと区別していれば「獲得形質の遺伝」に関して混乱することはないだろう。
(本原稿は、『『種の起源』を読んだふりができる本』の著者による書き下ろしです)
1961年、東京都生まれ。東京大学教養学部基礎科学科卒業。民間企業を経て大学に戻り、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了。博士(理学)。専門は分子古生物学。武蔵野美術大学教授。『化石の分子生物学 生命進化の謎を解く』(講談社現代新書)で、第29回講談社科学出版賞を受賞。著書に、『爆発的進化論』(新潮新書)、『絶滅の人類史―なぜ「私たち」が生き延びたのか』(NHK出版新書)、『若い読者に贈る美しい生物学講義』(ダイヤモンド社)などがある。