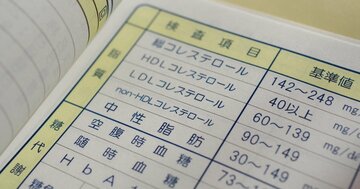血液検査で「すい臓がん」は見つかるの?→医師の答えが想像以上に重かった
人生100年時代は、健康こそ最大の資産です。しかし40歳を越えると、がん、糖尿病、腎臓病といった病気を避けては通れません。国立がん研究センターによれば、40~49歳のがん患者数は、30~39歳と比べると3倍以上です(2020年)。もちろん50代、60代と年齢を重ねるにつれ、がん患者数はどんどん増えていきます。
本連載は、毎日の食事から、大病を患ったあとのリハビリまで、病気の「予防」「早期発見」「再発予防」を学ぶものです。著者は、産業医×内科医の森勇磨氏。初の単著『40歳からの予防医学 医者が教える「病気にならない知識と習慣74」』を出版し、感染症医・神戸大学教授の岩田健太郎氏が「安心して読める健康の教科書」と推薦文を寄せています。出版を記念し、寄稿記事を特別に公開します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「すい臓がん」について知っておこう
「沈黙の臓器」。これは、すい臓という臓器の別名です。すい臓がんは本当に症状が出にくいため、こう呼ばれています。そして、がんの中でも最も生存率が低いものをご存じでしょうか?
それが、まさにすい臓がんなのです。現場の医師にとっても早期発見が非常に難しく、悲しい思いをすることが多いがんです。
今回は、そんなすい臓がんについて、どんな症状があるのか、現代の医学でわかっていること、そして日常でできる予防策について、しっかりお話ししていきます。
そもそも「すい臓」とは?
まず、すい臓という臓器について、あまりなじみのない方も多いと思いますので、簡単に解説しておきます。そもそもすい臓がどこにあるかご存じでしょうか? すい臓は胃の裏あたり、体のかなり奥の方にあります。形はオタマジャクシのような、ちょっとかわいい形をしています。
多くの臓器は腹膜という膜に覆われていますが、すい臓は腹膜の外、背中側に位置していて、「後腹膜臓器」と呼ばれることもあります。この特徴は、後ほど紹介するすい臓がんの症状とも関係してきますので、覚えておいてくださいね。
すい臓の主な役割は大きく2つあります。1つ目は、食べ物を消化する酵素を作ることです。糖質を分解する「アミラーゼ」、中性脂肪を分解する「リパーゼ」、たんぱく質を分解する「トリプシン」などの消化酵素を作って、十二指腸へと送り出しています。つまり、胃の下で消化を支える“縁の下の力持ち”なんです。
2つ目の役割は、血糖値をコントロールするホルモン「インスリン」を作ることです。インスリンが不足すると、血糖値がうまく調整できず、さまざまな悪影響が出ます。たとえば「1型糖尿病」は、すい臓の中のβ細胞がうまく働かなくなることで起こります。普段あまり気にかけないすい臓ですが、実はとても重要な臓器なのです。
血液検査でわかるのか?
では、そんなすい臓にがんができた場合、どうやって診断され、治療されるのでしょうか。よく「血液検査ですい臓がんってわかるの?」と聞かれますが、結論から言うと、血液検査だけでは診断できません。
確かに「腫瘍マーカー」というタンパク質を測ることはできますが、それだけでは診断はつかないのです。マーカーが上がらない場合もあれば、がんでなくても上がることもあるため、あくまで参考程度なのです。
すい臓がんの診断では、主に画像検査が使われます。たとえば超音波(エコー)検査や、造影剤を使ったCT検査などです。また、すい臓の中には「膵管」という管が通っているのですが、がんによってこの管が狭くなり拡張すると、それががんのサインになることもあります。
さらに、胃カメラを使って十二指腸までカメラを進め、そこから細い管を膵管に通して細胞を採取し、良性か悪性かを診断するという方法もあります。
治療としては、早期発見できれば手術が可能です。ただし、すい臓は十二指腸などと複雑に関係していて、すい臓だけを単純に取り出すことはできません。
たとえば膵頭部にがんができた場合は「膵頭十二指腸切除術(PD手術)」という大きな手術になります。これは医師にとっても患者にとっても非常に負担が大きい手術となります。
(本原稿は、森勇磨著『40歳からの予防医学 医者が教える「病気にならない知識と習慣74」』を一部抜粋・加筆したものです)