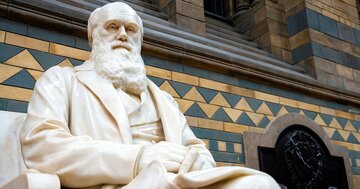ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
カンブリア爆発の原因
ダーウィンの時代における化石記録の大きな謎として、最古の生物が現生生物と同じくらい複雑な構造をしていたことが挙げられる。たとえば、カンブリア紀の三葉虫は、現生の昆虫に匹敵するような複雑な複眼を持っていた。このような三葉虫が進化するには長い時間がかかるはずなので、三葉虫より古い時代にもたくさんの生物が生きていたはずである。それなのに、どうして化石が見つからないのだろうか。
ダーウィンはカンブリア紀以前の化石が見つからないことについて、いくつかの仮説を提示している。たとえば、化石がよく調べられているヨーロッパや北アメリカは、当時は堆積が起こらないような地域だったとか、すさまじい圧力で熱せられて岩石が変成したため、化石が失われたなどの仮説である。
もちろん、そういうこともあったかもしれないけれど、そのせいでカンブリア紀以前の化石がすべて失われたと結論するのは無理があるだろう(ダーウィンもそう感じていた)。
しかし、じつはダーウィンは、「最古の生物が現生生物と同じくらい複雑な構造をしている」という難点に対する答えに辿り着いていた。たとえば、飛行能力のように非常に有益な形質を持つ生物がいったん出現すれば、瞬く間に分布を広げていくだろう、とダーウィンは述べている。これが、この難点に対する答えになっていたのである。
カンブリア紀には、さまざまな種類の複雑な動物が、一気に出現したことが知られている。そのおもな理由としては、動物同士における捕食などの相互作用が始まったことが挙げられる。
肉食動物は、獲物を捕まえるために武器を進化させる。すると、獲物の方も、防御手段を進化させる。すると、肉食動物は、獲物を見つけたり捕まえたりできるように視覚を進化させる。すると、獲物の方も、うまく逃げられるように視覚を進化させる。
このような生物同士の相互作用によって、有益な形質の進化がエスカレートして、多くの複雑な動物が一気に出現した。これがカンブリア爆発と呼ばれる現象で、この時代以降は、化石がたくさん見つかるようになるのである。
さらに、カンブリア爆発を起こした原因としては、海水中の酸素濃度の上昇も挙げられる。ただし、これは、カンブリア爆発より数千万年前に起きていた可能性が高いので、カンブリア爆発の直接の引き金になったのではなく、必要条件として前もって準備されていたようなイメージかもしれない。