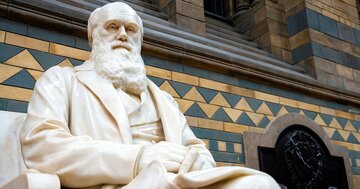ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、読者の「頭の中」に、実際に『種の起源』を読んだ後と同じような記憶が残る画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊される。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
名著『種の起源』を理解するために
『種の起源』は比較的大きな本で、原書は本文だけで500頁近くある。その中ではいろいろな主張が絡まり合っているし、同じことが違う言葉で表現されていることもあるし、同じものについての説明が異なる章に少しずつ散らばっていたりもする。
そのため、前から順番に読んでいくだけでは、全体像を把握することが難しい。
そこで、まず『種の起源』の大ざっぱな枠組みを説明しておくことにする。いわゆるネタバレになってしまうけれど、『種の起源』の大枠を理解したうえで読み進んでいけば、格段に理解しやすくなるはずだ。
進化の仕組みについて
さて、『種の起源』を理解するためにもっとも重要なことは、そこで提唱されている進化の仕組みを理解することである。『種の起源』で提唱されている進化の仕組みは4つだ。「自然淘汰」と「用不用」と「生活条件の直接作用」と「習性」である。
自然淘汰について
自然淘汰は、生存や繁殖に有利な個体が増えていくメカニズムである。たとえば、首の短いキリンと首の長いキリンがいた場合、首の長いキリンの方が高い木の葉をたくさん食べられる。そこで、首の長いキリンの方がより多く生き残って、より多く子を作って増えていく。その結果、キリンの首は長くなっていく、そんなイメージだ。
ダーウィンは自然淘汰の中で、生存ではなく繁殖に有利なメカニズムを「性淘汰」と呼んでいる。たとえば、クジャクのオスの鮮やかな飾り羽は、肉食獣に見つかりやすいし、逃げる時には邪魔になるので、生存のためには有害である。
しかし、メスに対するアピールとしては有益で、飾り羽が鮮やかな方が、子をより多く残すことができる。その結果、飾り羽は進化したのだと考えられ、こういうメカニズムを性淘汰と呼ぶのである。ダーウィンは『種の起源』の中で、性淘汰を自然淘汰の一部だと言ったり、性淘汰を自然淘汰とは別のものとして区別したりするのでわかりにくい。
ただし、厳密に自然淘汰と性淘汰を区別することはできないので、性淘汰は自然淘汰の一部と考えた方がよいだろう(現在では「自然淘汰」の中で、生存に有利なものを「環境淘汰」、繁殖に有利なものを「性淘汰」と呼ぶこともある)。