ダーウィンの『種の起源』は「地動説」と並び人類に知的革命を起こした名著である。しかし、かなり読みにくいため、読み通せる人は数少ない。短時間で読めて、現在からみて正しい・正しくないがわかり、最新の進化学の知見も楽しく解説しながら、『種の起源』が理解できるようになる画期的な本『『種の起源』を読んだふりができる本』が発刊された。
長谷川眞理子氏(人類学者)「ダーウィンの慧眼も限界もよくわかる、出色の『種の起源』解説本。これさえ読めば、100年以上も前の古典自体を読む必要はないかも」、吉川浩満氏(『理不尽な進化』著者)「読んだふりができるだけではありません。実物に挑戦しないではいられなくなります。真面目な読者も必読の驚異の一冊」、中江有里氏(俳優)「不真面目なタイトルに油断してはいけません。『種の起源』をかみ砕いてくれる、めちゃ優秀な家庭教師みたいな本です」と各氏から絶賛されたその内容の一部を紹介します。
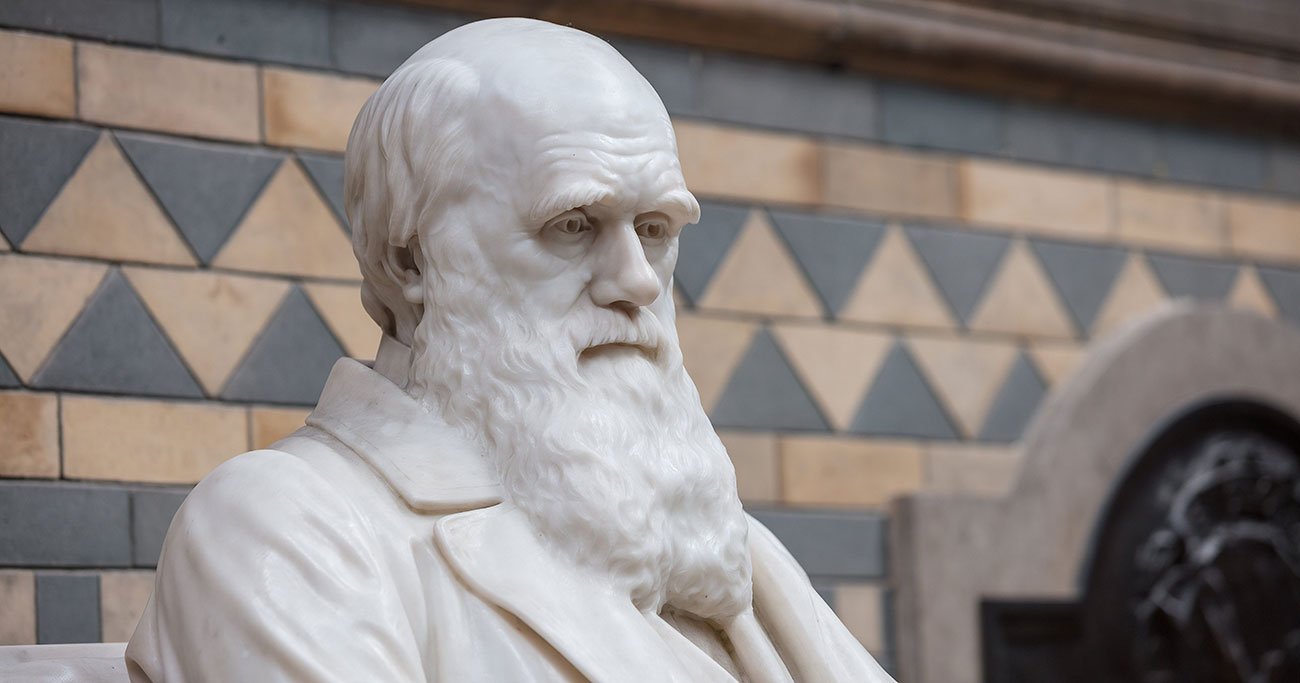 画像はイメージです Photo: Adobe Stock
画像はイメージです Photo: Adobe Stock
ダーウィンと自然淘汰
この世にダーウィンの進化論ほど誤解されているものは少ないだろう。ダーウィンは自然淘汰を発見したとか、ラマルクが主張した獲得形質の遺伝を否定して自然淘汰だけを進化の仕組みと考えたとか、そんな誤った見方がけっこう広まっているのである。
ダーウィンといえば自然淘汰が有名だが、じつは自然淘汰を発見したのはダーウィンではない。というか、自然淘汰は大昔から知られている考え方だ。たとえば、古代ギリシアのアリストテレス(紀元前384~紀元前322)の著作にも、すでに自然淘汰の仕組みが書かれている。
また、ダーウィンの進化論に反対した人物でもっとも有名なのは、おそらくサミュエル・ウィルバーフォース(1805~1873)だろう。イギリス国教会のオックスフォード主教であったウィルバーフォースは、1860年にオックスフォードで開かれた英国科学振興協会の会合で、ダーウィンの番犬といわれたトマス・ヘンリー・ハクスリー(1825~1895)と論争を行ったことで、よく知られている。
進化と自然淘汰
もちろんウィルバーフォースは進化論に反対の立場であったが、このウィルバーフォースでさえ自然淘汰は認めていた。そもそもウィルバーフォースは、ダーウィンの『種の起源』が出版される前から自然淘汰の仕組みを知っていたし、しかも自然淘汰が実際に働いているとも考えていたのである。
ただし、アリストテレスもウィルバーフォースも、自然淘汰によって進化が起きるとは考えていなかった。たとえば、ウィルバーフォースは、自然淘汰のことを、生物を進化させない仕組みと考えていたのである。
神がデザインした生物は本来完璧である。とはいえ、ときどき平均から外れた個体が生まれることがある。たとえば、体重が軽過ぎたり重過ぎたりする個体が生まれることがあるわけだ。そういう個体は平均的な個体より生存力が劣ることが多いので、自然淘汰によって除かれてしまう。そうして生物のデザインは変わることなく保たれていく、というのである。



