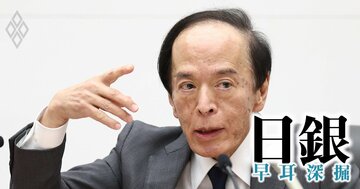9月19日の金融政策決定会合後、記者会見する日本銀行の植田和男総裁 Photo:JIJI
9月19日の金融政策決定会合後、記者会見する日本銀行の植田和男総裁 Photo:JIJI
日銀、5会合連続政策金利据え置き
説得力欠ける「トランプ関税の不確実性」
日本銀行は9月15、16日の金融政策決定会合で、ETF(上場投資信託証券)の売却開始を決める一方で、政策金利の引き上げは5会合連続で見送った。
日銀は2010年からETFの購入を始めたが、中央銀行が株式市場に介入するという異例の政策に対しては、IMFやOECDなどの国際機関から、資産価格のゆがみや出口戦略の難しさへの懸念が示されてきた。
そうした状況からの脱却が始まったことは、適切な判断だと考えられる。
政策金利の引き上げ見送りについて、日銀はその判断理由の一つとして、「各国の通商政策等の今後の展開やその影響を受けた海外の経済・物価動向を巡る不確実性は高い状況が続いている」と説明している。
植田和男総裁は決定会合後の会見で、「アメリカの関税政策の影響などが一段と出てくる可能性がある」「不確実性がある中、もう少しデータなり情報なりを見たい」などと説明した。
このように、アメリカの関税による企業業績などへの影響を点検する必要があると判断したとみられる。
しかし、日米の関税交渉は7月に決着し、自動車関税や相互関税の税率引き下げが合意されている。これを受けて株価は顕著に上昇した。関税そのものによる直接的な不確実性は、少なくとも短期的には後退したとみるべきだろう。
ただし、関税交渉は合意したが、その代償として、日本は巨額の対米投資義務を約束し、日本経済にとって非常に重い負担となる可能性があるので問題が解決したわけではない。
しかし、この問題は金融政策によって対処するものではなく、財政措置や産業政策で対応すべき課題だろう。
金融政策の適否は、現在の金利水準が経済活動に対して中立的か否かという観点から判断されるべきだ。