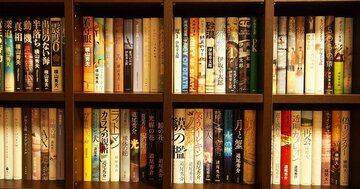もし光源氏がドラッカーを読んでいたら――。
想像するだけで少し愉快で、でもなぜか妙に気になる。
今年、没後20年を迎えるピーター・F・ドラッカーのマネジメント論は、リーダーが抱える悩みを今も鮮やかに解きほぐしてくれます。
「難しそうだから避けてきた」という人にこそ届いてほしいストーリー仕立てで学べる新しいドラッカー入門、『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』がついに刊行です。
本記事では、著者の吉田麻子氏にドラッカーの魅力を伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
現代のリーダーは負担が大きすぎる
――現代のリーダーはさまざまな面から負担が大きいと思います。リーダー自身が燃え尽きないために、自分をどうマネジメントすべきだと思いますか?
吉田麻子(以下、吉田):現代のリーダーは、成果を求められる一方で、メンバーのモチベーションを支え、組織文化をつくり……と、さまざまな面から大きな負担を背負っています。
ライフとワークのバランスが崩れたり、長年のハードワークがたたって、リーダー自身が燃え尽きてしまうこともあります。
しかし燃え尽きの原因は、過重労働だけではありません。実は、挑戦の不足もまた大きなリスクです。
燃え尽きを避けるためには?
吉田:ドラッカーの『経営者の条件』ではこう述べられています。
「熱意に燃え、誇るべき成果をあげている人とは、その能力が挑戦を受け活用されている人である。これに対し、強い不満をもつ人はみな、『能力が生かされていない』という。仕事の大きさが、挑戦を受け能力を試すにはあまりに小さすぎるとき、若い知識労働者は組織を去るか、さもなければ急速に不機嫌で非生産的で未熟な中年となってしまう」
つまり、今の仕事が刺激的でなくなった場合も、燃え尽きの可能性があるというのです。
また『明日を支配するもの』ではこう語られています。
「知識労働者は何歳になっても終わることがない。とはいえ、30歳のときには心躍る仕事だったものも、50歳ともなれば退屈する。だが、あと20年とはいかないまでも、10年、15年は働きたい。したがって、第二の人生を設計することが必要となる」
燃え尽きを避けるためには「第二の人生」をどう設計するかという視点が不可欠なのです。