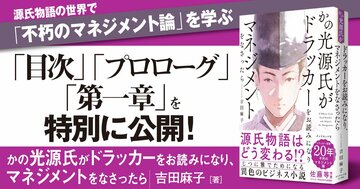今年はマネジメントの父、ピーター・F・ドラッカー没後20年。そのマネジメント論は現代でも深く息づいています。
「マネジメントの基礎を身につけたい」
「リーダーとして、どうメンバーに接したらいいのかわからない」
「管理職として仕事をしてきたけど、うまくいっていない気がする」
「ドラッカーは難しそうだから、今まで触れてこなかった」
そのような悩みを解決するヒントが詰まった書籍『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』が発売されます。本書は、これまでドラッカーを知らなかった人でも物語の中でその本質を学べる1冊です。
本記事では、著者の吉田麻子氏がドラッカーから学べることを解説します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
仕事をするか、会議に出るか
「人は、仕事をするか、会議に出るかである。同時に両方を行うことはできない」
思わずはっとさせられる言葉ですが、こちらはドラッカーの『経営者の条件』の『第二章 汝の時間を知れ』で書かれている文章です。
ドラッカーは『経営者の条件』で成果をあげる人物になるための5つの習慣的能力について記述しています。
◻︎汝の時間を知れ
◻︎どのような貢献ができるか
◻︎人の強みを生かす
◻︎最も重要なことに集中する
◻︎成果のあがる意思決定をする
の5つです。
『二章 汝の時間を知れ』では、成果をあげる時間の使い方をするためにはまず自らが何に時間を使っているかを記録してみたうえで、適切な活動に時間を割けるように不必要な活動を減らすなどして時間を整理し、生まれた時間をまとめることで、真になすべきことに時間を使えるようになるといっています。
その中で、そもそも組織的に問題はないか時間浪費の原因を整理するという箇所があります。ドラッカーは、
1)システムの欠陥や先見性の欠如からくる時間の浪費
2)人員過剰からくる時間の浪費
3)組織構造の欠陥からくる時間の浪費
4)情報に関わる機能障害からくる時間の浪費
を主な時間浪費の原因として挙げていて、
3)組織構造の欠陥からくる時間の浪費については、
「組織構造の欠陥からくる時間の浪費がある。その兆候が会議の過剰である」
といっています。
「ウチの会社は会議が多いかもしれない」と思っている方は、どきりとするかもしれませんね。
ドラッカーの言葉は以下のように続きます。
「会議は元来、組織の欠陥を補完するためのものである。人は、仕事をするか、会議に出るかである。同時に両方を行うことはできない」
ここで思わず言いたくなります。
――会議で忙しくしているんだけれど、これは仕事ではないの!?
実際、仕事の時間中どのくらいを会議の時間が占めていたら「会議が多い」と言えるのでしょう。