今年はマネジメントの父、ピーター・F・ドラッカー没後20年を迎えます。そのマネジメント論は現代でも深く息づいています。
「マネジメントの基礎を身につけたい」
「リーダーとして、どうメンバーに接したらいいのかわからない」
「管理職として仕事をしてきたけど、うまくいっていない気がする」
「ドラッカーは難しそうだから、今まで触れてこなかった」
そのような悩みを解決するヒントが詰まった書籍『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』が発売されます。本書は、これまでドラッカーを知らなかった人でも物語の中でその本質を学べる1冊です。
本記事では、著者の吉田麻子氏にドラッカーの魅力を伺いました。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局 吉田瑞希)
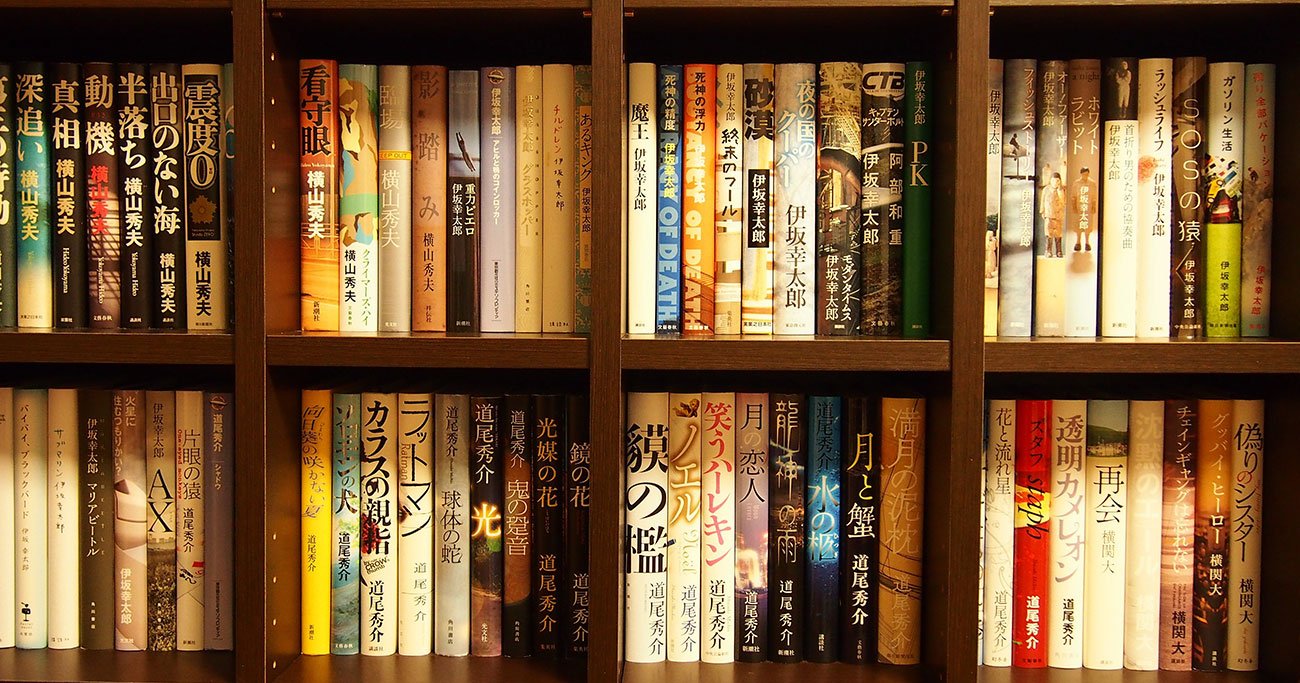 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
時代によって変わる悩み
――吉田さんは10年以上、ドラッカーの読書会を主宰されています。参加されている方は、以前と現在で悩みの変化はございますか。
最近増えていると感じるのは、「ワークライフバランス」や「自分らしいキャリア」に関するお悩みです。
コロナ禍を経てリモートワークが広がり、働き方や住まい方が多様化しました。
その中で、昔ながらの価値観で進む上司と、新しい時代に合ったキャリアを模索したい若手との間にギャップが生まれています。
「できれば飲み会などは避けたいけれど、リモートばかりだと会社のあたたかさを感じにくい」という声もあれば、「これまでは仕事中心で生きてきたけれど、これからは趣味や家族にも時間を使いたい」と考える方も増えています。
ある50代の女性は「定時を過ぎて私用で帰る時に、どうしても罪悪感を覚えてしまう」と語っていました。
一方で、組織は世代も価値観も異なる人たちによって動いています。
その中でどうコミュニケーションを取り、次世代に可能性のある仕組みを残していくか。
これも今ならではの悩みといえるでしょう。
――ドラッカーは今年で没後20年を迎える、いわゆる過去の人ですが、そのような現代ならでは悩みにも解決のヒントがあるのでしょうか?
1909年に生まれ、2005年に亡くなったドラッカーを「過去の人」、「昔流行ったもの」と捉える人も少なくありません。
現に読書会参加者からも、「第二次世界大戦後の企業の事例が書いてあって古く感じる」といった声がありました。
しかし、今なお私たちのドラッカー読書会のファシリテーター仲間は全国に150人以上誕生しており、それぞれの地域で読書会の明かりが灯っています。
ドラッカーを共に学ぶ仲間は日を追うごとに増えており、そこには年代や職種を越えた独特の人間関係が構築されています。
彼らがよく話すのは、たとえば「それぞれのドラッカー」という言葉です。
「ドラッカーはまるでウチの会社のことを書いているみたいだ」、「どうして私のひそかな悩みがここに明記されているんだろう」という驚きの声はよく聞かれます。
ドラッカーは自らを「社会生態学者」であると言っています。彼は「見る人」であったといいます。ドラッカーが知覚し、分析して、記述した大量の事柄は、まるで現代社会からマネジメントという原理を取り出したかのようです。
そして「書き手」でもあります。ドラッカーの言葉は響きます。ドラッカーの「一言」と出合ってそれを実践し、大きく仕事や人生が変化した人をたくさん見てきました。
確かに、ドラッカーが活躍したのは20世紀の後半です。
しかし彼の言葉の多くは「具体的な時代の課題」ではなく「普遍的な人間と組織、事業の原理」を語っています。だからこそ没後20年を経ても、今なお色あせることなく読まれ続けているのだと思います。
例えば、AIやリモートワークといった変化は、ドラッカーが生きていた時代には存在しませんでした。でも、彼は『断絶の時代』でこう言っています。
「若者が答えるべき問題は、何をしたらよいかではなく、自分を使って何をしたいかである」
これは、まさにキャリアや働き方が多様化する現代にそのまま響く言葉ではないでしょうか。
また『マネジメント』では、マネジメントには三つの役割があるとしています。
1.自らの組織に特有の目的とミッションを果たすこと
2.仕事を生産的なものとし、働く人たちに成果をあげさせること
3.社会に与えるインパクトを処理するとともに、社会的な貢献を行うこと
テクノロジーが進化しても、企業や個人が「なすべきことは何か」、「誰の役に立ち、どんな価値を生み出すか」を問うことは変わりません。
つまり、ドラッカーの言葉は「当時しか通用しない古い解決策」ではなく「変化に直面したときに立ち返るべき普遍の原理」なのだと思います。
没後20年を迎えてなお、多くの人が手に取り続ける理由もそこにあるのだと思います。



