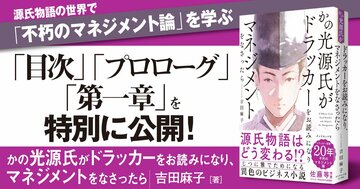今年はマネジメントの父、ピーター・F・ドラッカー没後20年を迎えます。そのマネジメント論は現代でも深く息づいています。
「マネジメントの基礎を身につけたい」
「リーダーとして、どうメンバーに接したらいいのかわからない」
「管理職として仕事をしてきたけど、うまくいっていない気がする」
「ドラッカーは難しそうだから、今まで触れてこなかった」
そのような悩みを解決するヒントが詰まった書籍『かの光源氏がドラッカーをお読みになり、マネジメントをなさったら』が発売されます。本書は、これまでドラッカーを知らなかった人でも物語の中でその本質を学べる1冊です。
本記事では、著者の吉田麻子氏がドラッカーから学べることをストーリー形式で解説します。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
プロローグ:若手社員・山本くんの一日
月曜の朝。
3年目の若手社員・山本くんは「今日は企画書を絶対に仕上げる」と意気込んで出社した。
ところが――
午前9時、先輩から「ちょっとこれ、手伝ってくれる?」と声がかかる。
10時半には別の先輩から「資料コピーお願い」と頼まれ、気づけば11時半。
机に戻れたのは、わずか10分だけ。
午後は会議ラッシュ。
13時からは営業部との打ち合わせ、14時半からはプロジェクト進捗会議、16時からは突発的に招集された「情報共有ミーティング」。
結局、会議室を出たのは17時前。
「やっと自分の時間だ!」と思った瞬間、上司に呼び止められる。
「山本、急ぎでこの数字だけ直してくれ」
結局、山本くんが「今日やりたかった仕事」に一行も手をつけられないまま、一日は終わった。
帰り道。
「俺は一日中“働いていた”のに、“成果”がない。この違和感の正体は何なんだろう」
「時間の使い方が下手なのかな……」
そうつぶやく山本くんの足取りは重かった。
時間泥棒の正体
同じような悩みを抱えている人がいるかもしれませんが、これは決して個人の能力不足によるものではありません。
ドラッカーの『経営者の条件』の『第一章 成果をあげる能力は修得できる』の『働く者を取り巻く組織の現実』という節では、「組織に働く者の置かれている状況は、成果をあげることを要求しながら、成果をあげることをきわめて困難にしている」としています。
ここでは本人の能力や努力とは別に、組織で働くということ自体が、成果をあげることを阻む四つの現実に囲まれており、それは自分ではコントロールできないものであるということが書かれています。
組織にいるということで自動的に発生する「成果を阻む現実」。
時間があってもあっても足りなくなるのはこれら“時間泥棒”のせいかもしれないのです。
では具体的にその四つとは何かを見ていきましょう。