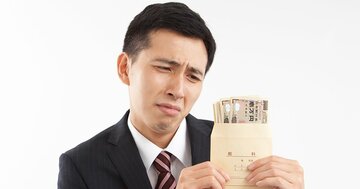唐鎌:日本では長年、物価も賃金も上がらなかった。その上、金融緩和の長期化で円安も進んだ。結果、インバウンドにとっては、先ほど河野さんがおっしゃったような「25年前、30年前の世界」が残されることになった、と。
それは我々日本人にとってもお得感、つまり「消費者余剰」が大きい状態だったわけですよね。この点は海外から帰国した多くの日本人が痛感するところではないかと思います。
同時に、最近はインバウンドによって日本の「消費者余剰」がむしり取られている感覚はたしかにあります。
お得感を楽しめるのは
外国人観光客だけになった
河野:今回の円安が進む前から、日本の“おもてなし”外国人観光客を惹きつけていたのは、「お得感(=消費者余剰)」が非常に大きかったからではないかと考えられます。
現在、グローバリゼーションの進展や、今回の円安インフレの影響で、日本各地で商品やサービスの値上げが進んでいます。その結果、これまで日本国内の消費者が享受していた大きな「消費者余剰」、つまり価格以上の価値を感じられるという感覚が失われつつあるのではないかと心配しています。
「消費者余剰」は、消費者が感じる「お買い得感」を示す概念ですが、今もお話ししたように、これはGDPには含まれません。一方で、企業の利益にあたる「生産者余剰」は、GDP統計にカウントされます。
たとえば、ある商品が6000円で販売されていて、その商品を生産するためのコストが3000円だったとします。このとき、企業が得る「生産者余剰」は、その差額である3000円になります。
一方で、消費者がこの商品に1万円の価値を感じていた場合、6000円で購入できたことで、「消費者余剰」は4000円でした。ところが、もし企業がこの商品の価格を1万円に引き上げたら、「生産者余剰」はさらに4000円増え、合計で7000円になります。その一方で、「消費者余剰」はゼロとなり、消費者は「お得感」を感じられなくなります。