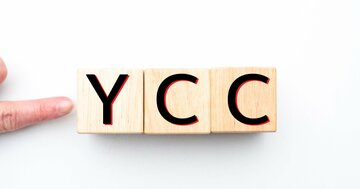河野龍太郎
筆者は日本銀行の利上げ見通しを修正した。次の利上げ時期を従来の6月から4月へ前倒しし、その後も4~5カ月に1度のペースで引き上げ、ターミナルレート(到達金利)2%への到達は2027年10月と想定する。背景には、総選挙の結果を受けた消費税減税を含む拡張財政の現実味、1月会合で示唆されたボード内のタカ派シフトがある。
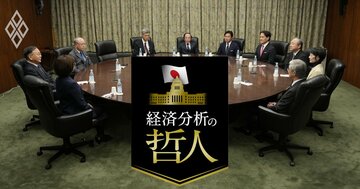
残業時間規制は、中小企業に適用され始めた2020年4月時点では労働需要が落ちていたため、影響が見えなかった。だが、23年5月以降の需要回復で労働供給が追随できず、人手不足が表面化した。労働需給を過小評価していた政府は残業時間規制の緩和を打ち出しているが、望ましい解決策は規制緩和ではなく、過大な労働需要をもたらす低い時間当たり実質賃金の是正と省力化投資だ。

戦後、ポンドからドルへ基軸通貨が移る過程で、英国は通貨切り下げと外貨不足に直面し、スターリング・エリアも巨額損失を被った。インドの分割払い合意、アルゼンチンのドル要求、豪・NZの追随、産油国のドル化とペトロダラー確立――各国の対応は明暗を分けた。日本の対米一極投資にも示唆を与える。

「円安で企業がもうかれば賃金も上がる」は“幻想”だった…専門家が語る根本原因とは
食料品をはじめあらゆる物価が値上がりするインフレ状況に直面し、我々はいま円安の弊害を嫌というほど実感させられている。だが、ほんの数年前までは「円安批判」がタブー視されるほど、だれもがみな円安を歓迎していた事実を忘れてはならない。たとえ賃金がアップしても物価上昇に追いつかないこの苦境の背景に、人気エコノミスト2人が迫る。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

「お得感を楽しむ外国人」と「苦しむ日本人」…インバウンド依存が招く悲惨な末路
外国人観光客による爆買いが日本経済を潤す。政府はそう信じているが、インバウンド需要の拡大でGDPや旅行業界の売上が伸びても、国民の暮らしは豊かにならない。むしろ、外国人消費に頼りすぎた国は、やがて大きな代償を払うことになる。我々の生活はどうなってしまうのか?いま注目のエコノミスト2人が、語り尽くす。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

「生産性が低いから賃上げできない」を信じる人が知らない、企業が絶対に語らない数字
「日本は生産性が低いから、賃上げができない」。一見もっともらしく聞こえるロジックだが、日本の労働生産性は30年間で上昇しているし、そもそも生産性という指標自体が曖昧だ。いま注目のエコノミスト2人の対談を通して、「生産性ガー」の裏に隠された日本企業の不都合な真実に迫る。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。
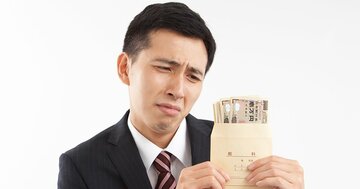
米国長期国債を敬遠する投資家が増え、ドル基軸体制の持続性に疑念が生じている。昨年5月のブルネルマイヤー氏らの講演は、安全資産バブルの特権と脆弱(ぜいじゃく)性を論じた。短期的な崩壊は想定しにくいが、市場期待の変化次第で、ドル一強体制は突如として揺らぐ可能性がある。

トランプ関税や対ロ制裁により、ドルを中心とする国際金融システムの正統性に揺らぎが生じている。中国をはじめとする新興国は、既存秩序に代わる多極的通貨体制や新たな国際決済通貨構想を模索している。IMF(国際通貨基金)体制の原点に立ち返るかのように、バンコール構想の復権が注目されつつある。ドル覇権は終わりの始まりに差しかかったのではないか。

米大統領経済諮問委員会のミラン委員長が、米国の安全保障や国際金融制度など「グローバル公共財」の費用分担を他国に求めた講演は、国際秩序の再設計に一石を投じる。ただ、米国は覇権システムから多大な利益を得る一方で、それを回収して国内で再分配するのに失敗していることが見過ごされている。問題の本質は、他国の費用分担ではない。

国境変更を事実上容認するかのような対ロシア宥和策でウクライナ戦争終結を目指すトランプ政権。ナショナリズム擁護者として注目されるヨラム・ハゾニーは、国家の主権と民族の自決を重視するが、ロシアのウクライナ侵攻はこの理念とどう整合するのか。トランプ外交に大きな影響を与えたとされるハゾニーの論考を紹介する。

日本銀行は過去の円高局面において金融緩和の強化で対応してきた。一方、今回の円安局面での金融引き締めには慎重な姿勢を崩しておらず、低い実質金利水準を維持している。円安放置は輸入インフレによる物価上昇をもたらし、消費を抑制する。結果として、持続的な物価の安定を損ねることになり、それは日銀法の理念に抵触するのではないか。

トランプ氏が米国大統領の座に返り咲く。彼が掲げる経済政策は、いずれも米経済のインフレを高進させる。連邦準備制度理事会(FRB)の利下げペースは鈍化するどころか25年に利上げに転じる可能性さえある。ドル高円安の進行が見込まれ、日本のインフレは上振れしそうだ。インフレのため、日本銀行は12月にも追加利上げに踏み切るだろう。

日本銀行の利上げと量的引き締め開始が契機となった8月初旬の急激な円高・株安は日銀の利上げが早すぎたから起きたのではない。遅すぎたからである。市場が落ちつけば日銀は年内に利上げを再開するだろう。政策金利が1%に達するまではおおむね3カ月に1回ペースで引き上げるとみている。

日本銀行は7月の政策決定会合で国債購入の減額、量的引き締めを開始する。量的緩和、国債の大量購入は長期金利低下を目的に開始されたが、量的引き締めは長期金利が急上昇することがないよう進められ、日銀が大量に国債を保有するストック効果ゆえに現実に長期金利は上昇しにくい。それは超円安にさいなまれ続けることにつながる。
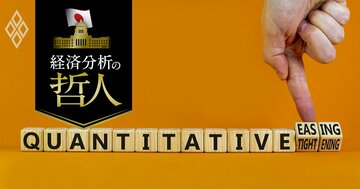
日本銀行は基調的な消費者物価上昇率が2026年度までには目標とする2%に達すると見通している。自然利子率をマイナス0.5%とみて利上げの着地点を1.5%と予想する。ただ、利上げをしても日銀による国債購入を減額し、長期金利が市場機能を取り戻さなければ円安傾向に歯止めがかからない恐れがある。

マイナス金利解除後の日本銀行の次なる利上げは9月、早ければ7月だろう。人口動態と働き方改革による労働供給の限界が需給ギャップをタイト化させている。共に、2025年以降の賃上げ圧力となり、インフレを上向かせる。25年末には政策金利は0.75%に達するとみている。

新型コロナウイルス感染拡大による経済活動抑制が終わり、拡大すると予想された個人消費。しかし、現実には足踏み状態が続いている。停滞をもたらした主因は“異次元緩和”、日銀の超金融緩和政策の継続にある。そのメカニズムを解説する。

日本銀行が「賃上げから物価高への波及」が十分でないことを強調し始めた。これはマイナス金利解除をしないことを意味するのではなく、むしろその準備を示すものだ。弊害の大きなマイナス金利を解除した後も、超低金利政策の継続が不可欠であると、日銀は今後、主張するのではないか。

2023年春闘における賃上げ率は定昇込みで3.6%。しかし、3%台の物価上昇率が続いており実質賃金はマイナスである。人手不足が継続する中、2%台のインフレとベアは定着しそうだが、労働移動を妨げる財政政策の先にあるのは「低成長、高インフレ」である。

日本銀行が7月28日の金融政策決定会合でYCCの「柔軟化」を決めた。背景にあるのは、日銀が当初想定していた以上のインフレ基調の定着だ。エネルギー価格高騰の影響が剥落した後も、賃上げの価格転嫁などが進みインフレ率2%以上が定着する。来年4月にはマイナス金利も撤廃されるだろう。「柔軟化」はその布石である。