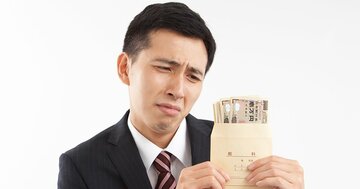河野:「生産者余剰」は企業の利益に近い概念であり、GDPに含まれます。一方で、「消費者余剰」は、たとえ増減があっても、GDP統計には反映されません。つまり、「消費者余剰」が減り、その分が「生産者余剰」に置き換わったとしても、経済厚生は変わりませんが、GDPは「生産者余剰」の増加分だけ膨らむことになります。
消費者のお買い得感が減っているにもかかわらず、GDPが増えたからといって、それを素直に喜べるかというと、なかなか難しいところですよね。
唐鎌:なるほど。数字には表れにくい「お買い得感の損失」、経済学の用語で言えば「消費者余剰」の多寡が景気実感を大きく左右しているということですよね。GDPの伸びと生活実感が乖離する理由がよくわかります。
わずかな利上げでは
もう円安を止められない
唐鎌:伸び悩む家計の消費に代わって、2023年以降の日本経済で気を吐いたのが、インバウンド需要でした。ご承知の通り、2024年の旅行収支黒字は約+6.1兆円に達しました。もちろん、過去最大の黒字です。
パンデミック前の2019年の旅行収支黒字が、当時としては過去最大の約+2.7兆円でした。5年で倍以上になったわけです。
それだけ見れば喜ばしいことに思えますが、実際はインバウンドの消費意欲に近い財やサービスから積極的に値上げが行われており、インバウンド需要と一緒にインフレを輸入しているような状況です。
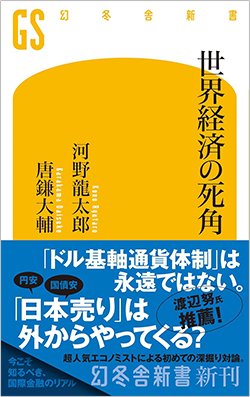 『世界経済の死角』(河野龍太郎、唐鎌大輔、幻冬舎)
『世界経済の死角』(河野龍太郎、唐鎌大輔、幻冬舎)
河野さんがおっしゃるように円安インフレで家計は圧迫されていると思いますが、インバウンド需要もその文脈で理解したいところです。
河野:超円安によって、インバウンド消費が大きく盛り上がっているのは事実ですが、おっしゃる通り、外国人の旺盛な需要によって地方でも物価が上がり、日本の家計は消費を抑制せざるを得ません。
わずかに利上げをしたって、インフレに追いついていなくて、今なお実質金利は深いマイナスの領域にあります。こうした緩和的な金融環境の継続によって円安圧力がもたらされ、それがインバウンド消費を大きく刺激し、その結果、物価が上がって、日本人の個人消費がクラウドアウトされている(押し退けられている)ということです。
経済って、本来は国民のためにあるはずですが、政策当局者の間では、そのことが十分に理解されていない、ということでしょうかね。