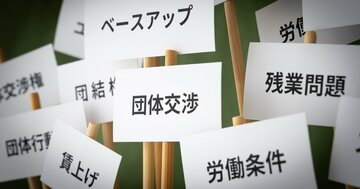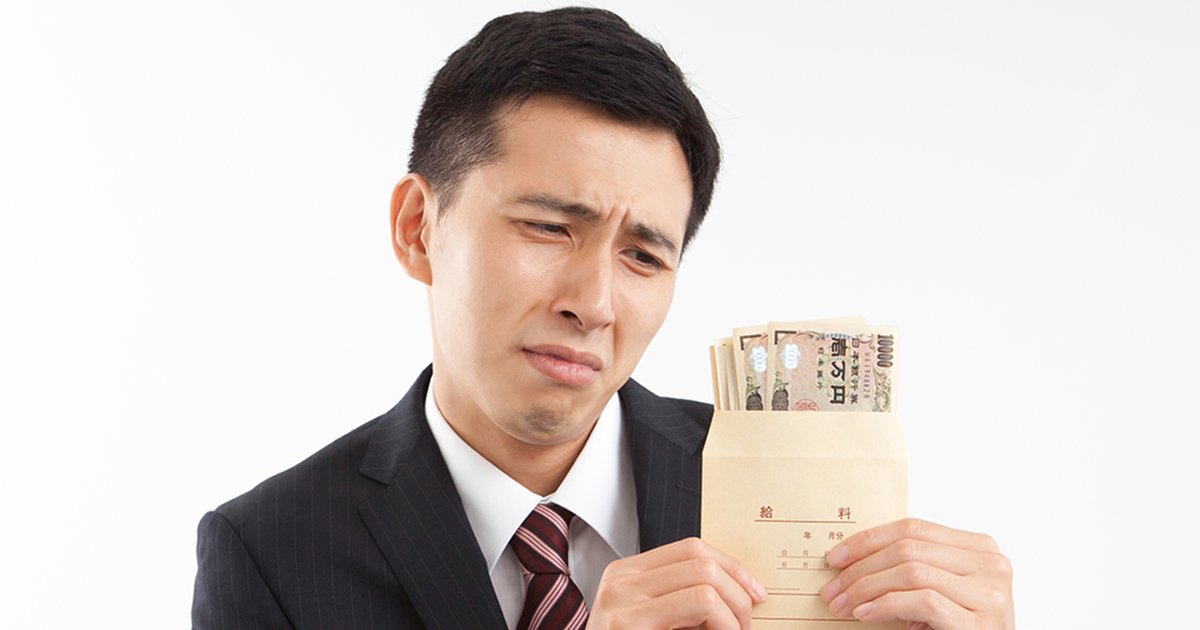 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
「日本は生産性が低いから、賃上げができない」。一見もっともらしく聞こえるロジックだが、日本の労働生産性は30年間で上昇しているし、そもそも生産性という指標自体が曖昧だ。いま注目のエコノミスト2人の対談を通して、「生産性ガー」の裏に隠された日本企業の不都合な真実に迫る。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。
日本が衰退したのは
国民の働きが足りないから?
河野龍太郎(以下、河野):2023年、日本のGDPがドイツに抜かれ、世界第4位に転落したというニュースが注目を集めました。
唐鎌大輔(以下、唐鎌):こういう報道に触れると、「私たちの働きが足りないからだろうか」「もっと頑張って働かなければいけないのか」と、何だか責められているような気持ちになりますよね。
河野:働く人々の賃金は、みんなが一生懸命に働いたから増えるとか、働きぶりが悪いから増えないとか、そう単純なものでもありません。
唐鎌:私たちの暮らしやすさは「賃金」と「物価」のバランスによって決まるものです。たとえば、賃金が2倍になっても、モノやサービスの値段も2倍になれば、実際の生活の豊かさは変わりません。「物価を考慮した実際の賃金」を「実質賃金」と呼びますが、この実質賃金の取り扱いは、世間で言われているほど簡単ではないですよね。
河野:まず、時間当たり実質賃金は、1998年から2023年までの間、日本ではまったくの横ばいでした。正確に言うと、最近の円安インフレの影響で、1998年に比べると2023年は3%ほど低い状況です。