
唐鎌大輔
ECB(欧州中央銀行)は2月14日、域外中銀向けユーロ流動性供給枠「EUREP」の強化・常設化を公表した。危機時の臨時対応から平時の制度へと位置付けを改め、ユーロ建て資産の換金可能性に対する制度的な安心感を高める狙いがある。FRB(米連邦準備制度理事会)の同様のシステムであるFIMA常設化に対応する動きとして、ユーロの国際的役割を底上げし、基軸通貨性を強化する布石として注目される。

「ドル離れ」局面で円が連れ安になった背景には、経済・安全保障での対米依存という米国と“一蓮托生”の構図がある。同じもろさは韓国ウォン、フィリピンペソにも及び、台湾・朝鮮半島有事の最前線に立つ通貨は有事通貨として評価されやすい。一方でAUKUS(米国、英国、オーストラリア3カ国よる安全保障協力の枠組み)の一員である豪ドルは上昇した。地政学リスクの東アジアからの距離と資源国としての強みが分岐点となる。

2025年4月の「解放の日」以降、金融市場ではドル安を背景に「ドル離れ」が新常態のように語られてきた。しかし名目実効為替相場や対米証券投資統計を検証すると、その実態は必ずしも単純ではない。ドル安局面はいったん収束しつつある一方、米長期金利の「下がりにくさ」は新たなリスク要因として浮かんでくる。

高市首相の台湾有事発言を受け、中国政府が自国民に対し日本への渡航自粛を呼びかけ、旅行会社も販売停止に動き始めた。中国人観光客は約2兆円規模の需要を生み、日本経済にとって最大級のインバウンド市場である。すでに失速気味だった訪日需要に追い打ちとなれば、景気下押しを通じて日銀の利上げ判断にも新たな不透明要因をもたらしかねない。

「円安で企業がもうかれば賃金も上がる」は“幻想”だった…専門家が語る根本原因とは
食料品をはじめあらゆる物価が値上がりするインフレ状況に直面し、我々はいま円安の弊害を嫌というほど実感させられている。だが、ほんの数年前までは「円安批判」がタブー視されるほど、だれもがみな円安を歓迎していた事実を忘れてはならない。たとえ賃金がアップしても物価上昇に追いつかないこの苦境の背景に、人気エコノミスト2人が迫る。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

「お得感を楽しむ外国人」と「苦しむ日本人」…インバウンド依存が招く悲惨な末路
外国人観光客による爆買いが日本経済を潤す。政府はそう信じているが、インバウンド需要の拡大でGDPや旅行業界の売上が伸びても、国民の暮らしは豊かにならない。むしろ、外国人消費に頼りすぎた国は、やがて大きな代償を払うことになる。我々の生活はどうなってしまうのか?いま注目のエコノミスト2人が、語り尽くす。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。

「生産性が低いから賃上げできない」を信じる人が知らない、企業が絶対に語らない数字
「日本は生産性が低いから、賃上げができない」。一見もっともらしく聞こえるロジックだが、日本の労働生産性は30年間で上昇しているし、そもそも生産性という指標自体が曖昧だ。いま注目のエコノミスト2人の対談を通して、「生産性ガー」の裏に隠された日本企業の不都合な真実に迫る。※本稿は、河野龍太郎、唐鎌大輔『世界経済の死角』(幻冬舎)の一部を抜粋・編集したものです。
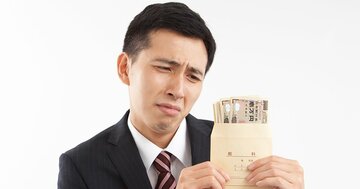
IMF(国際通貨基金)が発表した2025年6月末の外貨準備に占めるドル比率は56.32%と過去最低を更新した。だが為替調整後は57.67%でおおむね横ばい。上半期のドル安が見かけの比率低下を拡大させた。短期の評価替えと、長期の「脱ドル」トレンドの交錯をデータで分析するとともに、今後のドル離れの行く先を検証する。

2025年春以降、「ドルの基軸通貨性」が金融市場の主要テーマとして注目を集めている。特に4月には資本流出による「米国離れ」を象徴する報道が相次いだが、5月には過去最大規模の資本流入が記録されるなど、実態との齟齬も見られる。対米証券投資データを基に、資本フローと為替市場の動きから「米国離れ」論の真偽を検証する。

日本銀行が発表した資金循環統計によると、家計の外貨建て金融資産の比率が着実に上昇している。実質的に10%時代も視野に入りつつある。若年層を中心にNISAによる投資活動も活発化し、「貯蓄から投資」への動きが加速している。その背景には日本経済への諦観がある。

2025年6月の日本銀行の政策決定会合では、国債買い入れ減額ペースの緩和が決定された。債券市場の混乱を抑える「優しさ」が表れた形だが、予見可能性や量的引き締め(QT)の信認に与える影響は小さくない。日銀は、金利上昇と円安の板挟みに立たされている。

日本の超長期金利が上昇する中で、為替市場では「円金利上昇による円買い」という見方が散見される。しかし、こうした解釈は政府債務への懸念や対外経済構造の変容を無視した短絡的な見方である。金利上昇の真因とそれが円売り要因となる背景を構造的に読み解く。

トランプ関税の目的は貿易赤字の縮小にある。そのために、ドル安も志向している。ただ、過去を振り返るとドル安は早期の貿易収支改善には結び付いていない。いわゆるJカーブ効果が先んじて発現するためである。

2024年の経常収支黒字は過去最大となったが、サービス収支のうちのデジタル収支の赤字、旅行収支の黒字も過去最大となった。今後を見据えると、デジタル収支の赤字はさらに拡大し、旅行収支の黒字は頭打ちになる公算が大きい。見えてくるのはサービス収支の赤字10兆円超えの常態化である。

ユーロ圏の景気減速は明らかであり、ECBは利下げを継続中だ。景況感格差、金利格差から対ドルでのユーロ安が進行しており、インフレ抑制の観点からさらなる利下げの制約要因となりつつある。景気動向に合わせて利下げを継続すれば1ユーロ=1ドル、いわゆるパリティ割れは確実だ。

12月19日、日本銀行は金融政策の現状維持を決め、一時1ドル157円台まで円安が進んだ。ただ、今後の政策金利の方向性は上向きである。一方、スイス国立銀行は12日に政策金利の0.5%引き下げを決定し、両者の政策金利の水準はほぼ変わらなくなった。だが、基調としての円安スイスフラン高は変わらない。この差をもたらすのは日本とスイスの外貨を稼ぐ力の差である。

2024年7~9月期のGDP(国内総生産)の成長率は、市場予想を上回った。個人消費が思いのほか堅調だったことが寄与している。しかし、定額減税などの特殊要因に支えられた部分が大きく、景気の基調は強くない。景気面からは日本銀行の利上げは正当化されないとみるが、12月の利上げの可能性は高いとみている。その背景を解説する。
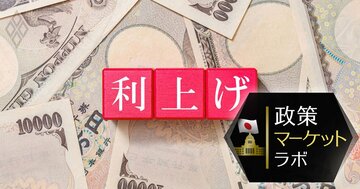
11月のFOMC(米連邦公開市場委員会)の動向に注目が集まっているが、為替市場の予測にあたって重要なのは1年後の金利動向である。1年後には米国の利下げの終点が争点になっている可能性が高い。その時点では、再び円安へと転じるとみる。円高局面は短命に終わりそうだ。

米国の利下げを先取りする形で、ドル円は139円台をつけた。円高の要因を日米金利差とする解説が流布しているが、背景には貿易収支の赤字縮小を主因とする需給の改善もある。一方、依然デジタル赤字も拡大している。こうした構造を熟慮した上で今後の日本経済の在り方を考えてほしい。

セブン&アイ・ホールディングスへのカナダのコンビニエンスストア大手による企業買収案件が明らかになった。日本の対内直接投資残高の対GDP(国内総生産)比率は、北朝鮮よりも低い。円安の今、企業買収による直接投資というカードはその重要性が注目されているだけに、実現可否にかかわらず本件の行方が意味するところは大きい。
