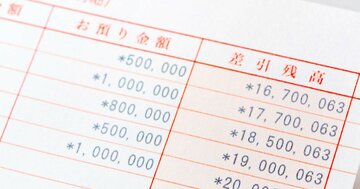【一発アウト】家族が泣く…絶対やってはいけない「遺言書のNG行動」
人生100年時代、お金を増やすより、守る意識のほうが大切です。相続税は、1人につき1回しか発生しない税金ですが、その額は極めて大きく、無視できません。家族間のトラブルも年々増えており、相続争いの8割近くが遺産5000万円以下の「普通の家庭」で起きています。
本連載は、相続にまつわる法律や税金の基礎知識から、相続争いの裁判例や税務調査の勘所を学ぶものです。著者は、相続専門税理士の橘慶太氏。相続の相談実績は5000人を超えている。大増税改革と言われている「相続贈与一体化」に完全対応の『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】 相続専門YouTuber税理士がお金のソン・トクをとことん教えます!』を出版した。遺言書、相続税、贈与税、不動産、税務調査、各種手続という観点から、相続のリアルをあますところなく伝えている。2024年から贈与税の新ルールが適用されるが、その際の注意点を聞いた。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
家族が泣く…絶対やってはいけない「遺言書のNG行動」
本日は、遺言書トラブルについてお話しします。
2019年と2020年に自筆証書遺言の取り扱いを定めた法律が大幅に改正されました。自筆証書遺言にまつわるトラブルと、民法改正について解説していきます。
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑と封筒と糊があれば、いつでもどこでも簡単に作れます。しかし、簡単に作れるために発生するトラブルもあります。
トラブル① 紛失
紛失したのが遺言を書いた本人であるなら、新しく書き直せばいいだけです(遺言書は日付の新しいものだけが有効なので)。問題は、相続が発生した後に、遺言書を預かっていた人が紛失してしまうケースです。
よくあるのは「父は『遺言書を弁護士に預けている』と言っていたので、その弁護士を訪ねたのですが、その弁護士が先に亡くなっており、遺言書は見つかりませんでした……」というケースです。また、相続人の誰にも内容を知られたくないからと、自分しか知らない秘密の保管場所に遺言書を隠す人もいます。そのような遺言書は、相続発生後に誰からも発見されず、永久に秘密になってしまうこともあるので注意しましょう。
トラブル② 偽造
実際にあった話ですが、あるところに、鈴木一郎(仮名)と鈴木二郎(仮名)という兄弟がいました。二郎は素行が悪かったため、父から遺言書に「全財産を一郎に相続させる」という内容を書かれてしまいました。父の相続発生後、二郎は一郎よりも早く遺言書を発見し、その内容を読み、このままでは自分が遺産を相続できないことを知ります。
考えた二郎は、その遺言書の、一郎の「一」の字の上に、横棒を一本書き加えました。そうすると、その遺言書は「全財産を二郎に相続させる」に早変わり! 一郎は「生前の父と二郎の関係性からみて、そのような遺言書を残すはずがない。二郎が遺言書を改竄した」と訴えます。しかし、二郎は遺言書に書かれている内容は父の真意であり、改竄した証拠はどこにも無いと反論。結局、この裁判は非常に長い年月をかけて決着がつきました(一郎が勝訴したそうです)。
このように、自筆証書遺言は少しの改竄だけで、内容を180度変えることができるのです。こういった事態を防ぐために、相続人の名前の後ろには生年月日を記載するようにしましょう。例えば「相続人鈴木一郎(昭和○○年○月○日生)」のような形です。こうすれば簡単に改竄することはできません。
トラブル③ 破棄
自分に不利な内容の遺言書を見つけた場合、その遺言書を破棄してしまうケースもよくあります。本来、遺言書の改竄や破棄が発覚した場合、その人は、相続する権利を剥奪されるという非常に重い処分を受けます。さらに刑法上も、私文書偽造罪や私用文書等毀棄罪などの罪に問われます。
しかし、遺言書を破棄された場合には、【もともと遺言書が存在していたのに破棄された】ということを立証しなければならず、これを立証するのは極めて困難です。法律の原則は疑わしきは罰せず。証拠も無く「破棄されたと思う」というレベルでは、結局泣き寝入りするしかないことになります。こういった事態を防ぐためにも、自筆証書遺言の保管には細心の注意を払わなければならないのです。
トラブル④ 貸金庫
遺言書を銀行の貸金庫などに保管すると、いざ相続が発生したときに、貸金庫から遺言書を取り出せなくなることがあります。相続人が貸金庫を開けるためには、相続人全員の同意書か、遺言書が必要になります。しかし、肝心の遺言書が貸金庫の中にあれば、開けることができません。
銀行としても、特定の相続人が単独で貸金庫を開けることを許すと、他の相続人から「貸金庫の中身をネコババされた! 何で勝手に貸金庫を開けたんだ!」と訴えられるリスクがあります。そのため、相続人全員の同意がないと貸金庫を開けられないようにしています。なお、遺言書で遺言執行者という人を選任し、執行者に「貸金庫を開ける権限も与える」と指定しておけば、遺言執行者が単独で貸金庫を開けることができます(遺言執行者は相続人を指定することも可能です)。
しかし、せっかくこうした権限を与えられていても、肝心の遺言書が貸金庫に入れられてしまうと、権限が与えられていることを銀行の人に証明できません。結局、相続人全員の同意が必要になってしまいます。そのような事態を防ぐためにも、遺言書を貸金庫で保管するのはやめましょう。
(本原稿は『ぶっちゃけ相続【増補改訂版】』の一部抜粋・編集を行ったものです)