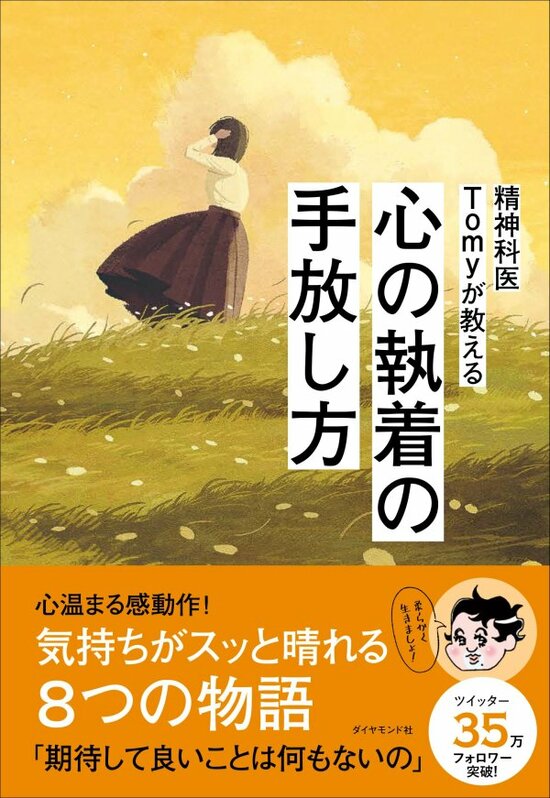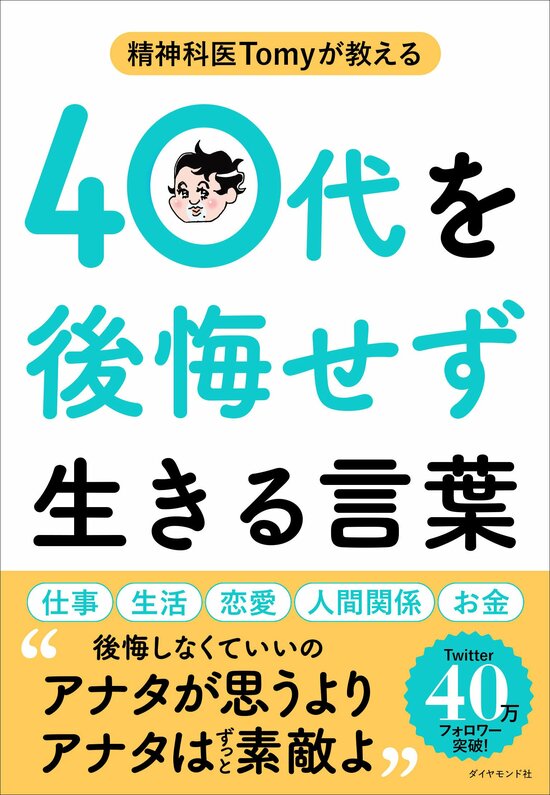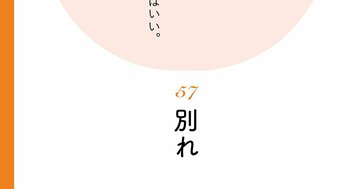「頑張らなくていい」という言葉が持つ、もう一つの側面
では、精神科医がうつ病の人に「頑張らなくていいですよ」と言うかというと、私はそれも違うと考えています。「頑張れと言ってはいけない」の反対は「頑張らなくていいですよ」ではないのです。
うつ病になる人は、これまで自分を追い込んで頑張ってこられたケースが非常に多いです。そのような人が「頑張らなくてもいいですよ」と言われてしまうと、寂しさを感じたり、自分の評価がさらに下がってしまったりして、場合によってはかえって本人を追い詰めてしまう可能性があります。
つまり、「頑張らなくてもいいですよ」という言葉は、時として非常に冷たい言葉になり得るのです。これは、ご家族や周りの人が声をかける場合も同様で、個人的にはあまり使わないほうが良いのではないかと思っています。
大切なのは「ありのままの自分」でいること
では、どのように声をかけるのが良いのでしょうか。私は、「自分らしくいなさい」「ありのままに」と伝えるのが一番良いと考えています。
高市総裁の「ワークライフバランスを捨てる」発言も、「自分らしく、そのように宣言します」とおっしゃったに過ぎません。ですから、周りは「疲れたときには、ありのままの自分を観察して、少し休んでくださいね。そのままでいいんですよ」という気持ちで、全身でそれを示し、見守ることが正しい姿勢なのではないでしょうか。
今のありのままの自分でいい
ワークライフバランスは確かに大事です。しかしそれは、「辛い時はやめる、楽しい時はやる」というように、自分らしく決めていけば良いものだと思います。その方針に対して、他人が目くじらを立てて非難するようなことではないでしょう。
そして、「頑張れ」と言ってはいけないかもしれませんが、「頑張らなくていいですよ」という言葉もまた違う、ということをお伝えしました。たとえ頑張りすぎたと感じても、「今のありのままの自分でいいんだ」と受け入れることが大切です。
セルフモニタリングの重要性
「今の自分の気持ちはどうだろう?」「どうしたいだろう?」と自問自答してみてください。「もう少しできそうだけれど、面白くないな」と感じるかもしれません。あるいは「肉体的に無理をすると崩れるかもしれないけど、本当にやりたいことだろうか?」と考えた時に、「今日はだるいな」「気が向かないな」と感じたら、やめれば良いのです。
もしそこで「~するべきだ」という気持ちが湧き上がり、ありのままの気持ちを無視するような行動を自分に強いているとしたら、それは良い状態とは言えません。
ワークライフバランスの話をしましたが、最終的にお伝えしたかったのは、自分の人生をどうコントロールしていくかを考えた時、自分のありのままの気持ちを観察する「セルフモニタリング」が非常に重要である、ということなのです。
※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)の著者による特別原稿です。