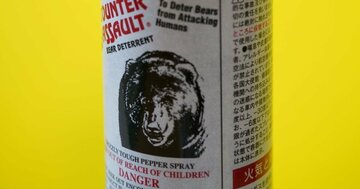そして、クマの世界にも階級や力関係があり、奥山は体が大きく力の強いクマが牛耳っている。一方、それ以外のクマは強い個体を恐れて、居場所を探して里山付近に下りる。
里山に下りるクマたちは、かつては「人との間合い」をよく知っていた。本来は人を避けて上手に動くことができたが、最近になって人と接触している理由は、大きく2つある。
まず、未熟なまま子を持つ若いクマが増えていること。母グマの体長が1メートル程度の場合、大きさに鑑みると年齢は3歳くらい。つまり2歳で交尾をしている。この若さで母親になるクマは、昔の自然界ではあまり見られなかった。
 写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
里山にいるクマの個体数が増え、繁殖期に交尾をしたいオスが多くなった結果、若いメスグマが「仕方なく妊娠して子を持つ」という選択を強いられているのかもしれない。クマとして未熟であるが故に、意図せずして人間の前に出てきている場合もあるのだ。
もうひとつは、人間側の「クマを森に押し返す力」が弱まっていること。集落付近で暮らす都会化したアーバンベアは人との距離感を心得ているとはいえ、人間側の対策が不十分になると増長する。
過疎と高齢化でハンターの数が減り、イヌが飼われなくなった。住民が市街地周辺の草を刈らなくなり、クマの食べ物になりそうな果実を定期的に収穫できなくなった。クルマが市街地を頻繁に走らなくなった――。
そういった地域では、クマの警戒心が薄れているのだ。「森に押し返す力」が弱まった地域にクマが出て、その地域に住んでいる人間を襲っている可能性は高い。