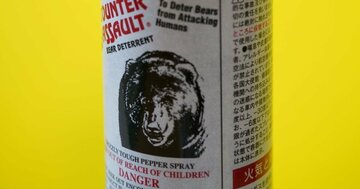「クマの2年周期」に着目すると…
27年は、23年や25年と同じ状況に
「25年はクマの被害が多く発生する、警戒が必要」との予測を見事的中させた米田氏。というのも23年はクマの出生数が多く、かつてないほど赤ちゃんグマが生まれたとみられている。その子グマが2歳になり、自立して自由に動き始めるのが25年だったからだ。つまり、「クマの2年周期」に着目すると理解しやすい。
この法則も踏まえて、26~27年の中期の見立てを聞いた。クマ被害は日本で当たり前の光景になってしまうのか?
「24年はドングリ類が豊作で、25年は子連れクマが多い。つまり今年と同じ事が27年にも起こると思う。ただし、各地の駆除意識が強ければ、今年と同等か、少しは減るだろう」
「26年は春の早い時期から体長50センチほどのクマが人里や民家、城址のような広い緑地から現れるだろう。そして夏に進むと、クマは市街地にも出るはずだ。その翌年となる27年は、23年や25年と同じ状況になることを推測する」
最後に米田氏は、「マスコミがヒグマもツキノワグマも混在して報道していることには注意してほしい。これにより一般市民もやや誤解していて、ツキノワグマの凶暴性が底上げされている感がある。両種では生態が異なり、対処法も違う」と語った。
解説してきたように、地球温暖化を背景とする暖冬や、地方の過疎化・少子高齢化によって人間側の「クマを森に押し返す力」が弱まっていることも、クマの“凶暴化”の一因になっていることを忘れないようにしたい。