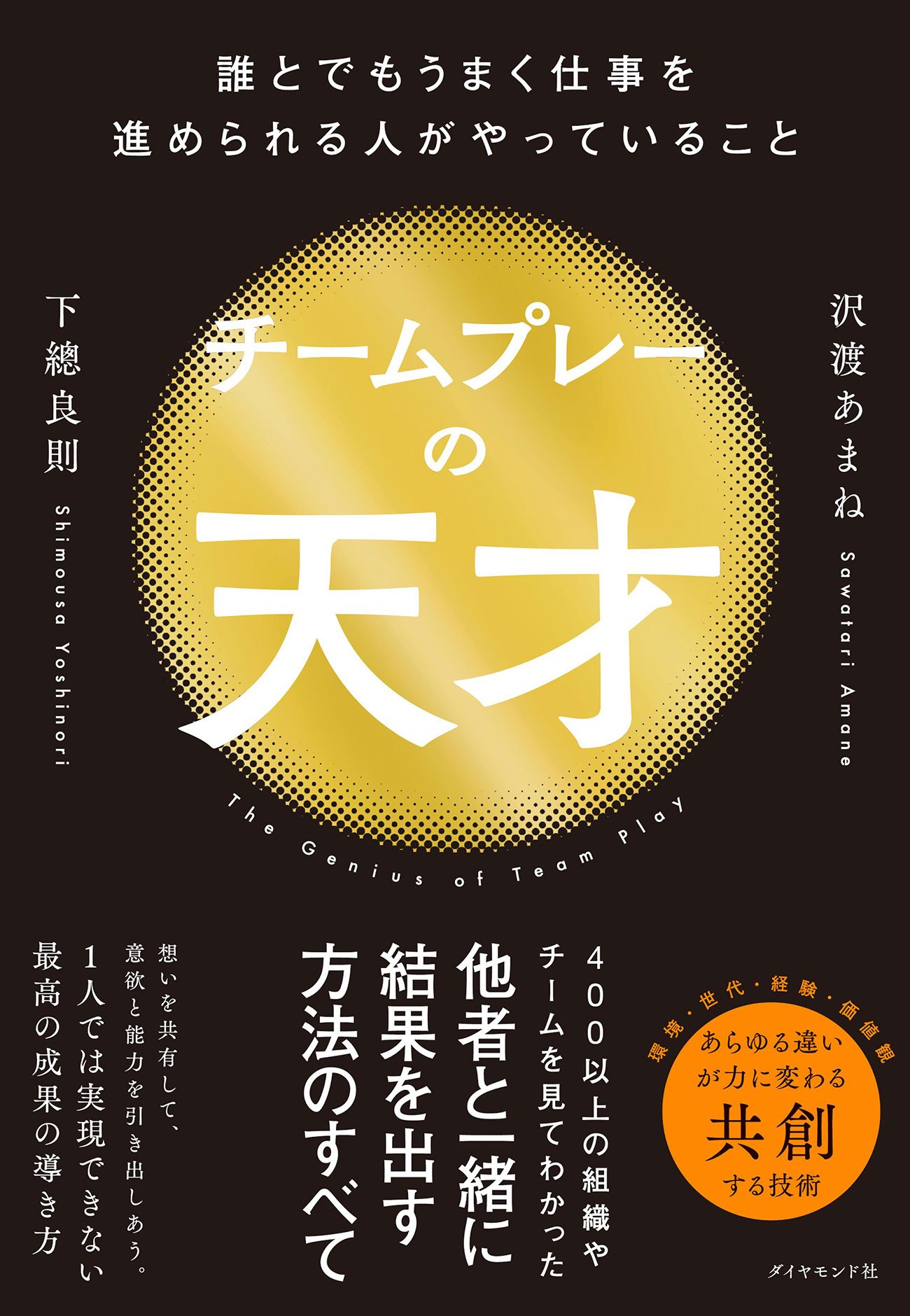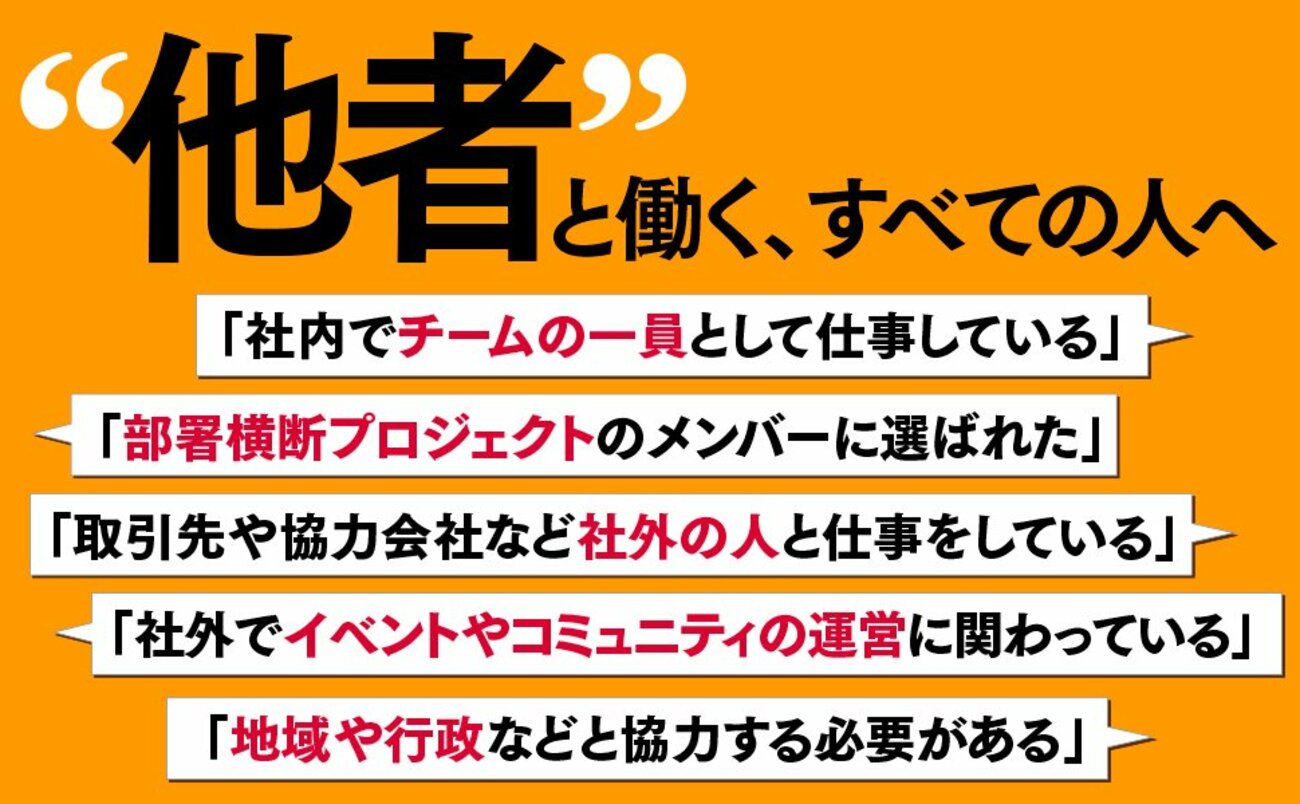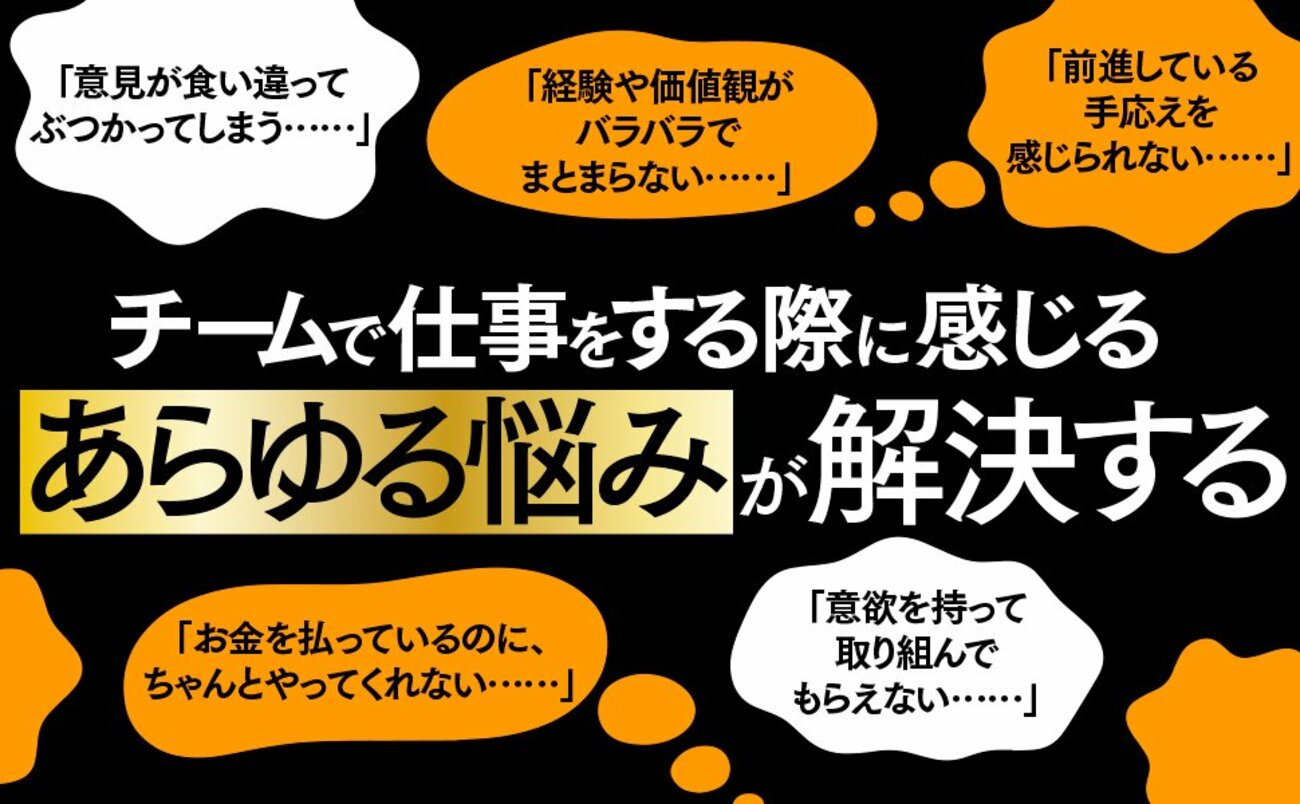他部署と協力したり他社と連携したりと、「チームで仕事をする」ことは多いもの。一方で、価値観や背景の違う相手とのすれ違いや衝突にモヤモヤすることも……。じつは何気ない振る舞いが、無意識のうちに仲間を疲弊させてしまうことがあります。信頼を失い、チームのやる気を削いでしまう“やってはいけない行動”とは? 400以上の組織やチームを見てきた組織開発の専門家が「誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること」をまとめた書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)から、そのヒントを紹介します。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
仕事仲間を「疲弊させる」行為とは
チームで仕事をする際、意外と見落としがちなのがコミュニケーションの「手段」への気遣い。
なかでも、DM(ダイレクトメッセージの略)など、特定の相手との1対1の閉じたコミュニケーションには要注意です。
これは口頭のコミュニケーションでも同じです。
情報が当事者間だけでやりとりされると、ことの経緯や決定事項がチームに共有されにくくなります。
結果、連絡を受けた人が、後々チームの他のメンバーや周りの人たちに説明するのに骨が折れてしまいます。
チームに対する「意欲」が削がれてしまう
私はこれを「“説明しよう!”コスト」と呼んでいます(昔の戦隊ヒーローもののテレビドラマで、ナレーターが視聴者にものがたりの経緯やヒーローの必殺技の内容を「説明しよう!」の出だしで解説していたシーンになぞらえて)。
後から報告だけ受けたメンバーも、経緯がわからないために自ずと下請けマインドが強くなったり、そのテーマに対する心の持ち方、気持ちの置き方に迷いやすくなったりするデメリットもあります。
すなわち、チームへの意欲的な参画の動機を削いでしまう。
チームの仲間に好かれる人の「気遣い」
最初のやりとりは1対1で始まったとしても、どこかのタイミングで
「ここからはグループチャットでやりとりしましょう」
「チームのメーリングリスト宛てに送ってください」
など、チーム全体で同じ情報を共有できるやりとりに切り替えましょう。
とはいえ、何でもかんでも全員に一斉共有すればいいというわけでもありません。
「担当者を複数名決めて、誰か1人だけに情報が集中し、業務が属人化しないようにする」
「情報整理役をおいて、交通整理をしてもらう」
状況や情報の性質に応じて、そのような体制を検討したいものです。
(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者との仕事をラクにする具体的な93の技術を紹介しています)