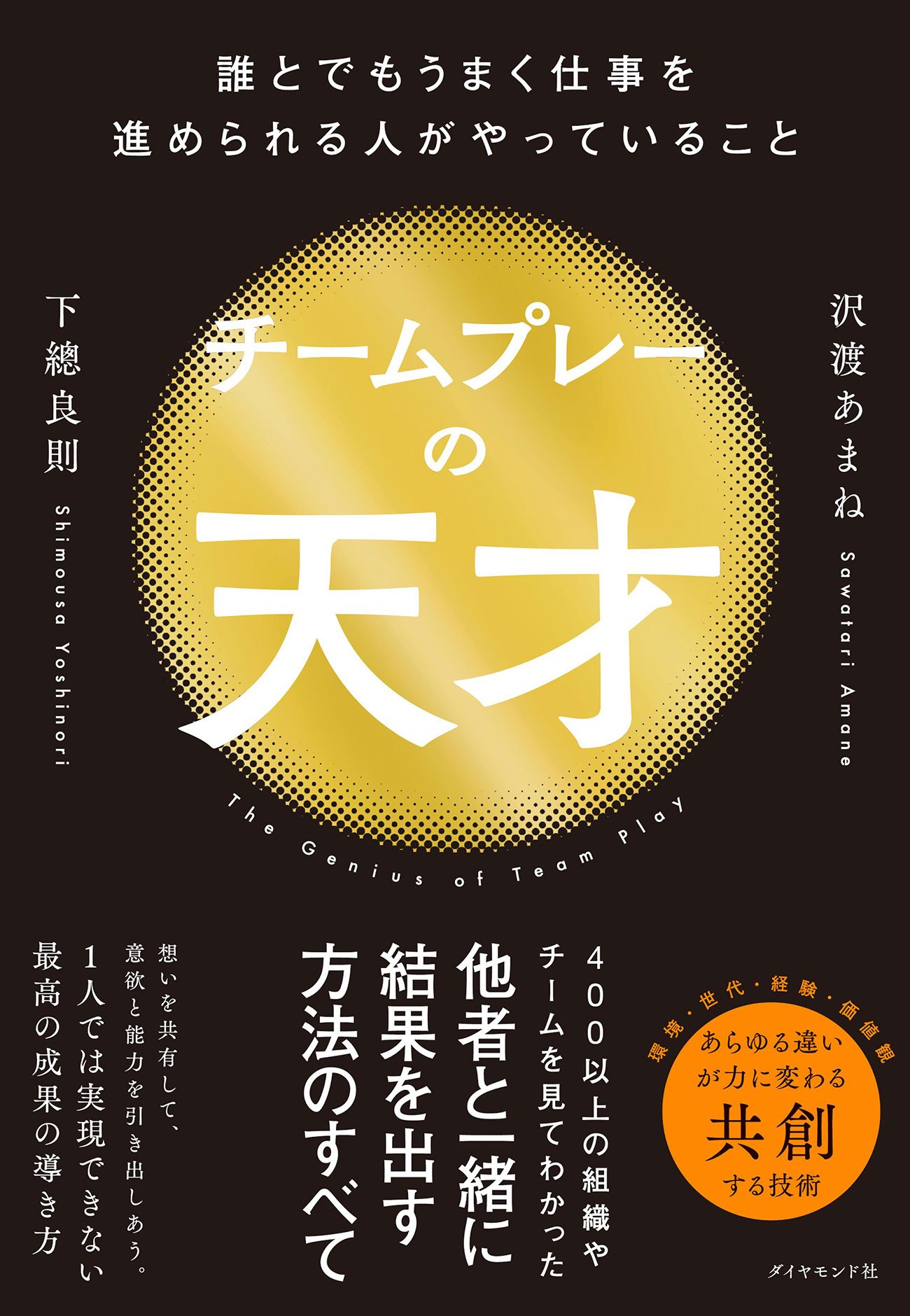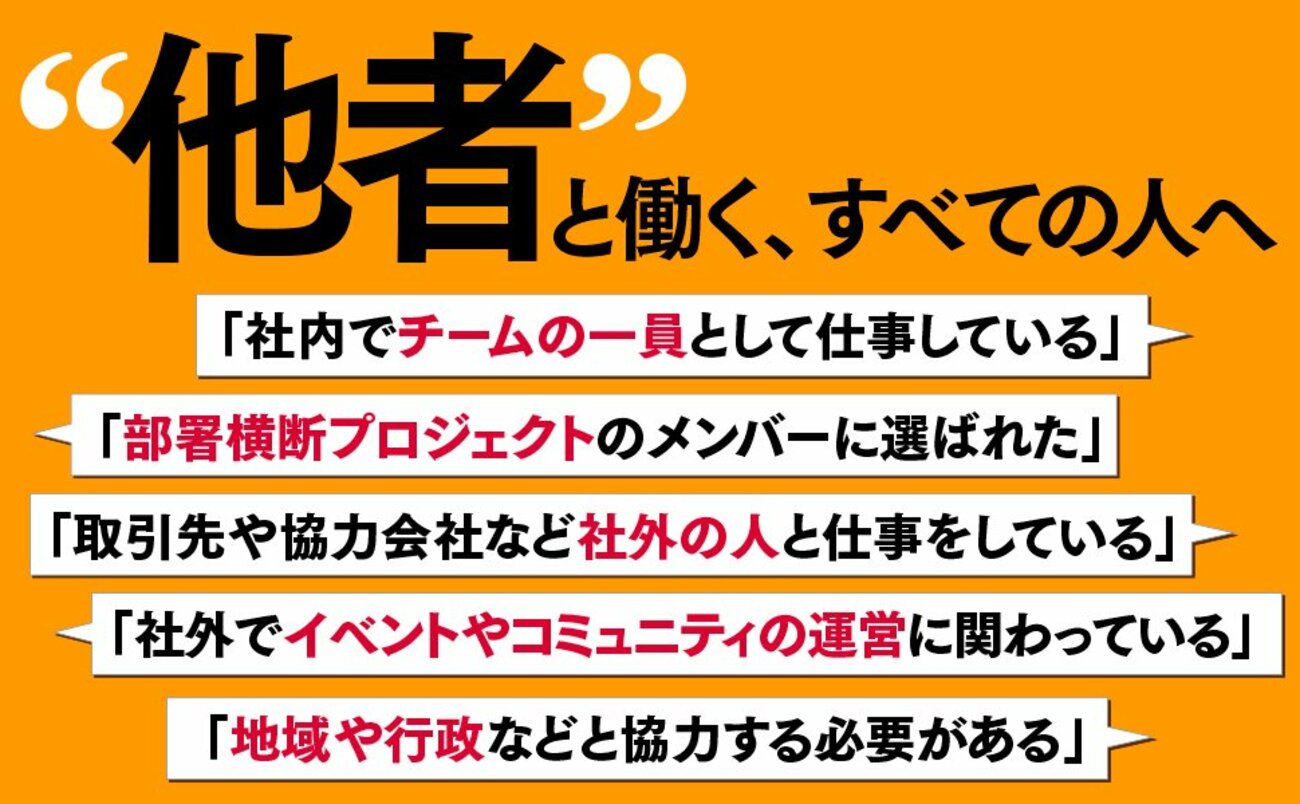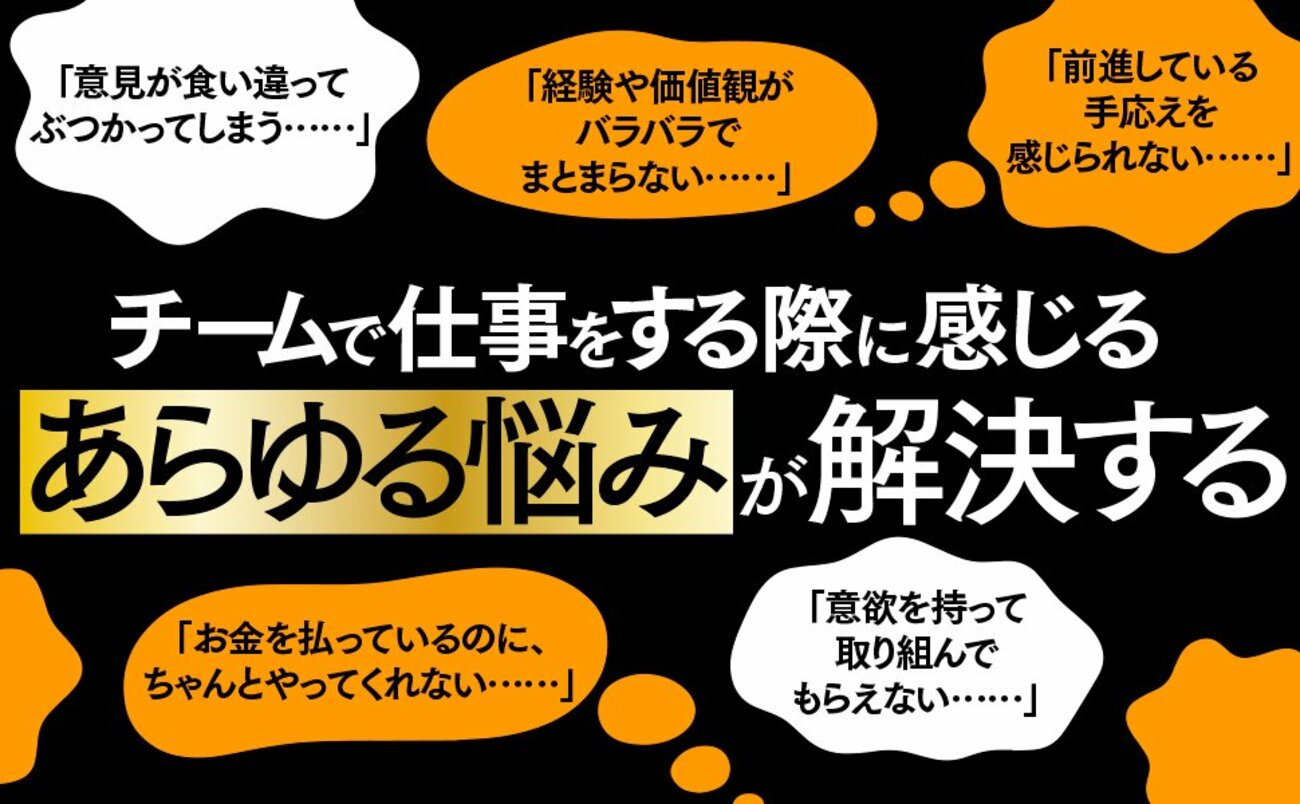チームメンバーのモチベーションを高め、仲間に気持ちよく協力してもらいたい。けれど、いざ伝えようとすると「どう言えばいいのか」「どうすれば動いてくれるのか」がわからない。リーダーにかぎらず、チームマネジメントや動機づけは、学んでおきたい重要スキルです。400以上の組織やチームを見てきた組織開発の専門家が、「誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること」を体系化した書籍『チームプレーの天才』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)から、そのヒントを紹介します。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「会社やチームのため」だけでは走りきれない
キャリアに対する人々の関心は日に日に高まりつつあります。
会社から言われたことを忠実にこなしていれば明るい未来が約束された時代は、もはや終わったと言えるでしょう。
「その仕事の経験が、自分の未来にどう役立つか?」
「それによって将来“食いっぱぐれない”人材になれるのか?」
あらゆる仕事において、この問いが頭をよぎります。
もはや人生100年時代と呼ばれる世の中を強く生き抜いていくための問いと言っても過言ではありません。
チームメンバーが「モチベーション」を失ってしまう理由
共創活動を進める上でも、各メンバーの「キャリア」は無視できません。
そのチームやプロジェクトに対して自分がどう貢献できるか、そこでどんな体験をしてどんな能力や経験を身につけることができそうか、そのイメージを持てるか持てないかでメンバー(またはそのチームやプロジェクトに関わる関係者)のモチベーションは大きく変わります。
「チームの役に立てていない」
「このプロジェクトを頑張っても、何にも身につかない」
「時間の無駄になるだけ」
これではモチベーションは上がりませんし、プロジェクトがうまくいったとしても、その後のキャリアにマイナスの影響をもたらしかねません。
チームで「共創」できる人が「言わない」こと
チームプレーがうまい人は、各メンバーが「このプロジェクトが自分のキャリアにどう役立つか」「そのために自分は何をすればいいか」をイメージできるようなコミュニケーションをしています。
「仕事だから」
「チームのためだから」
「やってくれないと困るから」
とは、絶対に言いません。
これでは、本人のモチベーションをむしろ下げてしまうのです。
(本稿は、書籍『チームプレーの天才』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、他者とうまく仕事を進めるための具体的な93の技術を紹介しています)