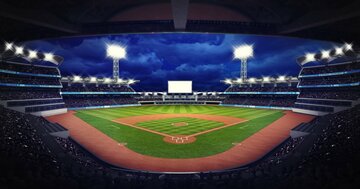「構想力・イノベーション講座」(運営Aoba-BBT)の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』(ダイヤモンド社)は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。企業とユーザーが共同で価値を生み出していく「場づくり」が重視される現在、どうすれば価値ある戦略をつくることができるのか? 本連載では、同書の内容をベースに坂田氏の書き下ろしの記事をお届けする。
 Photo: Alina Nikitaeva/Adobe Stock
Photo: Alina Nikitaeva/Adobe Stock
大きな戦略を描くだけでは、成功しない
あなたの会社では、優秀な経営企画スタッフや外部の戦略コンサルタントが作成したにもかかわらず、失敗に終わった、もしくはうまく実行に移せなかった戦略はありませんか?
多くの企業では、戦略そのものの内容というよりも、「最初の1歩」を誤ることでつまずいています。
どんなに壮大な構想を描いても、最初の着手点を見誤れば、成果にはつながりません。
成功する戦略と失敗する戦略の分かれ目は、最初にどこから着手するかにあります。
局所的課題の解決から、仕組みを作る
戦略の方向性自体が間違っていたわけではないのに、実行段階でつまずく企業は少なくありません。
失敗する多くのケースでは、全体構想に気を取られ、肝心の足元の課題を見過ごしていることが原因です。
たとえばAmazonは、創業当初、書籍に特化したECサービスとしてスタートしました。
その背景には、「書籍は、実店舗において顧客の嗜好にあわせて棚を最適化することは難しいが、ECであればそれが可能」という明確な着眼点がありました。
書籍は品数が膨大で在庫回転率も低く、デジタル化による効率化の余地が最も大きい領域であり、ECという仕組みを試すのに最適なカテゴリだったのです。
仕組みを構築したうえで、包括的サービスへと昇華させる
Amazonは、書籍という限定された領域の中で、検索、レコメンド、在庫管理、物流などの仕組みを徹底的に磨き上げていきました。
このプロセスを通じて、他のカテゴリにも応用可能な普遍的なシステム基盤を整え、現在のような包括的なサービス展開へとつながっていったのです。
つまり、最初の1歩を「小さく」「深く」踏み出したことで、後の大きな戦略へとつながる“仕組みの核”が生まれたのです。
これこそが、成功する戦略に共通する構造です。
反対に、最初から全方位的に手を広げようとすれば、課題が拡散し、どの仕組みも中途半端に終わります。
戦略とは、最初の1歩をどこに置くかで、その後の展開が大きく左右されます。
IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士(MBA)。ITストラテジスト。
大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング(現フォーティエンスコンサルティング)に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援(事業計画立案・実行、M&A、資金調達など)に従事。
その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。
退任後、経営共創基盤(IGPI)に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。
単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』(共にダイヤモンド社)がある。