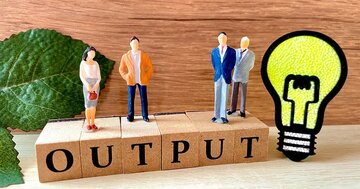「構想力・イノベーション講座」(運営Aoba-BBT)の人気講師で、シンガポールを拠点に活躍する戦略コンサルタント坂田幸樹氏の最新刊『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』(ダイヤモンド社)は、新規事業の立案や自社の課題解決に役立つ戦略の立て方をわかりやすく解説する入門書。企業とユーザーが共同で価値を生み出していく「場づくり」が重視される現在、どうすれば価値ある戦略をつくることができるのか? 本連載では、同書の内容をベースに坂田氏の書き下ろしの記事をお届けする。
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
時代は「モノづくり」「コトづくり」から「場づくり」へ
あなたの会社では、今年の戦略会議を昨年と同じフォーマットで進めていませんか?
それは、モノづくりやコトづくりが中心だった時代に最適化されたやり方です。かつては通用していたとしても、いまの時代には対応しきれません。
いま、世界では「モノ」や「コト」ではなく、「場」をつくる企業が勝ち始めています。
製品をつくる時代(モノづくり)から、体験をつくる時代(コトづくり)へ。そしていまは、誰とどんな関係をつくるかを設計する「場づくり」の時代へと突入しています。
場をどうデザインするかが、競争力を決める
場づくりとは、人や企業が共に価値を生み出せる舞台を設計することです。
たとえば、精密機械部品のECサイトを運営するミスミは、そこにとどまらない戦略を展開しており、全国に点在する小規模加工工場と企業ユーザをオンラインでつなぐ仕組みとして、加工部品の調達を効率化するサービス「meviyマーケットプレイス」を構築しました。
このようなプラットフォームがあることで、顧客と供給者の双方が新たなビジネス機会を得る「場」が生まれています。
いまや戦略は、モノやコトを超えて「関係性のデザイン」に踏み込めるかどうかが問われています。
戦略は、環境の変化に応じて形を変える「動的なもの」
本来、戦略とは静的な設計図ではなく、環境の変化に応じて形を変えていく動的なものです。
経営者は、日々変化する外部環境からさまざまなインプットを受け取りながら、自社にとっての意味を考え、戦略を絶えず練り直すことが求められます。
では、場づくりの時代における戦略とは何なのでしょうか?
それは、環境に応じて視点を変え、価値を再定義し、仕組みを進化させる「動的な営み」です。
あなたの会社は、変化に合わせて戦略、そして場をデザインできているでしょうか?
『戦略のデザイン』では、こうした時代の変遷を整理しながら、場づくりの時代における戦略の立て方について、10のレッスンを通じて体系的に解説しています。
日々の変化の兆しを見極め、これからの時代に合った新しい戦略を学びたい方に最適です。
IGPIグループ共同経営者、IGPIシンガポール取締役CEO、JBIC IG Partners取締役。早稲田大学政治経済学部卒、IEビジネススクール経営学修士(MBA)。ITストラテジスト。
大学卒業後、キャップジェミニ・アーンスト・アンド・ヤング(現フォーティエンスコンサルティング)に入社。日本コカ・コーラを経て、創業期のリヴァンプ入社。アパレル企業、ファストフードチェーン、システム会社などへのハンズオン支援(事業計画立案・実行、M&A、資金調達など)に従事。
その後、支援先のシステム会社にリヴァンプから転籍して代表取締役に就任。
退任後、経営共創基盤(IGPI)に入社。2013年にIGPIシンガポールを立ち上げるためシンガポールに拠点を移す。現在は3拠点、8国籍のチームで日本企業や現地企業、政府機関向けのプロジェクトに従事。
単著に『戦略のデザイン ゼロから「勝ち筋」を導き出す10の問い』『超速で成果を出す アジャイル仕事術』、共著に『構想力が劇的に高まる アーキテクト思考』(共にダイヤモンド社)がある。