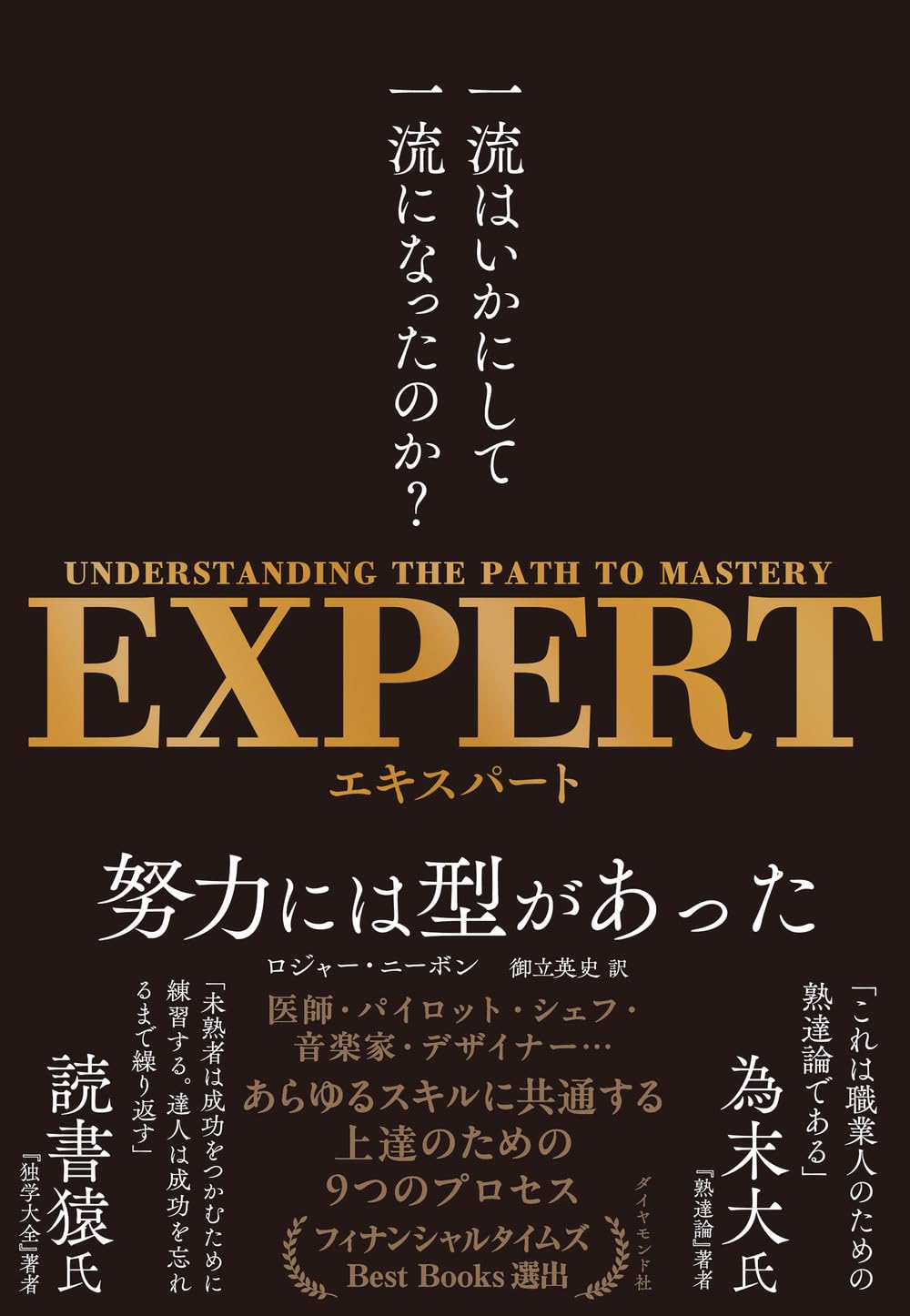『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』(ロジャー・ニーボン著/御立英史訳、ダイヤモンド社)は、あらゆる分野で「一流」へと至るプロセスを体系的に描き出した一冊です。どんな分野であれ、とある9つのプロセスをたどることで、誰だって一流になれる――医者やパイロット、外科医など30名を超える一流への取材・調査を重ねて、その普遍的な過程を明らかにしています。今回は「ずば抜けて仕事ができる人」の肌感覚について『EXPERT』の内容を元にお届けします。(構成/ダイヤモンド社・森遥香)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
「ずば抜けて仕事ができる人」の肌感覚
「この人、なぜここまで仕事が早くて正確なんだろう」
そう感じさせる人は、論理やスキルだけでは説明できない“肌感覚”を持っています。一見曖昧に思えるこの感覚は、実は人間が本来持ち合わせる感覚器そのものの特性から理解できます。
私たちが頼りにしている視覚や聴覚は、一方通行でも成立する感覚です。こちらが相手を見ていても、相手はこちらを見ていないかもしれない。こちらが声を聞いていても、相手はこちらの声を聞いているとは限らない。観察しているだけで情報が得られてしまう、いわば“距離のある関わり方”です。
一方で、触覚に目を向けると、状況は一変します。
医療の現場では、触覚のこうした特性が特にはっきりと現れる。意識のある患者を診察するとき、患者は必ず医師に触れられていることを認識する。それを意識させずに診察することはできない。これは医師にかぎらず、人と関わる仕事全般に当てはまる。相手から情報を受け取るとき、自覚していなくても、自分も相手に何らかの情報を発信している。駆け出しの美容師だったころのファブリスも、客の髪を洗いながら、自分自身に関する何らかの情報を客に伝えていたのである。
『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』より
触れた瞬間に必ず“反応が返ってくる”。この相互性が、触覚の最大の特徴です。そしてその原理は、医師や美容師だけでなく、ビジネスにおけるあらゆる人間関係にそのまま当てはまっています。人と向き合う瞬間には、必ずこちらの情報が相手に渡り、相手の反応がこちらに返ってきます。
ずば抜けて仕事ができる人は、この“反応の往復”を、視覚や聴覚よりもはるかに敏感に捉えています。
会議で相手の表情が曇った瞬間、沈黙の質が変わった瞬間、声の奥に迷いが混じった瞬間など、言葉になる前の変化を身体で感じ取り、自分の働きかけを微調整しているのです。
彼らが「場の空気を読める」「相手の次の動きを予測できる」と言われるのは、この触覚的な双方向性を当たり前の前提として扱っているからです。こちらが一言発すれば、相手の姿勢や視線がどう動いたか。こちらが一歩踏み込めば、相手がどう下がるのか。それらを“肌”で感じているのです。
この感覚は先天的な才能というより、経験を重ねるうちに自然と磨かれていく能力です。反応を受け取り、働きかけを調整する。その微細な往復を続けた人ほど、触覚的な感度は高まっていきます。
言語化されない直感が働くとき、身体はすでに相手の反応を受け取っています。ずば抜けて仕事ができる人とは、言葉より早く、反応の“揺れ”を感じ取れる人なのです。
(本記事は、ロジャー・ニーボン著『EXPERT 一流はいかにして一流になったのか?』を元にした記事です。)