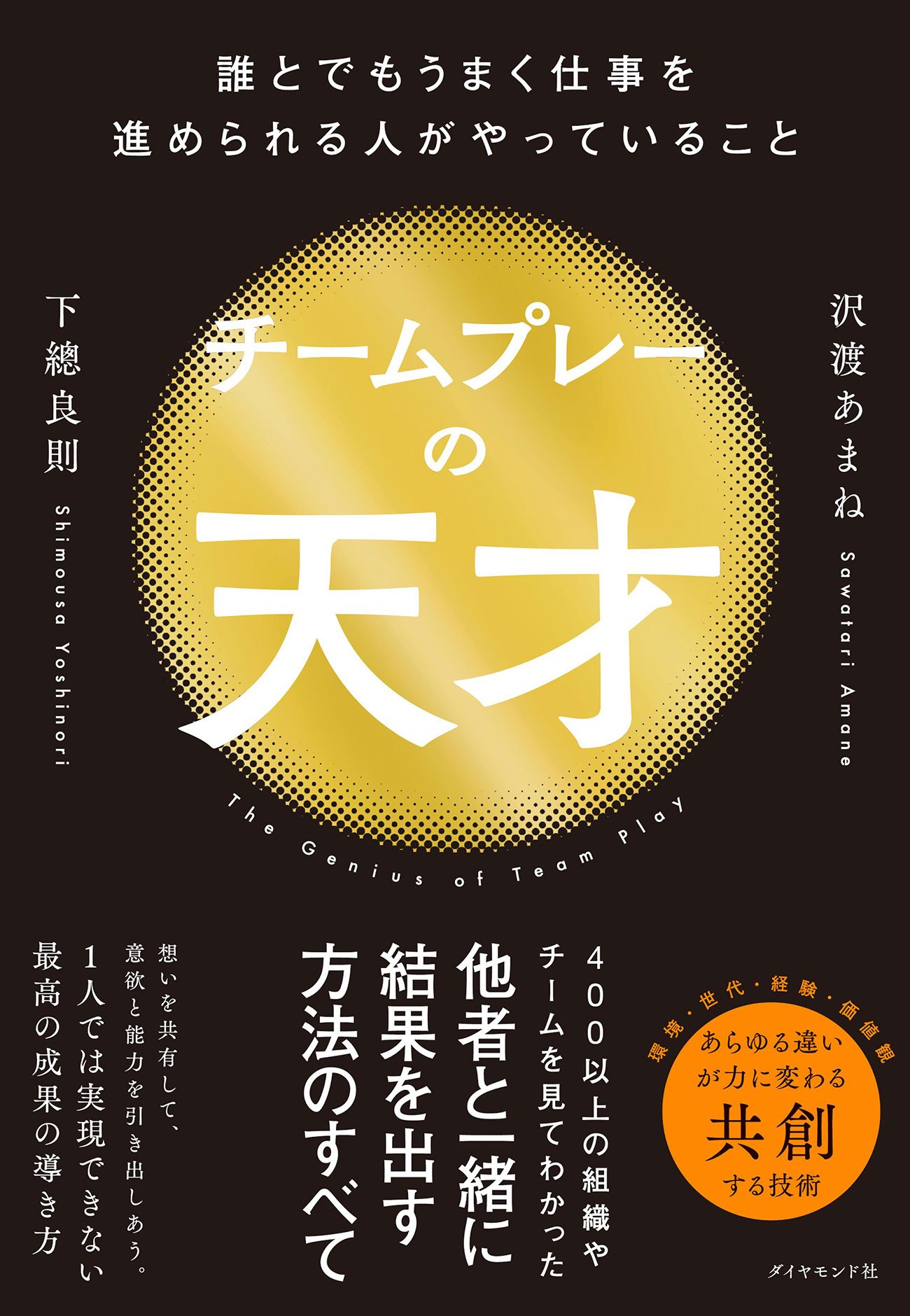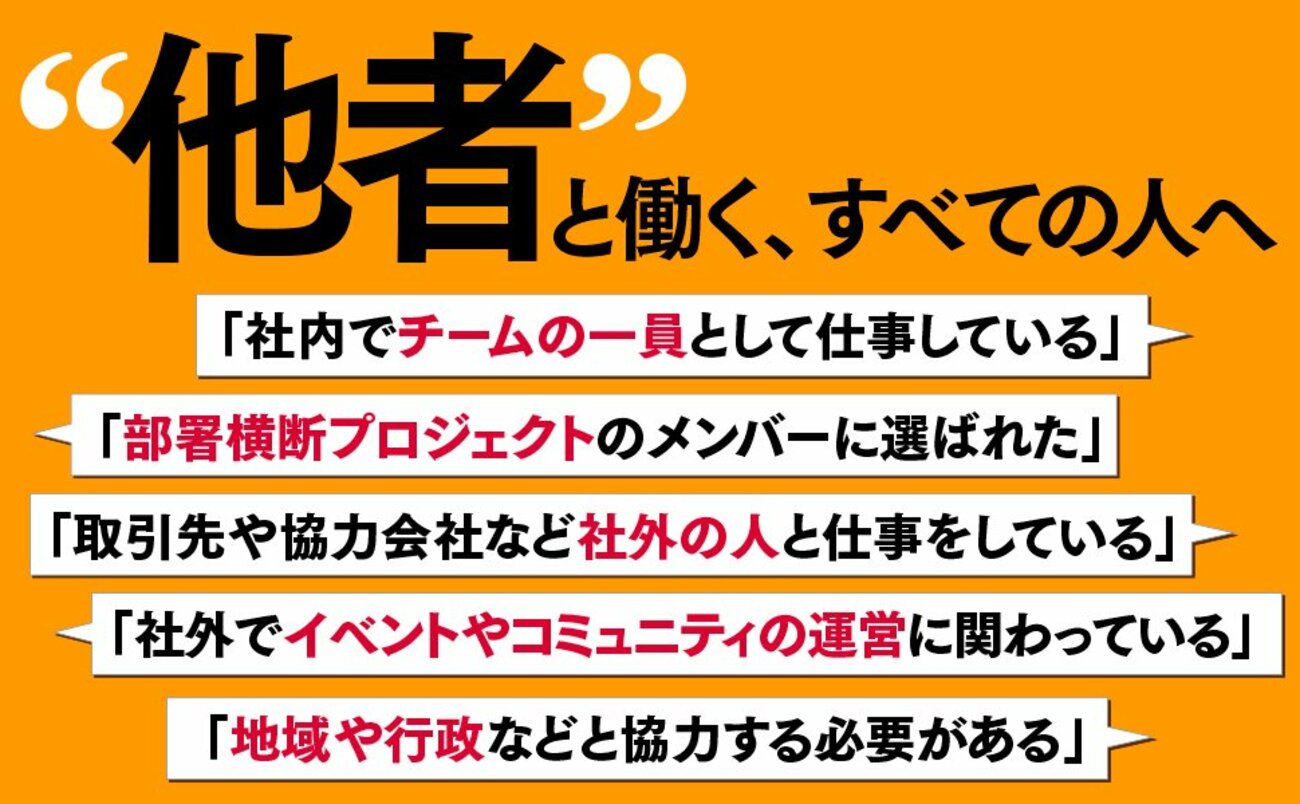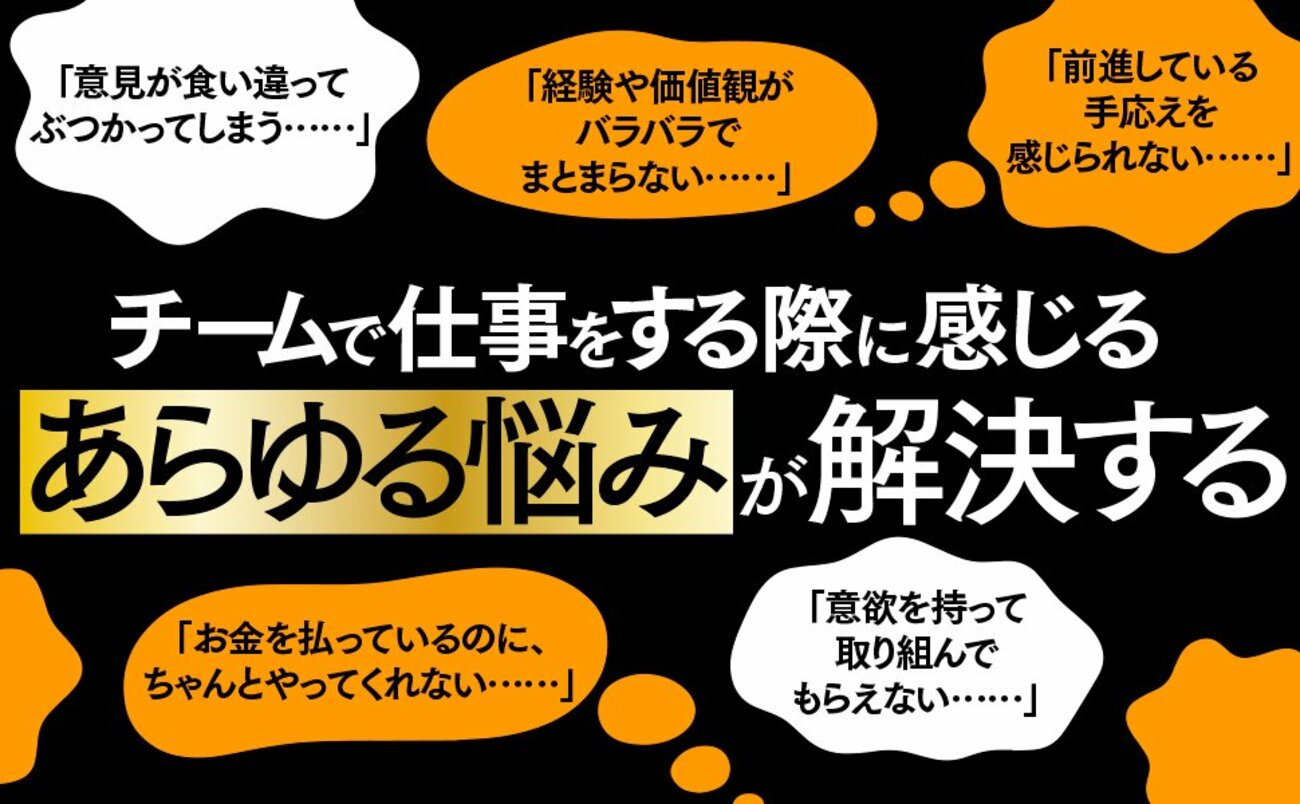「チームをうんざりさせるリーダー」と「好かれるリーダー」には、“決定的な違い”があります。じつは、「良かれと思ってやっていること」が、チームのメンバーを疲弊させ、やる気を奪っているのです。では、その行為とは? それを指摘してくれるのが、400以上のチームを見た専門家が「仲間と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』(沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊)だ。「あらゆる仕事仲間との関係性が良くなる」と話題の一冊から、その内容を紹介しよう。(構成/ダイヤモンド社・石井一穂)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
リーダーが「気をつけたい」こと
チームのみんなで同じ体験をし、それを振り返る。これによってチームに一体感が出ます。
その振り返りにおいては「未来を語る」ことが大切だとお伝えしましたが、その未来を無理やり手繰り寄せようとするのは禁物です。
体験で得た学びや気づきをすぐに活かそう(または活かさせよう)と躍起にならない、焦らない。
「効果」が出るのを焦ってはいけない
その体験はいま直面している課題の解決や、目先の仕事の成果を出すためにすぐには役立たないかもしれません。
もしかしたら永遠に日の目を見ないかもしれない。
ですが、新しい体験や人との出会いの意味はかなり後になってわかることも往々にしてあります。
「3年前に社外で受けた研修で得た知識が、いまの仕事で役に立った」
「5年前に地域コミュニティでたまたま会話した他社の人を思い出して、いまのプロジェクト活動で仕事をお願いすることに」
「2年前に雑談した他部署の課長が、水処理技術を学んでいると言っていた。顧客から水処理に詳しい人がいないかと相談を受けたので、その課長に協力してもらおうと考えた」
多かれ少なかれ、このような体験をしたことがあるのではないでしょうか。
にもかかわらず、体験をいまの仕事や組織にすぐ活かそうとして焦ると、無理や軋轢が生じます。
「すぐには役に立たない学び」も受け入れよう
また、「体験からは必ず学びを得て、すぐに活かさなければならない」とする同調圧力的な空気は、メンバーが新たな体験を試す際の心のハードルを上げることがあります。
仮に「社外研修に参加したら必ず論文を提出する」なるルールがあったとしたら、どれだけの人が気持ちよく研修参加の手を挙げられるでしょうか。
体験による学びを何が何でもすぐに活かさせようとする文化は、体験恐怖症、体験拒否症候群を組織にもたらしかねないのです。
体験に即効性を求めない姿勢、すなわちネガティブ・ケイパビリティをもって、じっくり体験の意味を見いだしていきましょう。
(本稿は、他者との仕事を円滑にするコツをまとめた書籍『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です)