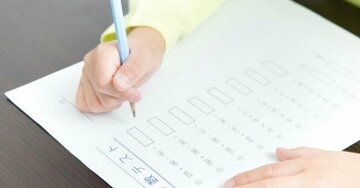写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
SAPIXの広野雅明先生に「中学受験の素朴な疑問」をぶつける連載。全5回にわたって「第2志望の選び方」を取り上げます。第2回は偏差値や評判だけで選んでしまう親子が陥る、意外な落とし穴をSAPIX広報の広野雅明先生に解説してもらいます。(聞き手・文/教育アドバイザー 鳥居りんこ)
SAPIX講師が思わず“待った!”
心配になる志望校の選び方
――前回は近年、地理的にも受験回数的にも受験可能な学校が増えているために、併願校選びは逆に難しくなっているというお話でした。しかし、本命校1校だけではリスクが高過ぎるので併願校はいくつか用意しておきたいのが保護者の本音かと思います。どのように決めていけばいいのでしょうか?
確かに第1志望校に合格する子どもは数人にひとり。倍率が2倍だとしても約半数の子どもは第2以下の志望校に回るわけですから、第2志望校、第3志望校の選択がとても大事になってきます。
まずは自宅から学校までの距離で候補を出してください。第1志望校の場合ですと思い入れが強い分、多少長い通学時間でも魅力が上回り受験する人が多くいます。一方で、2番手校以降の選択では通学範囲がやや狭くなるという傾向はあります。中学受験において通学距離は志望校選びの重要な要素の1つ。お子さんが6年間無理なく通えるかを考慮し、慎重に検討することが大切です。
地図アプリで経路検索することで、おおよその所要時間を把握できますし、通学時間から学校を検索できる機能がある中学受験専門の学校検索サイトなどを利用するのもひとつの手です。候補校となった学校には必ず、平日の朝夕のラッシュ時に通学経路を実際に確認してみてください。
交通手段を考慮した場合、乗り換えは2回までが限界という説もありますし、中高一貫校に通う生徒の片道の通学時間の平均は、60分前後と言われています。
また、桜蔭中学校や女子学院中学校のように通学時間を90分未満とするエリア居住地制限を設けている学校もありますので注意が必要です。早朝や放課後の活動が多く、学校行事が盛んな学校では、通学に時間がかかると生徒の負担が大きすぎるという判断がなされているのです。