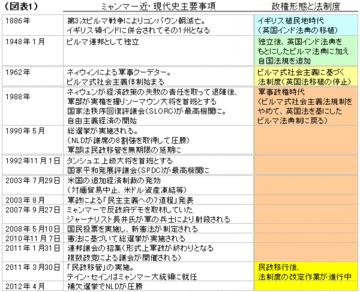前回、ミャンマーにおける医療の現況について、近隣諸国との比較の観点からご紹介した。一方で、ミャンマーにおける医療の現状は、数値的な尺度から見えない点も多々ある。特に実際に現地で医療活動を行う際には、どのような困難があるのか。また日本などの医療先進国から見て、そもそも何が問題なのかは、実際にそこに従事した方にしか見えてこない。
今回は、日本人医師として現地でのサポートに長年従事しているNPO法人ミャンマーファミリー・クリニックと菜園の会代表の名知仁子氏に、ミャンマーにおける医療制度の実態と、そこで長年活動してきた現場ならではの視点からの話を伺った。
サイクロン「ナルギス」では
現地政府の監視がついた
名知氏は、1988年に獨協医科大学を卒業後、日本医科大学第一内科医局に入局し医師として活躍されていたが、1999年にマザーテレサに感銘を受け国際医療を志し退職。2002年に国際緊急医療支援団体の一員となり、それ以降、国際医療支援に取り組んできた。
ミャンマーについては、2002年にタイ、ミャンマーの国境沿いでカレン族に対する医療支援を実施し、その後、少数民族紛争で取り上げられるロヒンギャ人に対する医療支援をラカイン州で行ったり、ミャンマーデルタ地帯でのサイクロン被害に対する緊急人道援助にもかかわってきた。
特にこの時代は、まだ軍事政権が海外NGOの活動に対して厳しく監視していた時期で、なかなか情報が取り上げられないなかで、地道に草の根の医療活動を他の団体と一緒に展開してきた。
当時を振り返って、最も厳しい情報統制が敷かれていたのは、2008年に大型のサイクロン「ナルギス」により甚大な災害がもたらされた時だという。その時は、必ず毎日現地の政府関係者に対し、活動の内容を報告する義務があった。