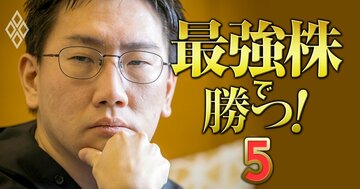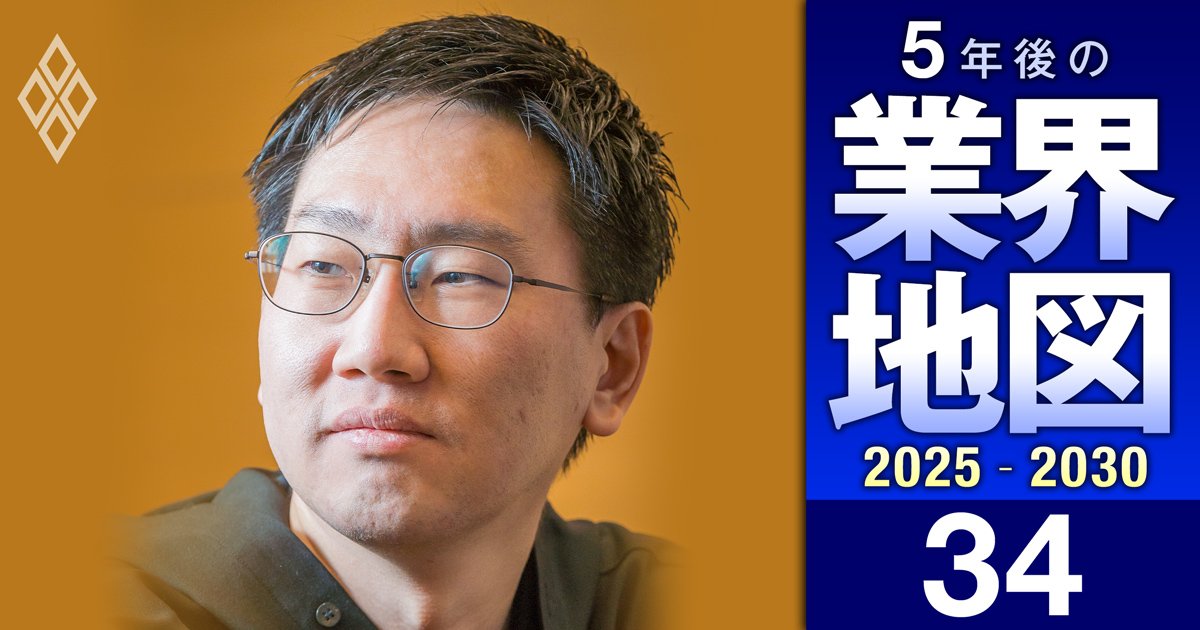 Photo by Masato Kato
Photo by Masato Kato
なぜ多くの個人投資家は中長期投資で大きな利益を獲得できないのか。特集『5年後の業界地図2025-2030 序列・年収・就職・株価…』の#34では、住信SBIネット銀行がNTTドコモにTOB(株式公開買い付け)されたことで70億円以上の利益を確定した片山晃氏に「中長期投資の極意」と「落とし穴」について聞いた。片山氏は中長期投資で大きな果実を得るには「ノイズを気にしない覚悟」と「耐える」ことが必要と指摘するが、その真意とは?資産250億円を築いた片山氏が中長期で有望とみているセクターや、狙うべき銘柄の条件についても具体的に明かしたロングインタビューをお届けする。(構成・聞き手/ダイヤモンド編集部 篭島裕亮)
住信SBIネット銀行へのTOBで
70億円以上の利益を確定
――NTTドコモによる住信SBIネット銀行のTOB(株式公開買い付け)により、1銘柄で70億円以上の利益を確定して話題になりました。ダイヤモンド・オンラインでの過去のインタビュー(2023年7月17日、24年9月12日、25年3月11日)においても、住信SBIネット銀行などネット銀行の将来性を高く評価していました。中長期投資の見本のような取引だと思いますが、あらためて振り返っていただけますか。
住信SBIネット銀行は、ほぼ初値(初値1222円。公開価格は1200円)で200万株程度買いました。途中、多少売買しましたが、200万株程度は継続して保有していました。
NTTドコモによるTOB価格が4900円だったので、利益確定額は70億円程度です。現在の総資産額は250億円程度です。
住信SBIの場合、買いの根拠は大きく二つありました。業績の成長期待と株価の割安感です。
インターネットバンキングで済ませるケースが主流になりつつあるなか、決済、預金、貸し出しなどの銀行機能をパートナー企業に提供するBaaS(バンキング・アズ・ア・サービス)のように、ネット銀行ならではの収益性の高い新しいビジネスモデルもある。仮にマクロ景気がどうなろうと構造的に伸びていくのは間違いないと思っていました。
株価の割安感という意味では、住信SBIが上場したとき、米シリコンバレーバンク(SVB)の問題で銀行セクターの株価が調整していました。将来性と割安感、二つの要素があったので自信を持って大きく買うことができました。
――とはいえ、保有期間中は株価が横ばい推移の時期もありましたし、トランプ関税による全体相場の暴落もありました。途中で売却して利益確定をしたくなりませんでしたか?
他の銀行と同様、どこの証券会社のレポートを見ても、PBR(株価純資産倍率)の何倍かで住信SBIの目標株価は付いていました。支店からネットへというビッグチェンジが始まったばかりなのに、これまでの銀行と同じ尺度で評価すべきなのかどうか。
また、当時の住信SBIは地方銀行大手と比較して時価総額が3分の1程度でしたが、全国をカバーして今から伸びていく住信SBIの方が評価されていないのはおかしい。世間の認識の変化が起こるなら、チャンスは大きいのではないかと思っていました。
 かたやま・あきら/1982年生まれ。2005年に65万円で株式投資を始め、17年には資産140億円に到達。その後はヘッジファンド運営、事業投資、スタートアップ投資に活動の幅を広げ、近年は自己資金の運用に加えてディーリング事業を立ち上げ、後進の育成も積極的に行っている。現在の総資産は約250億円。 Photo by M.K.
かたやま・あきら/1982年生まれ。2005年に65万円で株式投資を始め、17年には資産140億円に到達。その後はヘッジファンド運営、事業投資、スタートアップ投資に活動の幅を広げ、近年は自己資金の運用に加えてディーリング事業を立ち上げ、後進の育成も積極的に行っている。現在の総資産は約250億円。 Photo by M.K.
――24年8月や25年4月などの暴落時は一時的にポジションを軽くしたと述べていました。そのときも住信SBIは売却しなかった?
昨年の8月の暴落時は、むしろ買い増しをしました。数年先のあるべき株価評価に対してのギャップが大きければ、いつ上がるのかはいったん無視して買い増しをします。
――大きな利益を獲得するには「銘柄選び」と「売買タイミング」という二つの要素が必要です。個人投資家の場合、銘柄を当てることができても、大きな利益を獲得できない人が多い印象です。何が問題なのでしょうか。
いい銘柄を買えているのに、どうして長期で持ち続けられないのかという話ですよね。その理由は明白です。中長期で持つべき銘柄とその瞬間に上がっている株は、一致しないことが多いからです。
次ページでは、片山氏が中長期投資で大きく勝つために重要だと指摘する「ノイズを気にしない覚悟」や「テクニカルルールの活用」「個社要因の分析術」などを解説。今後は取材で個別銘柄に触れるのは控えるという片山氏だが、「そこをなんとか」と粘り、可能な範囲で有望セクターや具体的な注目銘柄についても触れてもらった。