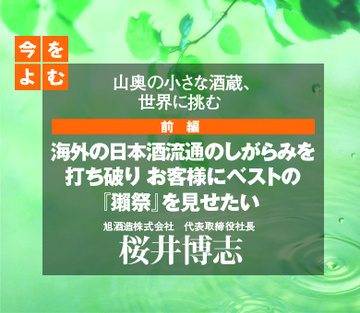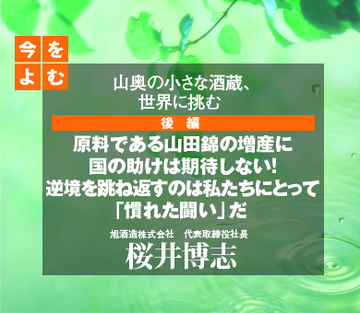父の急逝で急遽、酒蔵の三代目を継ぐことになった、旭酒造の桜井博志会長。日本酒市場の縮小に先駆けて、業績が悪化していくなか、「もし自分が自殺すれば…」と死亡保険金を借金返済のあてにしてしまうほど追いつめられていきます。最初に打った手とはどのようなものだったのでしょうか。その後、「獺祭」の大ヒットで急成長して2023年には米国製造に乗り出すのですが、成功の足掛かりをつかむまでのお話を、桜井会長の著書『逆境経営』から振り返ります。(初出:2014年1月14日)

「この子たちが大学を出るまで、うちの酒蔵はもつだろうか…」
約40年前、9才と7才だったふたりの子どもの寝顔をみては、将来が恐ろしく、眠れない日が来る日も来る日も続きました。
1984(昭和59)年4月、急逝した父の跡を継いで、私が家業である旭酒造の三代目社長に就いたころのことです。旭酒造は、山口県周東町(現岩国市)獺越(おそごえ)という山奥で、江戸時代にあたる1770(明和7)年の昔から酒造りを続けてきた小さな酒蔵で、私が今も社長を務めています。
実は、私は社長就任の直前まで、勘当状態でした。
ある日突然、勘当息子が三代目に――。自分も含めて、誰もが想像だにしなかった出来事です。
長男として生まれた私は、大学卒業後に希望して大手である西宮酒造(現日本盛)で修業し、いったんは1976(昭和51)年に旭酒造に入社したのです。しかし、酒造りの方向性や経営をめぐって父とは意見が合わず、ついにはクビになりました。
その後、私は79(昭和54)年に櫻井商事という石材卸業の会社を興して、そちらに集中していました。年商2億円を稼ぐまでに育てたところで、父が亡くなったため、取るものも取りあえず酒造りに戻ったのでした。
もともと好きだった酒蔵を継ぐことに、特別の感慨があったことは確かです。
しかし、そんな感傷も吹き飛ぶような、惨憺たる現実が待ち受けていました。
当時の清酒業界には、第1次焼酎ブームという逆風が吹き荒れていました。
酒好きの方はご存じかもしれませんが、日本酒は1升瓶100本で1石と計算します。日本酒業界自体が、第1次オイルショックの年の最高980万石をピークに、現在は340万石まで縮小しています。
業界がそうして縮小の一途をたどった間に、旭酒造の業績はそれを上回るスピードで悪化していました。最盛期だった1973(昭和48)年の約2000石から、私が引き継いだ当時は3分の1の700石まで落ち込んで、年商は前年比85%という厳しい状態。所轄の税務署の担当官や、知り合いの会計士から、「あがけばあがくほど沈む泥沼」「ロング倒産状態」と揶揄される有り様でした。
最初に手をつけたのは、当時の看板商品だった本醸造1級酒<旭富士>です。
まず思いついたのは、灘・伏見の大手メーカーが出し始めたばかりの紙パック詰め日本酒(1800ml)でした。調べてみると、私たちのようにつぶれかけの酒蔵でもなんとか手が出せそうな充填機も見つかりました。
通常の瓶詰め製品に比べて、1本当たり約6倍もの人員が必要でした。それでも当時は、社員から毎日のように「売れないから仕事がない。今日は何をしましょう」と文句を言われるほど人が余っていたので問題ありませんでした。
人海戦術によるヒットの行く末は…
実際に生産を開始してみると、これが大ヒットしたのです!
「うちの新製品なんて売れるわけない」と弱気になっていた営業担当者たちも、酒蔵から営業活動に出る時点で紙パックしかトラックに積まずに、午前中にはトラック1台分の積荷をすべて売ってしまう大戦果でした。いつもは気弱そうに下を向いて皮肉しか言わない営業担当も、なんとなく自信を持って胸を張っているように見えました。
この大ヒットに気をよくした私は、ワンカップならぬ紙カップ(180ml)も作りたい、と目論見ました。
ただ、紙カップは1800ml詰めのような安い充填機がありません。当時の私たちに、1000万円以上もする高価な機械を購入する余裕はありませんでした。
ところが、よく調べてみると、紙カップというのはカップの内面に樹脂が塗られて、そこへアルミのフタをのせて熱を当てると蒸着される構造でした。
「そうや、アイロンや! アイロンでつけたらいいんや! 機械なんかいらん!!」
1000万円の機械の代わりに、数台購入したアイロンと、暇を嘆いていた瓶詰め担当の女性たちが活躍してくれました。こうして紙カップに充填できるようになり、一時は1800ml紙パックと180ml紙カップで、旭酒造の全出荷量の2割を占める勢いでした。
しかし、これら紙製品は、しばらく後にやめざるを得なくなりました。
売り上げ増に貢献しているかに見えたのも、まやかしだとわかったからです。
まず、充填時にあまりに人手がかかるのに耐えられなくなりました。さらには、普通酒そのものが価格競争のなかでまったく売れなくなりました。
紙製品を扱っていた取引先に、商品の打ち切りをお詫びに行くと、「うちがせっかく売ってやっているのに、やめるとはなんだ!」と怒られました。しかし、「企業の身を削って」ときれいごとを言ったところで、つまるところ、費用をお客様にご負担いただけなければ倒産します。
しかも、あれだけ「酒が売れないから仕事がない」と嘆いていた古参の瓶詰め部門の社員たちが、実際に忙しくなると、みな辞めてしまいました。
結局、減り続けている地方の普通酒市場を相手に商売を続けている限り、小手先の工夫をしたところで、焼け石に水。なんの解決にもならない。そう思い知らされた出来事でした。
抜本的な過一句の必要性を痛感し、この後、純米大吟醸造りに邁進することになります。