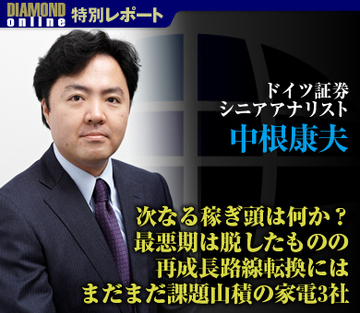ソニーを飛び出し、事業を興す“ヤメソニー”たち。彼らの共通点は、ものづくりに徹底的にこだわり、おもしろいものを生み出そうとするソニーDNAを体現しようと挑戦しているところだ。本連載ではそんな“ヤメソニー”たちを取り上げる。第1回は「ソニー最後の異端児」と呼ばれ、400以上の特許をもつソニーの名物技術者だった近藤哲二郎氏。ソニーの「A3(エーキューブド)研究所」を母体に、I3(アイキューブド)研究所を立ち上げ、ソニー出身の技術者約30人で映像技術を研究する。(聞き手/ダイヤモンド・オンライン編集部 片田江康男)
腹ぺこの人にパンを売る
テレビ“第一幕”は終わっている
 こんどう・てつじろう
こんどう・てつじろう1949年、愛媛県生まれ。1973年慶應義塾大学工学部電気工学科卒。日本無線入社。80年ソニー入社。400件以上の特許を出願・登録する。「エーキューブド研究所」を率いて、映像の高画質化技術「DRC」を実用化。同技術を搭載した『WEGA』、『BRAVIA』は大ヒットを記録する。2009年にソニー退職。「アイキューブド研究所」を設立。 Photo by Naoyoshi Goto
――現在、具体的にどのような研究を行っているのか教えてください。
まず、今日本のテレビメーカーが直面している市場環境について整理しておきたい。すでにテレビ事業は、“第一幕”が終わっている。第一幕というのは一言で言うと「不便解消型」。つまり、お腹が空いている人を対象にパンを売るようなビジネスだ。
40本の走査線のテレビが作られ、初めて「イ」の字が映し出されてから、100本に増えて、今度はカタカナから漢字の「稲」が映せるようになった。こういう時代はみんなテレビを見たかったし、欲しかった。カラーになったときも同じ状況だった。だから、量販店にテレビを置いておけば、飛ぶように売れていった。
こういう“腹ぺこ時代”は、エレクトロニクス産業にとって良い時代だった。腹ぺこの人を、“お腹いっぱい”にしようとしていた時代。これはテレビだけじゃない。VTR(ビデオテープレコーダー)だってそうだ。はじめはたったの15分しか録画できなかったが、それが30分になって、野球が1試合録画できる2時間になった。録画したいというニーズがあった時代だった。