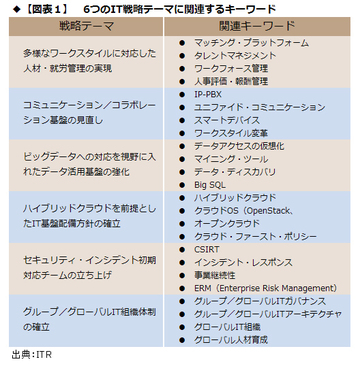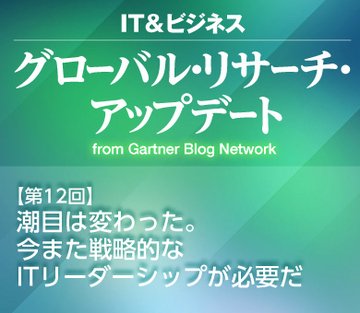アンドリュー・ラーナーガートナー リサーチディレクター
アンドリュー・ラーナーガートナー リサーチディレクター2014年5月12~16日にかけて、OpenStackのためのサミットが米ジョージア州アトランタ市で開催された。私は事前に同僚のリディア・リヨンが書いたリサーチ・レポートを読み直してOpenStackについて復習し、サミットで発表されるであろうネットワーク関連の最新情報に備えた。
企業内ネットワークを運用するネットワーク管理者たちの大半でさえ、その多くはOpenStackについて表面的なレベルの知識しか持ち合わせていない(要するに、彼らには管理すべき既存のネットワークがあるのだから)。私がクライアントとやり取りをする際にも、OpenStackに関するごく基本的な質問やコメントが数多く挙がる。たとえば次のようなものだ。
・OpenStackとは、一体何なのか?
・サーバーや仮想化環境の管理者はチェックしていると思うが、まだ運用には至っていない。
・ネットワークアーキテクチャのチームがよく話題にしているが、稼働するまでには至っていない。
・OpenStackとはVMwareのフリーウェア版(簡易版)か? それともVMwareのLinux版か?
さらに付け加えると、近頃は大半のネットワークベンダーのスライドやマーケティング資料で、OpenStackがさまざまな形で登場する(例:プラグイン、APIs、統合など。何たることだ!)。