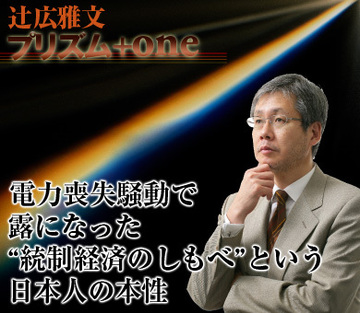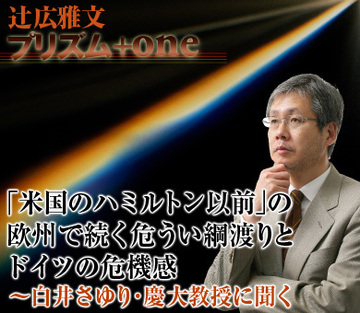稲盛和夫・京セラ名誉顧問が日本航空CEO就任を受諾した。その報を受けて、3人の財界人が披瀝してくれたエピソードが、それぞれに興味深い。
30年ほど前の1976年、大蔵省事務次官を経て、高木文雄氏が第八代国鉄総裁に就任した。彼は、赤字解消に向けて人員削減に手をつけたものの不十分であり、一方で運賃値上げを毎年のように行い、客離れを招いて赤字体質を悪化させ、経営の非効率性に集中砲火を浴び、在任7年で辞任した。
高木総裁誕生のきっかけは、前任者が国鉄労組が「スト権スト」を強行した責任を問われたことだった。「スト権スト」の決行は、実は当時の経営陣の内諾ゆえであった。国鉄の赤字体質の根には、国労、動労という労組の強大な権力とそれを制御できない経営側の脆弱、言い換えれば労使の馴れ合いがあった。労組の統率力、影響力は国鉄全国の労働現場だけでなく、他の公労協に及び、政界にも根を張り、社会の表側だけでなく、ダークサイドをも網羅していた。
日頃は強圧的、闘争的側面は影を潜め、それどころか友好的であり物分りがよい。しかし、事の裏側では常にしたたかで、ときに陰惨な仕掛けをするのを躊躇しない労組の暗い体質を十分に警戒しなければならないはずだった――。
こうした時代背景を説明してから、財界人はこう続けた。
「だが、高木さんは総裁就任後、何度も『みな、労組を誤解しているか、色眼鏡で見すぎている。私の言い分を実によく聞いてくれ、理解してくれる』と言っていた。甘すぎる、と忠告したのだが、聞いてもらえなかった。落とし穴にはまるのが、眼に見えた。辞任やむなしとなった頃、高木さんは酒を飲みながら、こう呟いたものだ。『組合の本当の体質を、誰も教えてくれなかった。本当に、ひどい』、と」
国鉄から日本郵政に、舞台を移そう。もう一人の財界人は、これによく似た逸話を思い出してくれた。彼は首脳として、ある公社の経営を経験している。
小泉純一郎総理(当時)から郵政改革を託され、日本郵政公社総裁に就任した生田正治氏は、コーポレートガバナンスに関する論客であり、効率的な郵政公社経営を実現すべく、改革を進めた。ここでも難関は、全逓と全郵政という二大労組であった。生田総裁は臆することなく、しかし慎重に組合に対峙した。それがうまくいっているという自負があったのだろう、本人は労組との“信頼関係”を時々に強調した。