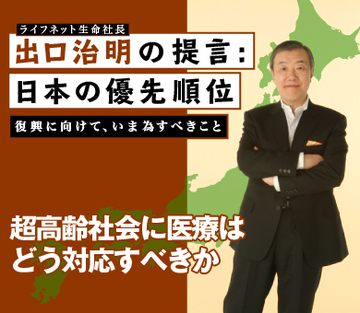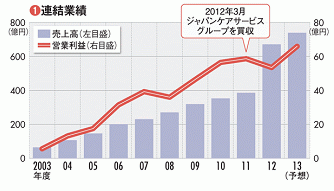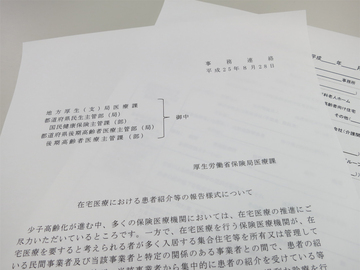連載第1回では日本の医療・介護制度が大転換期を迎えていること、具体的には医療の役割を「治す医療」から「支える医療」に、「病院完結型」から「地域完結型」へ、「医療から介護」へ、「病院・施設から地域・在宅」への転換を目指し、それを実現するためには、「地域包括ケアシステム」の構築が欠かせないということを述べた。
そこでこれから数回にわたり、入院、外来医療、そして在宅医療の3種類の変化を順番に分け入って論じたい。まず今回は入院医療の変化について説明していく。
診療報酬を動かすことで
医療機関の方向を誘導
日本の医療制度の見直しは、事実上、2年に1度の診療報酬改定によってなされる。診療報酬とは病院や診療所など医療機関に医療保険の団体から支払われる料金で、厚労省が決めている。したがって、より高い報酬が設定される分野に力を入れるように医療機関は動くので、医療の仕組みはこの報酬体系で変わっていく。
日本の医療提供者は公立の医療施設がわずか14%、病床数で22%と少ない。欧州では公立施設が大半なので政府が改革を強制できる。一方、日本では独立の医療法人が多く、国が制度改革を試みても、なかなか進展しない。そこで、「ニンジンをぶら下げて馬を走らせるように」、診療報酬を上下させることで誘導してきた経緯がある。
今回の診療報酬改定も同様だが、新たな要素が加わった。昨年8月に首相に提出された社会保障制度改革国民会議(慶應義塾長・清家篤議長)の報告書である。団塊世代が75歳以上になり医療・介護の需要が増える2025年を見据えて、それまでになすべき改革プランを示したのだ。
このため4月の診療報酬改定は、近来になく相当に思い切った内容になっている。いわば、報告書のお墨付きを得て、日本医師会など関連団体の雑音や抵抗を突破できたと言えるだろう。