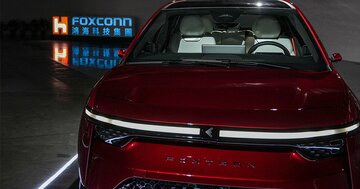9月17日、国土交通省が発表した今年7月1日時点の基準地価は、全国平均で前年同月比4.4%の下落となった。商業地は2年連続、住宅地はバブル崩壊後の1992年から18年連続の下落となり、地価の下落に歯止めがかかっていないことがわかる。
最近の地価動向の特徴は、昨年まで上昇していた東京や大阪、名古屋などの地価が2005年以来3年ぶりに下落するなど、大都市圏、特に商業地での地価下落が顕著になったことだ。それは、東京の中心である丸の内で、地価が15%程度下落したことからも明白だ。
この背景には、90年代初頭のバブル崩壊の影響に加えて、昨年のリーマンショック以降の世界的な不動産価格の下落の影響が、わが国にも波及していることがある。
海外の投資ファンドなどの資金がわが国の不動産市場から流失し、国内の金融機関の不動産向け融資が厳しくなっているため、不動産市場に滞留する「流動性=お金」がかなり低下している。
それが、中小ディベロッパーの資金繰りを悪化させ、不動産市場の取り引き件数を大きく減らしている。不動産売買の件数が減少していること自体も、地価下落に拍車をかける要因の1つになっている。
しかしここに来て、不動産市場の一部には“底入れ”に向けた明るさも見え始めてている。下落幅の大きかった東京の中心部では、大手生命保険会社がAIGビルを約1000億円で取得するなどのケースが出てきた。“値ころ感”が出ているオフィスビルについては、それなりの需要が出ている証拠だろう。
また、住宅地でも、大手ディベロッパーがマンション用地の手当てに動き始めたり、一部の個人が住宅地の新規取得や、買い替え用の不動産の手当てに動き出している。不動産会社の担当者にヒアリングしても、「ここしばらく、取り引き件数が増え始めている」と指摘していた。
そこで気になるのが、足元の仄かな明るさが本物になり、不動産市場に本格的な“底入れ”がいつ訪れるかだ。先行きをどう分析すればよいのだろうか?
結論から言うと、この点については、専門家の間でも見方が分かれている。「景気の二番底が来て不動産市場がさらに冷え込むようだと、“底入れ”は一時的な現象になる」との指摘がある一方、「景気回復が続き、不動産市場が活況を呈するようになると、地価も徐々に上昇することが予想される」という強気の見方もある。
不動産価格の上昇には様々な要因があるが、突き詰めて考えると、今後の地価動向は「景気の動向次第」になると見るべきだだろう。