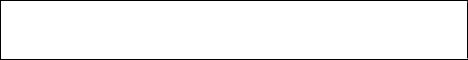新型インフルエンザ発生を機に始まった予防接種法改正の論議は、懲りずに弥縫策で終わる様相だ。
1990年代半ば以降、日本の予防接種政策は迷走し、制度は複雑化した。94年の予防接種法改正では、行政が接種を積極的に勧奨する法定接種が大幅に縮小された。2001年の見直しでは、65歳以上の季節性インフルを対象に法定接種“2類”(“1類”は旧来法にもあったポリオや百日咳などで、これらと比べ2類は接種の努力義務がなく補償額は半額程度)が新設され、天然痘など蔓延を防ぐため緊急性の高い「臨時接種」(接種の努力義務があり、補償額は1類と同額)と、全3枠になった。
今回の新型インフル発生時は、感染力が低いため「臨時接種」対象に当たらないと、努力義務がなく費用も自己負担、補償額は2類と同等の枠組みとして特別措置法が設置された。だが、国が責任と接種費用を負いたくなかったためとの見方もある。
昨年末に始まった厚生労働省の厚生科学審議会部会には、政策の抜本的な見直しが期待された。その“肝”は、法定接種の対象を拡大し、副作用が生じた場合の国・メーカー・医師の免責制度と、患者への補償制度の強化をセットで行うことだ。これらの条件が整ってこそ、大手メーカーがワクチン開発に乗り出し、外資メーカーから好条件も引き出せ、必要なワクチンを確保できる。
だが2月9日の第一次提言案を見る限り、抜本改革への機運は低い。肺炎球菌などニーズが急増する予防接種の法定化どころか、特措法と同じく努力義務を課さない新たな「臨時接種」枠を定める場当たりぶりだ。国民や患者不在の議論が続く。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 柴田むつみ)