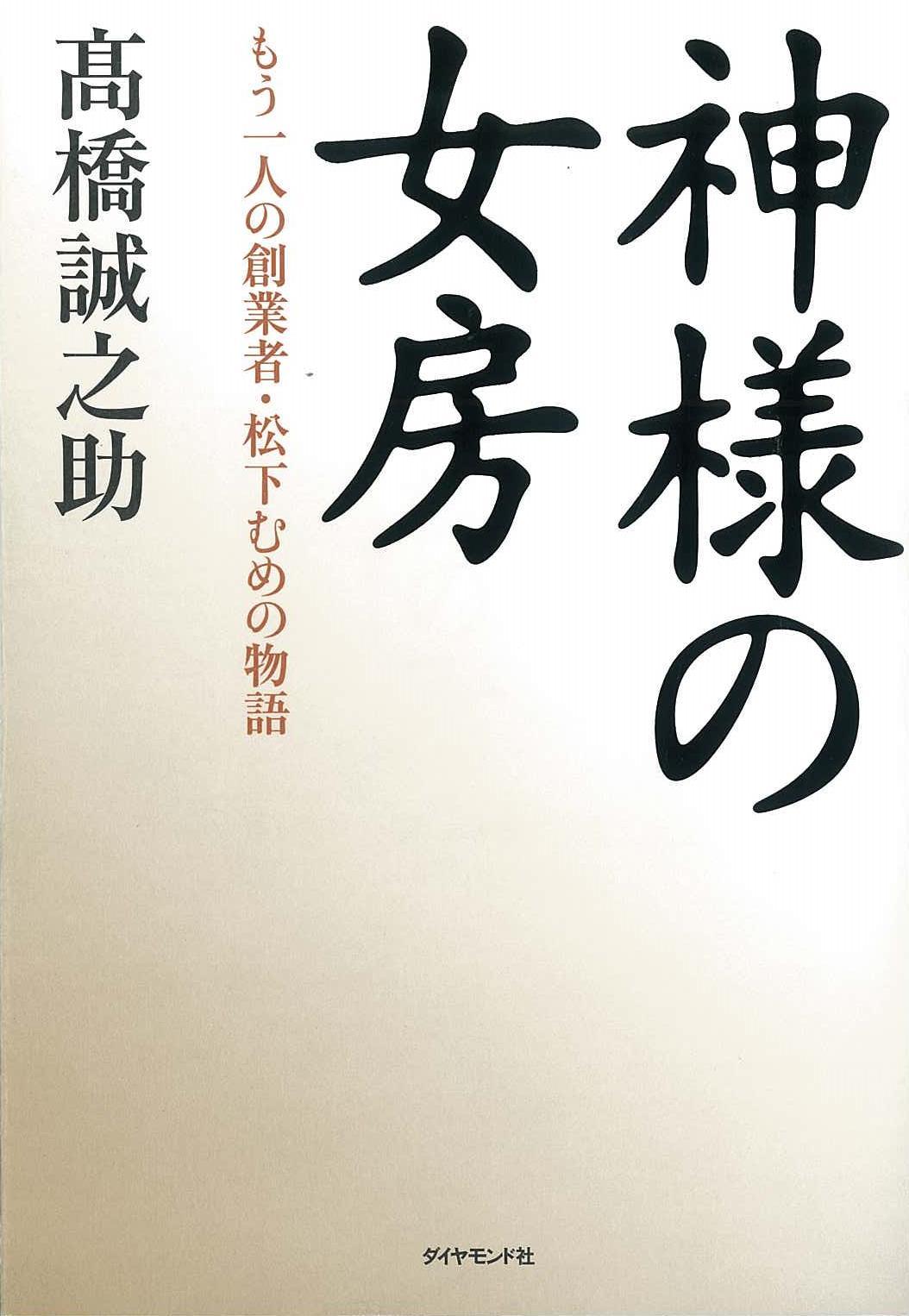「内助の功」では片づけられない
むめの夫人の献身
ここで少し横道にそれますが、今から20年ほど前、松下電器でトップ人事をめぐる人事抗争が勃発したそうです。谷井昭雄・4代目社長の時代でした。
今年4月に出版され、話題を集めている『ドキュメント パナソニック人事抗争史』の著者でノンフィクション作家の岩瀬達哉氏によると、この人事抗争の発端となったのは、皮肉なことに創業者・松下幸之助の“遺言”だったそうです。幸之助は当時、松下電器の会長職にあった娘婿・正治の経営能力を早くから見限っていて、なるべく早くに経営から手を引かせるよう“遺言”を残していたというのです。
やがて幸之助が他界したのち、谷井社長がその“遺言”を律儀に実行しようとした時、正治との間で壮絶な抗争が繰り広げられることになりました。創業家を代表し、経営の近代化に向けて意気込む正治にしてみれば、谷井の引退勧告はとても許せる類のものではなかったのでしょう。この人事抗争がいかに彼らを翻弄し、経営を空転させ、社業を傾かせていったのかの詳細については同書に譲りますが、いずれにせよ、幸之助とむめのが築き上げた「家業としての家族主義の良さ」は、幸之助亡きあと、急速にしぼんでいったのです。
閑話休題。
むめのは毎朝6時に起床し、朝食を終えると、新聞7紙に目を通しました。大阪発行の全国紙、地方紙、経済新聞、工業新聞……さらには幸之助宛てに送られてきた雑誌も一読したそうです。熱心に新聞を読んでいる彼女に不思議そうな視線を向けたお手伝いに、むめのはこう言いました。「主人のしとることを、分かっておらななりまヘん。また、忙しい主人が、見落としてしまいそうな話は覚えといて、言うたげななりません」。
新聞や雑誌に目を通すのは、一つでも幸之助の益になるものを見つけたい、という思いからでした。かくして、松下電器の要職を離れてからのむめのは、重要な記事はすべて切り抜いて台紙に貼りつけ、幸之助に伝えていたのです。むめのの献身は、内助の功あるいは糟糠の妻といった言葉だけで片付けられるものではなく、男のロマンを共有し、幸之助の良きビジネスパートナーとしての魅力を感じさせてくれます。
昭和64(1989)年1月7日の昭和天皇崩御から3ヵ月余が経過した4月27日、松下幸之助は94歳の生涯を閉じました。臨終の枕辺には正治、幸子夫妻をはじめとする松下家の人びと、むめのの甥の井植敏・三洋電機社長、丹羽正治・松下電工社長、谷井・松下電器社長など、ゆかりの面々が揃っていましたが、ただ一人、むめのの姿だけがそこにありませんでした。このときむめのは病床にあり、急変した幸之助の容態は周囲の気遣いで伝えられていなかったのです。
それから5年後。かねてお揃いであつらえておいた経帷子をまとい、むめのが幸之助のあとを追ったのは平成5(1993)年、9月5日のことでした。
享年九七。最後まで、むめのは幸之助を思い、自ら追いかけた夢を思った。そして、常に幸之助を立て、半歩後ろを歩くことを忘れなかった。その生涯からは、こんな声が聞こえてきそうだった。
「いつも早足で歩く人やった。最後まで、早足だった。これで、やっと追いつきますえ。これからは、もう少しゆっくり歩いとくなはれ。もう急ぐ必要はおまへんのやから。ゆっくりと、ゆっくりと」(288ページ)