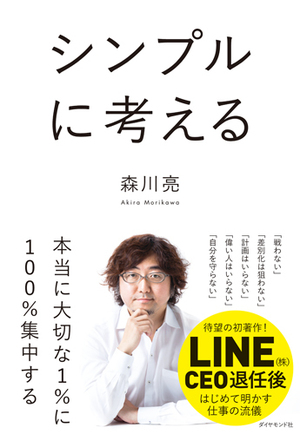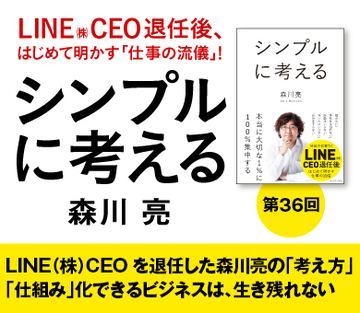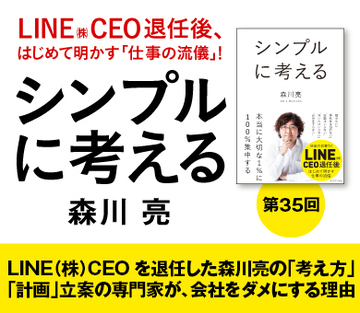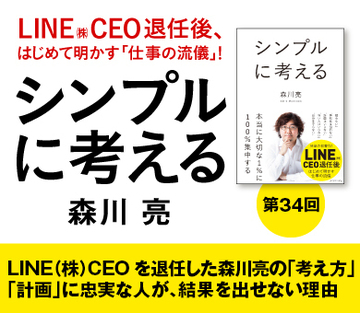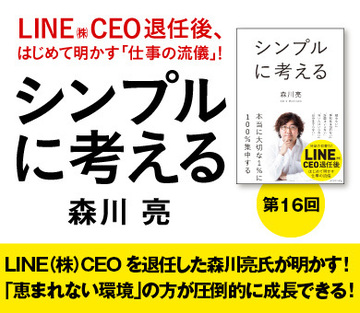「あれも大事、これも大事」と悩むのではなく、「何が本質なのか?」を考え抜く。そして、本当に大切な1%に100%集中する。シンプルに考えなければ、何も成し遂げることはできない――。LINE(株)CEO退任後、ゼロから新事業「C CHANNEL」を立ち上げた森川亮氏は、何を考え、何をしてきたのか?本連載では、待望の初著作『シンプルに考える』(ダイヤモンド社)から、森川氏の仕事術のエッセンスをご紹介します。
 1967年生まれ。筑波大学卒業後、日本テレビ放送網に入社。コンピュータシステム部門に配属され、多数の新規事業立ち上げに携わる。2000年にソニー入社。ブロードバンド事業を展開するジョイントベンチャーを成功に導く。03年にハンゲーム・ジャパン(株)(現LINE(株))入社。07年に同社の代表取締役社長に就任。15年3月にLINE(株)代表取締役社長を退任し、顧問に就任。同年4月、動画メディアを運営するC Channel(株)を設立、代表取締役に就任。著書に『シンプルに考える』(ダイヤモンド社)がある。(写真:榊智朗)
1967年生まれ。筑波大学卒業後、日本テレビ放送網に入社。コンピュータシステム部門に配属され、多数の新規事業立ち上げに携わる。2000年にソニー入社。ブロードバンド事業を展開するジョイントベンチャーを成功に導く。03年にハンゲーム・ジャパン(株)(現LINE(株))入社。07年に同社の代表取締役社長に就任。15年3月にLINE(株)代表取締役社長を退任し、顧問に就任。同年4月、動画メディアを運営するC Channel(株)を設立、代表取締役に就任。著書に『シンプルに考える』(ダイヤモンド社)がある。(写真:榊智朗)
事業スピードを上げるシンプルな方法
インターネット業界ではスピードが命です。
よほど技術的に差別化できない限り、新しい価値を生み出してもすぐにコピーされてしまう。それを前提に仕事の仕方を考えなければならないのです。だから、新しい価値を生み出すと同時に、最速のスピードで改善を重ねていく。そのスピードがライバルを凌駕していれば、追いつかれることはない。これが、インターネット業界のシンプルな必勝法則なのです。
では、スピードを上げるにはどうすればよいか?
簡単です。余計なことをやめればいい。すべてをシンプルにすればいいのです。
ムダな会議、ムダな申請書、時間のかかる決裁、上司への日次報告……。「本当に必要なのか?」という視点で検証すれば、いくらでも余計なルールは見つかります。これらを全部取っ払ってしまえば、メインの仕事をする時間しかなくなる。その当然の帰結として、スピードは最大化されるのです。
たとえば、LINE株式会社ではプログラムの仕様書はつくりません。権限や役割を大事にする会社だと、きちんとした仕様書をつくって、根回しをして会社の決裁を得なければ、エンジニアやデザイナーなどが動いてくれません。そのために、厖大な時間のロスが生じるのです。
しかし、LINE株式会社は、そのような「統制型のマネジメント」ではなく、「現場に任せるマネジメント」を採用しているので、商品コンセプトにエンジニアやデザイナーが共感すれば、わざわざ仕様書をつくらなくても、すぐにプロダクト開発に着手することができます。権限移譲もしていますから、現場リーダーがその場で「やろう!」と決断することもできる。やると決まったら、すぐにデザイナーがユーザー・インターフェイスを描いて、それをもとにエンジニアがプログラムをつくり始める。いきなり走り始めるのだから、圧倒的にスピードが速くなります。
トップスピードで走る社員に、組織を合わせる
注意したいのは、単に仕様書をやめればいいわけではないということ。権限や役割を重視する文化を残したまま、仕様書をやめれば職場は混乱するだけです。権限移譲をしていなければ、現場で意思決定をすることができませんから、上層部の決裁を得るために時間的ロスが生じるでしょう。仕様書をやめる効果は限定的にならざるを得ないのです。
これは、仕様書に限らない問題です。会議、申請書、報告なども、単にそれらをやめてしまえば、スピードが上がるとは限りません。場合によっては、職場が混乱したり、逆に非効率になることもありえます。そうした「表面的な現象」をいくらいじっても根本的な問題解決にはならないのです。
重要なのは、「いいものをつくりたい」という情熱と、技術をもつ野性的なフォワードたちに、仕事を任せることです。彼らはユーザーやマーケットと日々向き合っていますから、スピードの重要性は誰に指摘されなくてもわかっています。放っておいても、トップスピードで走り出すのです。そして、組織を彼らに合わせていく。
だからこそ、権限移譲をして、「現場に任せるマネジメント」になるし、彼らが全速力で走るのを邪魔するルールも取り払う。その結果、それらが有機的にからみ合って、組織全体のスピードも最大化されるのです。
ボトムの底上げが組織力の向上につながる──。
従来の組織論で、よく主張されてきたことです。「ダメな人たち」の成長に注力することによってこそ、組織全体の底上げができるというわけです。しかし、本当にそうでしょうか? 僕は疑問に思っています。
むしろ、フォワードにトップスピードで走らせる。それに、必死についていこうと努力するから、人は成長していくのだと思います。だから、僕はトップスピードに合わせることを経営の目標としてきました。それが、強い会社をつくる最高の方法だと考えているからです。