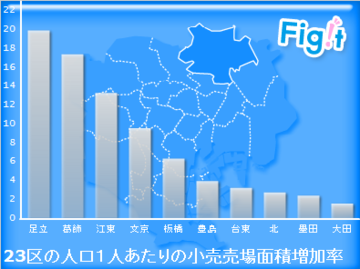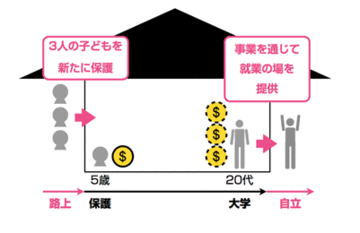竹ノ塚駅東口には小規模なフィリピンパブが密集する
竹ノ塚駅東口には小規模なフィリピンパブが密集する
「足立区のおじさんたちは、口は悪いけど目が優しいんだよね」
アニーさんはそう言って笑う。
「まず、このヤロ、バカヤロで始まるけれど、言っていることは正しかったりする。接客のマナーや態度についてよく怒られたけど、勉強になりましたよ」
足立区を拠点に、日本で働くこと25年。アニーさんはいま東武スカイツリーライン竹ノ塚駅のそばにあるフィリピンパブ「カリン」のママだ。
店はなんと、朝5時から営業している。
「タクシーの運転手さんたちから、夜勤が明ける朝方に店を開けてほしいって言われて」(アニーさん)
運転手だけでなく、やはり夜の仕事を終えた日本人のホステスやホストたちも飲みにくる。
夜が明ける頃になると、今度は年金暮らしの老人たちが訪れる。朝5時から11時までは、飲み放題・歌い放題で、さらに和定食がついて3時間2000円という破格の安さなのだ。
「あまりお金がなくても、ここに来れば友達がいて会話して、好きな歌を歌って楽しめる。朝や昼のお客さんは増えてますよ」(アニーさん)
明るいうちから泥酔して寝込んでいる客もいれば、外出したかと思えばハンバーガーとチキンを買ってきて店にいる人々に振る舞う客、家で作ってきたという故郷の料理を持ち寄るホステスたち……。
弛緩したアットホームな空気と、常連でなくともすぐになじめる親しみやすさは、アジアそのものだ。
フィリピンパブというと誤解されがちだが、お客の多くが求めているのは性的なサービスではない。フィリピーナの大らかさと、ホスピタリティに甘え、癒されにやってくるのだ。日本のスナックやキャバクラよりも、ずっとフレンドリーで「仕事でやっている」よそよそしさを感じさせない。南国をそのまま表したような満面の笑顔と、距離の近さ。
「みんな一緒に遊んでいるだけだから」とアニーさんは笑うが、客とホステスという垣根を取っ払ったような友だち感覚と、優しさに、日本人のおじさんたちは救われている。
 竹ノ塚駅周辺はフィリピンだけでなくアジア系外国人が多い
竹ノ塚駅周辺はフィリピンだけでなくアジア系外国人が多い
現在、フィリピンパブで働くホステスの多くは、1980~90年代に興行ビザを取得して「タレント」として来日した人々だ。2000年代に入るころには年間8万人のフィリピン人女性がパブで働くためにやってきたという。
しかしこれをアメリカ政府が「人身売買」と批判すると、日本はビザ発給の審査を厳格化。興行ビザはほとんど下りなくなった。以降、フィリピンパブを支えているのは、日本人と結婚して滞在カードや永住権を持っている女性だ。
日本人との間に生まれたハーフ世代も増えてはいるが、主力は熟女だ。外国で苦労して生きてきた彼女たちは、それゆえに懐が広く温かい。日々のストレスで疲れた日本人の男たちを、母か姉のように包み込んでくれる。