
技術のダイナミクスを理解せよ技術が製品や産業を生み出しそれが文明の発展を加速させる
上田惇生
ドラッカーは、まず、いかなる技術の変化が、いつ頃起こりそうかを知る必要があるという。もちろん技術の変化の日程は、あらかじめ知りうるものでは…
2012.11.6

上田惇生
ドラッカーは、まず、いかなる技術の変化が、いつ頃起こりそうかを知る必要があるという。もちろん技術の変化の日程は、あらかじめ知りうるものでは…
2012.11.6

高城幸司
リーダーや責任者になりたくないイマドキの若者が増えています。彼らは、もしリーダーを任されたとしても、同期を出し抜いていないか、周囲に嫌な思…
2012.11.5
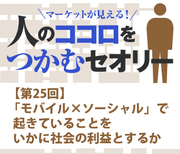
藤田康人
「その場でスマホ」が当たり前の世の中は、自分の行動が常に他人に見られているという自覚を持つことが大切だ。「モバイル×ソーシャルメディア」と…
2012.11.5
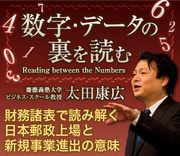
太田康広
日本郵政の上場計画が明らかになった。同社の財務諸表を使って、日本郵政グループが抱えている問題点と新規事業進出の意味を考えてみよう。
2012.11.5
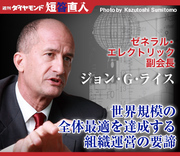
ゼネラル・エレクトリック(GE)が設立した全世界、事業を横断的に統括する組織、GGO(Global Growth & Operations…
2012.11.2
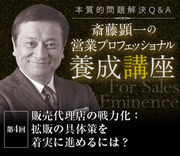
フォアサイト・アンド・カンパニー代表取締役 齋藤顯一
B2B製品を扱う法人営業マネジャーから、販売代理店の戦力化で拡販を図りたい、という相談が届きました。代理店販売の売上比率がジリ貧で、代理店…
2012.11.2

楠木 建
新しいことが次から次へと生まれる「ICT業界」で非連続性を組み込むのは挑戦的な仕事であるには違いないが、相対的にはイノベーションの機会が豊…
2012.11.1
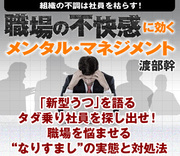
渡部 幹
「新型うつ」を語り、周囲に責任を押し付け、甘えるタダ乗り社員が増えている。問題なのは、本当にうつで苦しんでいる社員にまで偏見の目が向けられ…
2012.10.31
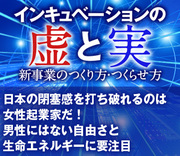
本荘修二
このところ「女性」が注目されている。報道でも急に扱われることが増えた。しかし、これは日本に限ったことではなく、世界的な潮流だ。women …
2012.10.29

上田惇生
ドラッカーは、リーダーたる者は、なすべきことからではなく、なされるべきことから考えよとさえいう。なすべきことを考えよというと、安易に、なし…
2012.10.29
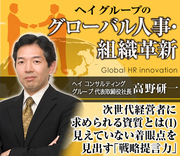
高野研一
いま次世代の経営者に求められている資質とは、「戦略提言力」と「リーダーシップ」の2つであろう。今回は戦略提言力とは何であり、それをいかにし…
2012.10.29
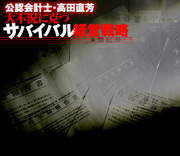
高田直芳
シャープについては、第89回コラムにおいて、ファナックやルネサスエレクトロニクスとともに、収益性分析を展開した。今回は、前回コラムで紹介し…
2012.10.26
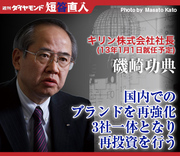
2013年1月、国内基幹事業会社3社をキリン株式会社(KC)の下に統括する。綜合飲料会社の設立の意図を聞いた。
2012.10.26

楠木 建
「なぜそうした優れた戦略を誰も思いつかなかったのか」、これが戦略イノベーションのもっとも本質的な問いだ。サウスウェスト航空の事例で「なぜ思…
2012.10.25

林 正愛
日本を変えていく存在と古川さんが期待を寄せるスマート・ウーマンとの対談第二弾。ソフトハウスを経営される市川博子さんは、日本の大学ではさきが…
2012.10.25
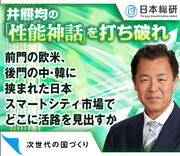
井熊 均
スマートシティ市場で日本は、前門の欧米、後門の中・韓に挟まれている。だからこそ日本は、エネルギーシステムを仕込み、組み上げ、事業として立ち…
2012.10.24
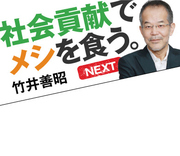
竹井善昭
「大きな社会的インパクトは、どのようにして生まれるか」について、それこそ大きなインパクトを与える本が発売された。同著では、マーケティングや…
2012.10.23

上田惇生
成功したイノベーションをしらみつぶしに調べ、それらの契機となったものを分類したところ、いちばん多かったのは発明・発見ではなかったという。そ…
2012.10.23

高城幸司
最近では、“ゴルフ女子”という言葉も生まれ、ゴルフは若い女性から人気を集めています。しかし、イマドキの若手男性社員は、先輩や上司が誘っても…
2012.10.22
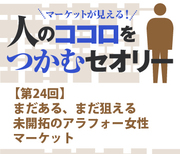
藤田康人
「美ST」元編集長の山本由樹氏が、来年4月に「アラフォー“独身”女性」だけにターゲットを絞った新雑誌「DRESS」を創刊する。未開拓の“独…
2012.10.22