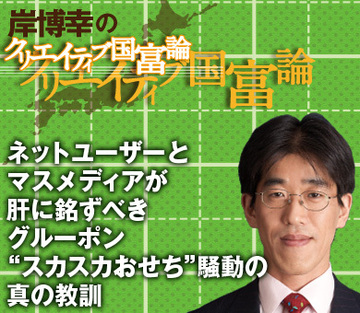岸 博幸
第140回
最近になって急に、官邸の政治家が発送電分離について発言をするようになり、菅首相も会見で言及しました。しかし東電賠償スキームとは矛盾しており、発送電分離の政策的意義を理解しているとはとても思えません。
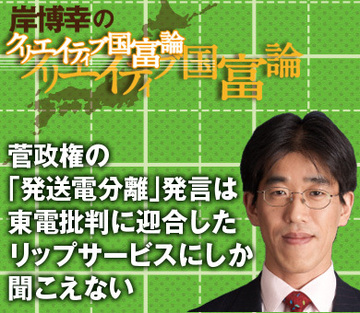
第139回
プロセスは杜撰で、実は原子力推進を前提としている浜岡原発停止。そして、市場のルールを無視し、かつ電力供給の独占体制を維持しようという東電救済スキーム。いずれの選択も、エネルギーの世界で、じつは震災前を再現しようとしているに過ぎない。
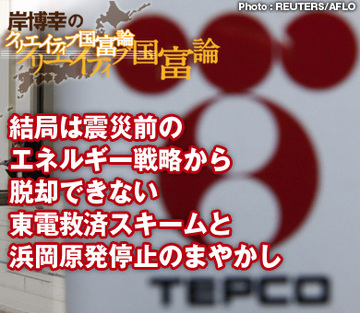
第138回
この大型連休中も、政府内では福島原発事故の被害者に対する損害賠償(補償)のスキームに関する検討が行われていた。政府は連休明けの5月10日の閣議決定を狙うが、やるべきことをやらずに電気料金値上げを急ぐ愚かな姿勢は糾弾されて然るべきだ。
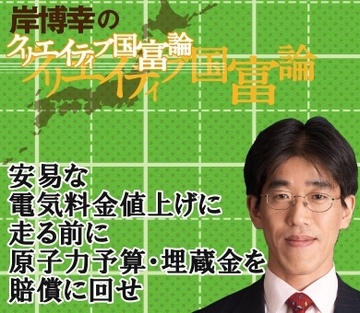
第137回
東北の復旧・復興に関する議論では、ゼロから新しい理想の姿を描くべきといった正論がよく聞かれます。しかし、将来の電力供給に関しては、基本的にはこれまでの電力供給体制の継続が暗黙の前提になっています。東京電力をめぐる議論が偏る最大の理由がそこにあります。
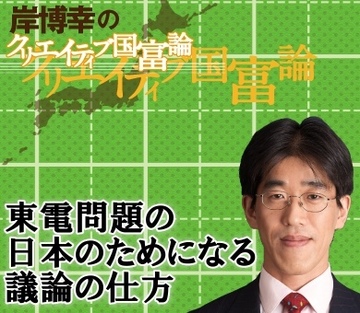
第136回
東電への政府支援策が、ほぼまとまりつつあるようです。そのポイントは被害者への補償金支払いを支援するための新機構の設立です。しかし現時点で判明している概要からは、東電と金融機関に甘く、国民に安易にツケ回ししようとしているとしか考えられません。

第135回
原発事故の補償というと農業や漁業のことばかりですが、地方都市の生活を支えてきた商工業についての議論があまりに少ない気がします。原発事故に苦しむ南相馬市を訪れて、その議論の重要性を痛感しました。

第134回
東日本大震災の被災地の方々が復旧に向けて大変な思いを続け、また福島第一原発がまだ落ち着かない状況であるにもかかわらず、予想されていた良くないことがもう政府内で始まってしまいました。それは、“震災を奇禍とした政府の焼け太り”です。
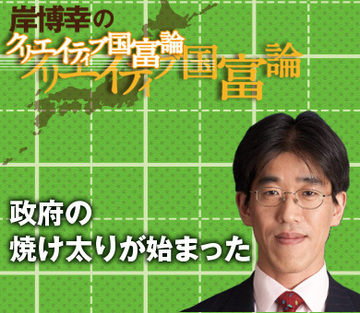
第133回
政府は福島第一原発から20~30キロ圏の住民に対して自主避難を促す一方で、民間企業には行政指導的な圧力をかけて同域内での通常の経済活動を強要しています。法律に基づく命令を出さず、現場に責任とリスクを押し付けるこの中途半端な対応は、混乱を増幅させるだけです。
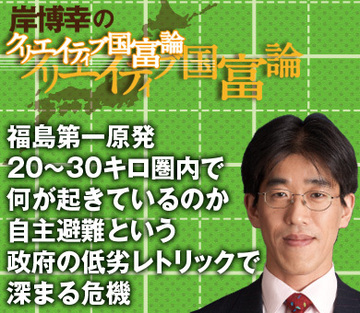
第132回
東日本大震災は製造業のグローバル・サプライチェーンに大きな影響を及ぼしていますが、重要なのは、世界の企業は震災からの復興を待ってくれるほど優しくないということです。日本がアジアのローカル経済の一つと落ちぶれるか、東北の復興とともに新たな形での繁栄を築けるかの分かれ道となるかもしれません。
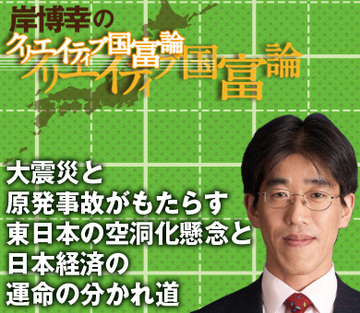
第131回
経済運営で最優先すべきは被災地への復興支援です。被災地の人命と生活が何よりも優先されることは当然です。しかし、それに加えて政府は、日本全体の経済運営も考えていかなくてはなりません。その際、二つの制約要因が存在することを意識しなくてはならないと思います。
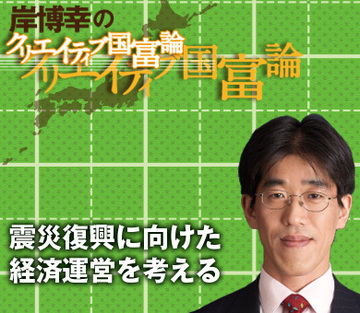
第130回
3号主婦年金問題が国会で大きな問題となっています。年金の切り替えを忘れて保険料が未納となっている主婦をどう救済するかという問題も当然重要ですが、この問題での政権の対応を見ていると、民主党の“政治主導”がいかにいい加減なものかが浮かび上がってきます。
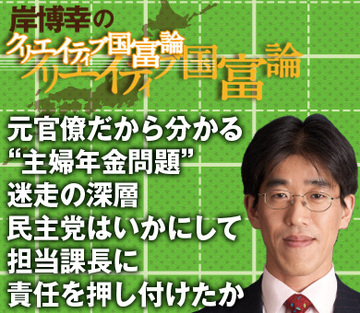
第129回
来年度予算案の年度内成立は確実になったが、予算関連法案の成立のメドは立っていない。本来、こうした状況では内閣の存続が危ぶまれるはずだが、官邸はなぜか強気を増している。そこには、野党批判の噴出を期待する奇妙な論理がある。
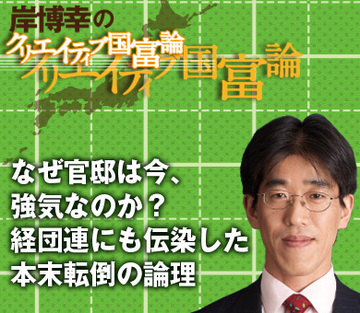
第128回
国家が“ネットの自由”を認めない場合に、反体制派が抵抗するのは自由ですが、それは内政の問題のはずであり、米国が原則論として振りかざすのは内政干渉に他なりません。それにも関わらず米国がなぜ、“インターネットの自由”という踏み込み過ぎた主張をするのでしょうか。
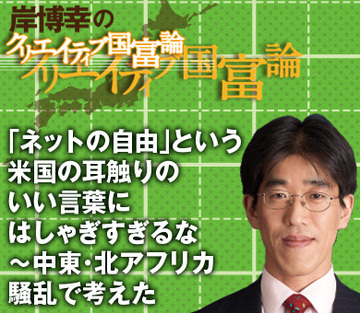
第127回
今回のネットバブルの本質は、マスコミよりもむしろユーザーその人からローコストなコンテンツを搾取して、そのコンテンツをユーザー間で過剰に共有させるという点にある。米国の識者は、この状況を指して「デジタル植民地主義」と呼ぶが、その真意とは?
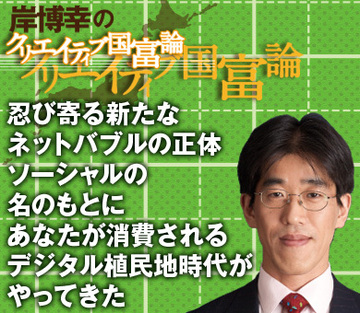
第126回
エジプト騒乱を指して、ツイッター革命、フェイスブック革命だと叫ぶ人が多いことに驚かされます。ちなみに、2009年のイランでの動乱の際もツイッター革命と言われました。結論から言えば、その認識は間違っています。
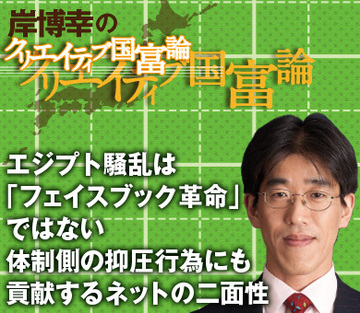
第125回
前回は、“財政再建=消費税増税”ではなく、“財政再建=増税+増収+歳出削減”が正しいことを説明しました。今週はその延長で、増税には“良い増税”と“悪い増税”の二種類があることを説明したいと思います。
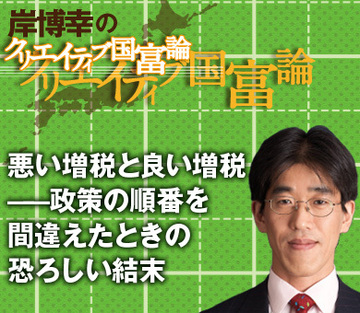
第124回
菅政権の消費税増税キャンペーンがいよいよ本格化している。政府が出す情報は増税に向けた機運の醸成を狙ったものばかり。一部の新聞もそれに乗ってしまっている感がある。そうしたキャンペーンに惑わされないよう、今回は基礎的なおさらいをしたい。
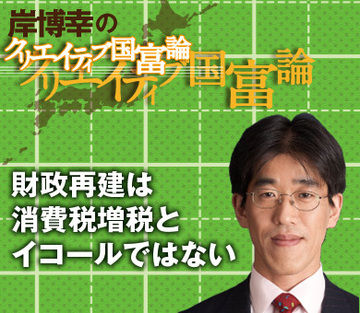
第123回
昨年の就任会見で、目指すべきは「最小不幸社会」だと述べた菅首相。しかし今回の内閣改造を見る限り、実際に目指しているのは「最小不幸財政と最大不幸経済」としか思えない。与謝野氏入閣は、民主党の国民に対する背信行為ではないか。
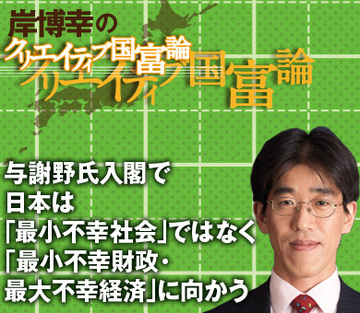
第122回
NHKの会長人事が大揺れに揺れています。一義的な責任は経営委員会にありますが、同時に民主党政権の責任も重いことを忘れてはいけません。この一事をもってしても、民主党の政権担当能力に疑問を感じざるを得ません。
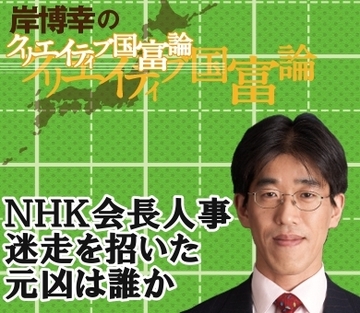
第121回
正月早々、ネット上ではグルーポンの“スカスカおせち”を巡って大騒ぎになりました。この問題にはいろいろな論点が存在しますが、個人的には、ネットの闇の深さとマスメディアの無力さが浮き彫りになったように思います。