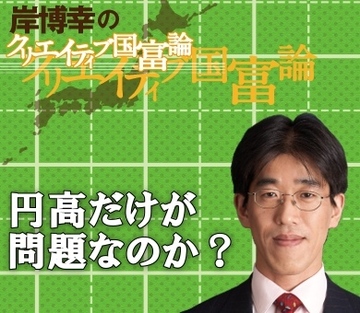岸 博幸
第120回
11年度予算の焦点となっている基礎年金の50%国庫負担を維持するため、国交省所管の独立行政法人の利益剰余金から1.2兆円の国庫返納を受けることが決まった。この決定自体は評価できるが、問題はその見返りとして行われた“ある取引”だ。
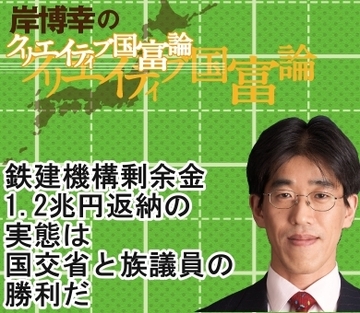
第119回
菅首相が、支持率回復を目指してか、自分で決断する場面を増やして“リーダーシップ”を濫発しています。しかし、政策議論が欠如したリーダーシップほど厄介なものはありません。法人税減税と諫早湾堤防の開門を例に、考えてみましょう。
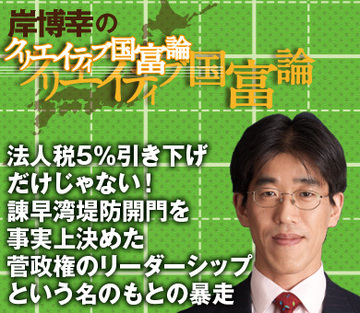
第118回
ウィキリークス問題を受けて、アマゾン・ドット・コムが同サイトへのサーバ貸し出しを停止したことは、一見もっともな対応に見えますが、とんでもありません。既存メディアも内部文書の暴露をしている点ではウィキリークスと同じ。アマゾンの恣意的判断はメディアにとって脅威なのです。
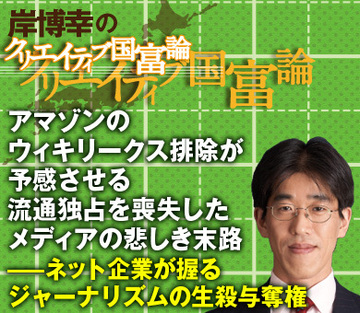
第117回
告発サイトのウィキリークスが米国務省の外交公電を暴露し、大騒ぎになっています。しかしメディアは公電の中身を面白おかしく報道するだけで、本質的な問題が議論されていません。それは、“インターネットの危険性”と“米国のダブルスタンダード”という問題です。
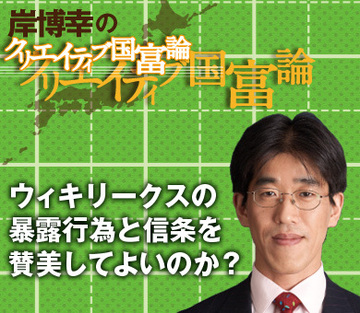
第116回
メディアの多くは北朝鮮の今回の暴挙を北朝鮮問題という独立の事象として捉えていますが、日本の外交の迷走がこの問題に少なからず影響を与えていることを忘れてはいけません。日本政府の責任も重いのです。
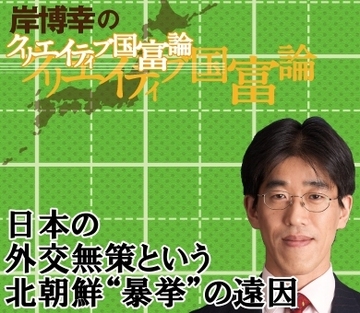
第115回
事業“再”仕分けについては、行うこと自体まったく意味がないと先週説明しましたが、言い直します。あのような低レベルな議論では行うことによる弊害のほうが目につきます。電子書籍中間フォーマットを巡る議論は、まさにそのことを浮き彫りにしました。
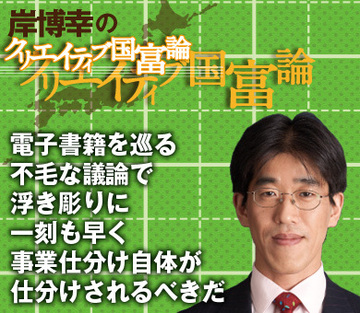
第114回
15日から事業仕分け第3弾後半戦が始まります。これまでの事業仕分けの判定に従わず予算要求を続ける事業の再仕分けですが、そもそも予算要求のすり抜けが問題ならば、行刷会議と各省庁代表の政治家が議論し、粛々と政治決着を目指せばいいだけの話ではないでしょうか。
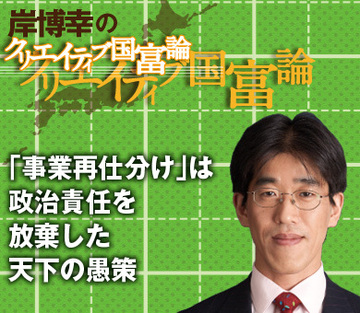
第113回
天下りは禁止するが、現役幹部の民間出向を増やし、かつ出世コースから外れた幹部公務員も定年まで働けるようにする。そんな公務員制度“改悪”が進行中です。民主党は霞が関を高齢者と安定志向の若者ばかりにしたいのでしょうか。

第112回
10月20日に英国のオズボーン財務相が、財政赤字削減のための「包括的歳出見直し」を発表した。同国にとって第2次大戦後最大規模となるこの歳出削減は、日本に3つの教訓を提示している。
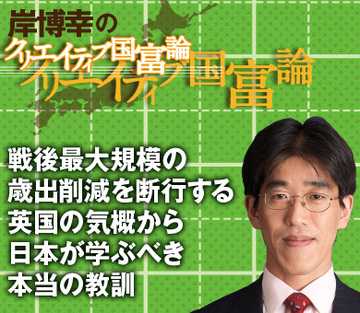
第111回
デフレによる日本社会の劣化を指摘したNYタイムズの記者、「大人、もっと頑張れ」と話してくれた中学1年生作家・宮井紅於さん。“デフレ日本”に巣食う無気力と甘えの構図を自覚できていないのはもはやわわわれ大人だけかもしれない。
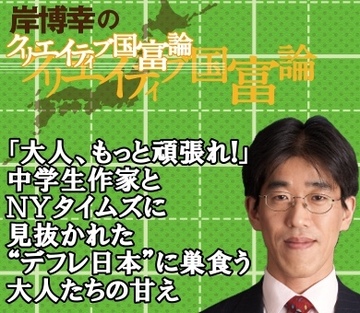
第110回
今週号の週刊ダイヤモンドは「電子書籍入門」という特集を展開しています。その充実した中身は評価できますが、気になる点もいくつかありました。読書離れは起きてない、電子書籍が普及すれば良書に出会う機会が増えるといった事実認識は本当に正しいのでしょうか。

第109回
米国でかつて最大手DVDレンタル・チェーンだったブロックバスターが経営破綻しました。そこに至るまでのレンタル市場の変容やライバル企業の躍進を学べば、メディアにとって重要な教訓を得ることができるのではないでしょうか。
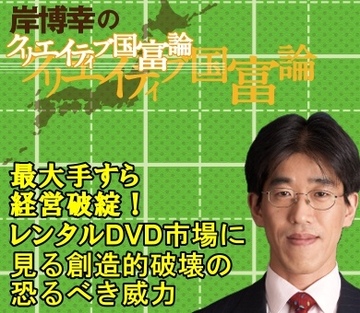
第108回
尖閣諸島問題を巡る政権の混迷の陰に隠れていますが、政府内では経済政策の司令塔を巡る混乱もひどくなっています。その両者に共通するのは、政策決定プロセスの崩壊です。“政治主導”の美名の下で“その場しのぎの政策決定”が繰り返されているのです。
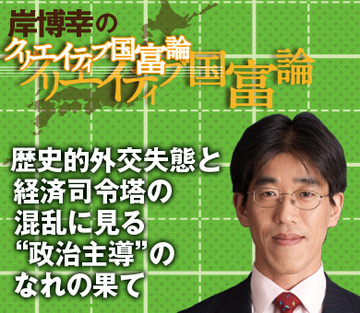
第107回
経済規模逆転は序の口。今後人民元の切り上げが進めば、2010年代後半にも中国の名目GDPは日本の2倍になる可能性が高い。尖閣諸島問題での中国の強硬姿勢を見れば、日本が外交的に絶対不利な状況に追い込まれるのは確実だ。
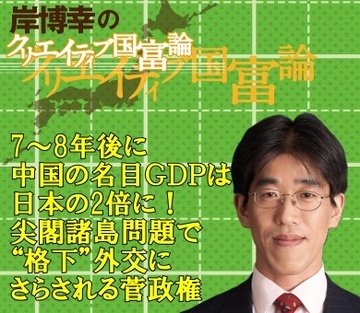
第106回
故ミッテラン仏大統領は就任当初、社会主義的政策を展開しましたが、それで経済が悪化すると、欧州統合を旗印に政策を市場主義の方向に大きく転換しました。同じ君子豹変を(いい意味でも)「パクリの天才」である菅総理に期待したいと思います。

第105回
民主党代表選も終盤なのに、経済政策を巡る論争はいまだ酷いままです。もはや政策の中身には期待できません。こうなったら、政策プロセスの改革につながり得る“思い”はどちらが強いのか――この点を評価基準とするしかないでしょう。
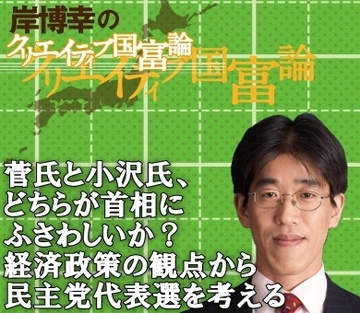
第104回
民主党代表選は党内権力闘争の最終決戦と言える構図となり、メディアにはたまらない展開でしょう。しかし、国民からすれば、緩やかな衰退か、劇薬治療か、どちらかを選べと言われているに等しく、悲劇以外の何物でもありません。
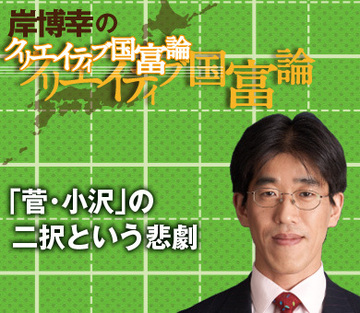
第103回
ITとネットは世の中を便利にしたが、本当に困っている人を救えるのか。この点について、私はこれまで懐疑的でした。しかし、高齢化率33%という北海道白老町で始まったある実験を通して、希望を持ち始めました。
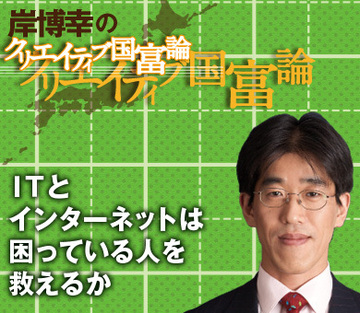
第102回
小中学生向けの電子教科書の普及を目指す産学協同コンソーシアムの「デジタル教科書教材協議会」が発足しました。しかし端末やプラットフォームは、アップルのiPadなど米国IT企業頼みになる予感。日本の教育の未来を左右する取り組みなのに、これでいいのでしょうか。
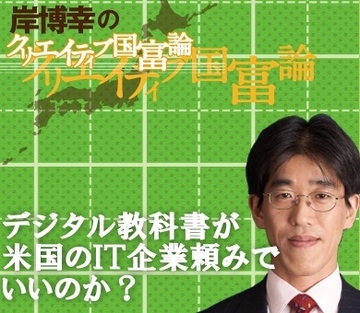
第101回
昨年は景気低迷の原因としてリーマンショックが、そして今回は円高ばかりが騒がれています。海外要因で景気が良くならないと政府が自己正当化し、新聞まで迎合してしまうようでは、とても正しい政策対応は望めません。