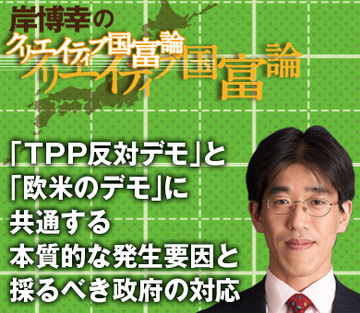岸 博幸
第180回
4月1日から東電の企業向け電気料金が値上げされ、当然ながらメディア上では東電への批判が目立ちます。値上げに至るまでの東電の対応のずさんさを考えると当然ですが、ある意味で東電以上に批判されるべきは経産省であることも忘れてはいけません。
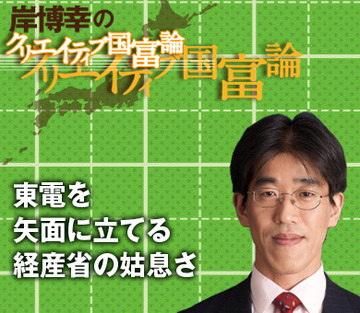
第179回
最近、ゴールドマン・サックス、グーグルという米国を代表する企業の幹部が「なぜ自分が会社を辞めたのか」という手記を公表しました。実はこの手記でも語られている2社が直面する問題点は、野田政権が目指す消費税増税にもそのまま当てはまっています。
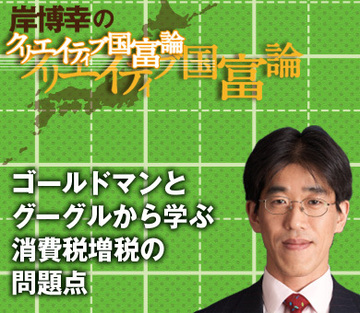
第178回
日本では「若者が弱くなった、内向きになった」と言われるようになって久しいですが、独立精神が旺盛で住む場所が移り変わることも厭わない国民性のはずの米国でも同じようなことが起きています。しかも、その原因の1つがネットであるかもしれないのです。
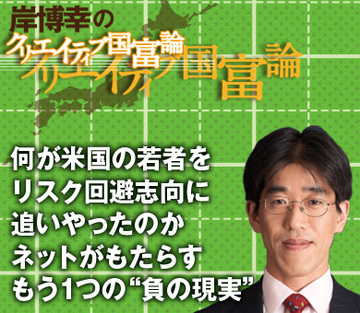
第177回
グーグルが3月1日にプライバシーポリシーを変更しましたが、この問題の深刻さとそれへの欧米の政府の対応の素早さを踏まえると、日本人のプライバシー意識の低さと日本政府の対応の緩さが改めて目につきます。これで日本は本当に大丈夫でしょうか。
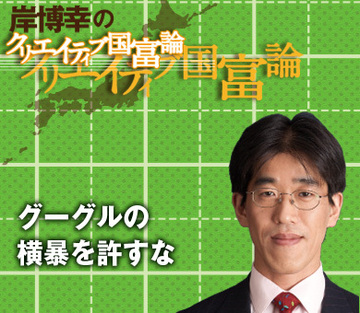
第176回
3月1日、橋下大阪市長の命により市役所内の違法行為を調べている第三者調査チームの中間報告が公表され、市の労働組合の呆れた実態が明らかになっています。しかし、内容もさることながら、労働組合が第三者調査チームを潰そうとしている事実も看過してはいけません。
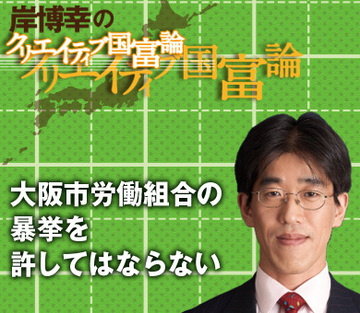
第175回
日本ではダルビッシュの動向に皆が注目していますが、米国プロスポーツ界では別のアジア人選手に大きな注目が集まっています。それがNBAのジェレミー・リンという台湾系アメリカ人選手です。実はこの選手の活躍から面白いインプリケーションが得られます。
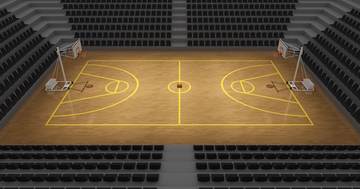
第174回
経済産業省は、東京電力に1兆円規模の公的資金注入を行い、東電の2/3以上の議決権を取得し、一時国有化しようとしています。これに対し、当事者の東電に加え、経団連や財務省までもが異論を唱えています。この状況をどう理解すべきでしょうか。
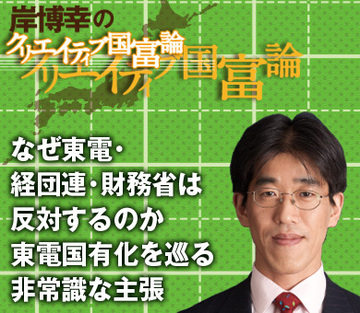
第173回
かつて米国を代表する企業であったGMは最盛期に米国内で40万人の雇用を産み出したのに、今の米国を代表するアップルはその1/10の4万人強の雇用しか産み出していません。この事実は、米国の中流階級の雇用喪失を示していますが、日本も例外ではないでしょう。
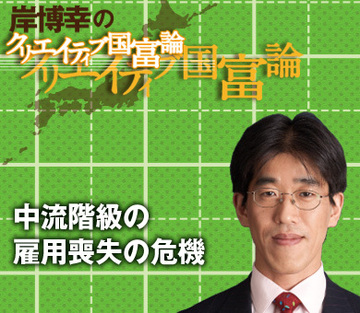
第172回
以前、ネットは民主主義と資本主義のあり方を変えつつあることを説明しましたが、ネット企業は雇用の構造も変えつつあります。それは先日、時価総額が世界一になったアップルの生み出す雇用の数を見れば明らかです。
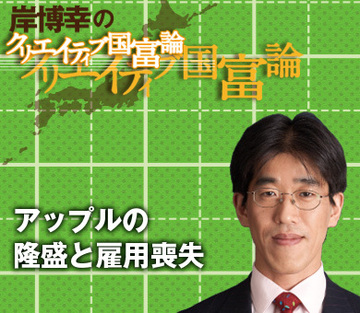
第171回
ある世論調査によると、「国民の約半分が二大政党に不満」「3分の2以上が、第三極の政党の代表に国のリーダーを望む」という結果が出ました。一見すると日本での調査と思われるかもしれません。しかしこれは、驚くべきことに米国で行われたものなのです。
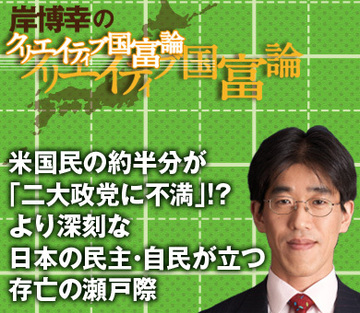
第170回
米国では、ネット上の違法サイトを取り締まる法案に対するネット企業の抗議行動が激しくなっています。日本では、どのネット企業がどういうアクションを起こしたという報道ばかりですが、この騒ぎからいくつかの重要な教訓を学べるのではないでしょうか。
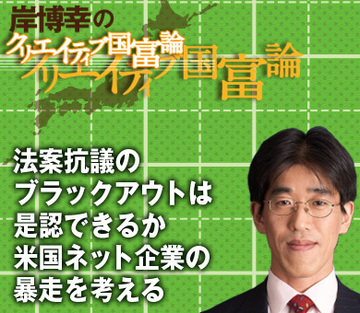
第169回
ソーシャルメディアの普及に伴い、民主主義が変質し始めています。しかし、先週政府与党で決定した社会保障・税の一体改革がよい例であるように、政治と行政は、策定プロセスにおいて民意を軽視し続けており、鈍感といわざるを得ません。
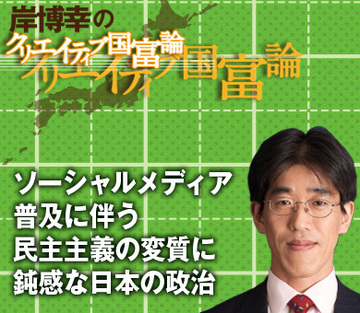
第168回
消費税増税を含む社会保障・税一体改革の素案が、今日の政府・与党の社会保障改革本部で正式決定されようとしています。しかし、メディアでは一体改革の問題点がしっかりと整理されていないようですので、今回、改めて整理したいと思います。
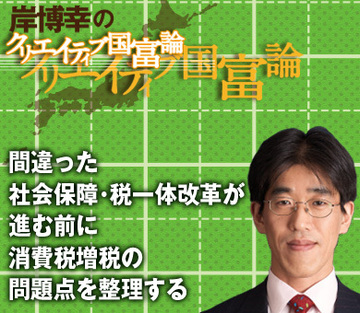
第167回
私は、消費税増税最優先の経済財政運営には反対しています。ですが、いずれ消費税増税が必要なことも事実なので、今回は、もし私が民主党と財務省の応援団だったら、消費税増税の実現に向けてどういう提案をするだろうかを考えてみました。
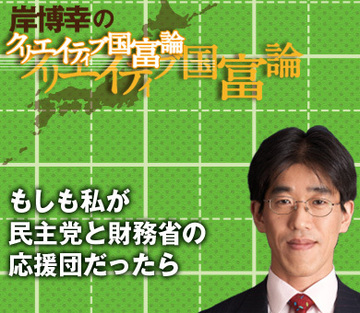
第166回
米国では、金融業界の金持ちを攻撃するデモが盛り上がったように、1929年の世界恐慌以来久々に「格差」を巡る議論が盛んになっている。その議論から、日本が学ぶべきは、今や成長と社会的平等が密接不可分であるという認識だ。
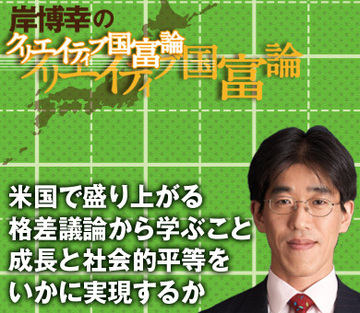
第165回
今やスマホ向けのOSでは、グーグルのアンドロイドやアップルのiOSが急速に普及しています。もちろんユーザの立場からすれば、スマホが便利であれば何の問題もありません。ただ、アプリを提供する側からすれば、既に様々な問題が生じています。
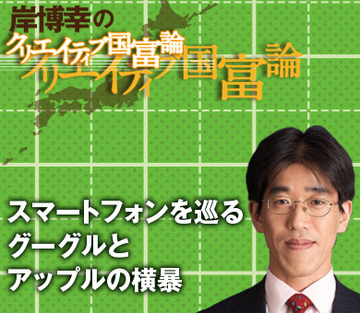
第164回
日本でもスマートフォンが急速に普及を始め、3年後にはユーザの半数近くがスマホになると予測されています。しかし、この盛り上がりを手放しで喜んで良いのでしょうか。
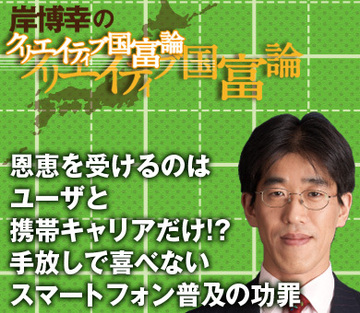
第163回
すったもんだの混乱を続けるTPPと今月27日の大阪W選挙。じつは両者には大きな共通点があります。この2つの問題の帰趨がどうなるかが日本の将来を占う試金石となるのではないでしょうか。
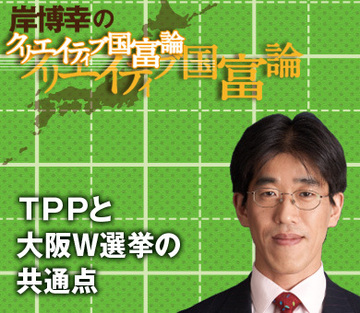
第162回
福島県では放射線を除染する作業が進められており、そのために様々な予算措置が講じられています。その中で、独立行政法人に除染事業を委託した予算について、その一部が中抜きされているのではという懸念があります。
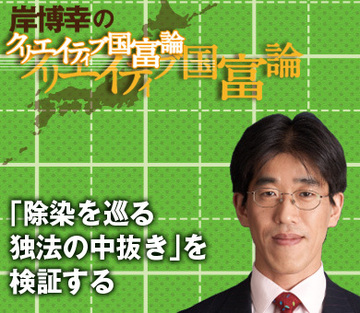
第161回
TPP参加反対を叫ぶデモが盛んになっています。欧州と米国でもデモが続いていることを考えると、日米欧と主要先進国すべてにデモが伝播したとも言えますが、日本のデモと欧米のデモを比較すると、どのようなインプリケーションが得られるでしょうか。