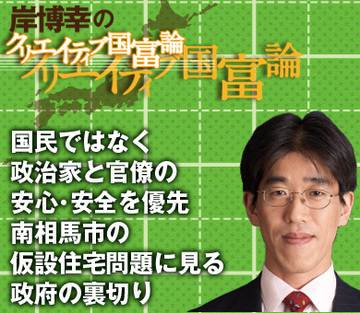岸 博幸
第160回
11月のAPEC首脳会合というデッドラインが近づくにつれ、TPPを巡る政府与党内の議論とメディアの報道が盛り上がってきましたが、どうも偏った議論ばかりが横行しています。このままで交渉への参加・不参加が意思決定されて大丈夫なのでしょうか。
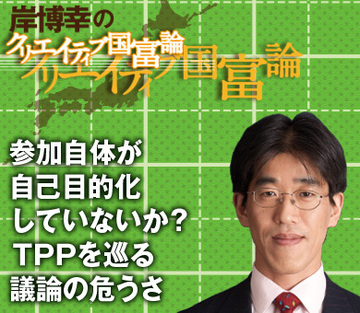
第159回
スティーブ・ジョブズ氏が10月5日に死去して以来、特に米国ではあらゆるメディアが同氏に関する特集を行なっていたが、それらの報道を読んでつくづく感じたことがある。民主党政権の政治家こそ、ジョブズ氏の功績から学ぶべきではないだろうか。
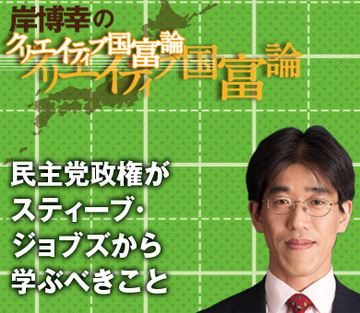
第158回
10月3日に“東京電力に関する経営・財務調査委員会”が報告書を発表しました。新聞などでは、東電のリストラの深堀りや電気料金値上げなどの表面的な数字ばかりが大々的に報道されていましたが、一番大事な点が報道されていません。
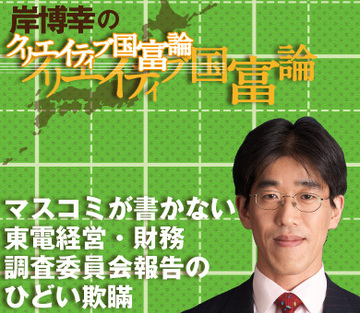
第157回
ソーシャルメディアは、中東や中国などでは民主化を進めるための手段として不可欠なものとなっていますが、メキシコではまったく別の意味で不可欠なものとなっていることをご存知でしょうか。なんとサバイバルの手段として不可欠になっているのです。
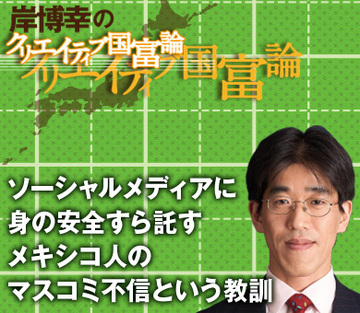
第156回
今や日本はもちろん、デフォルトの危機が報じられるギリシャを筆頭に欧州や米国でも、財政赤字と累積債務の削減という財政規律が最優先された経済財政運営がまかり通っています。しかし、そうした財政規律最優先は本当に正しいのでしょうか。

第155回
臨時国会が召集され、野田首相が初の所信表明演説を行いました。報道によると野党は「官僚の作文」など厳しい評価を下していましたが、実際にどの程度の出来なのかを検証してみましょう。

第154回
「Breaking All Illusions」とは、私がこよなく愛するプログレメタル・バンドの新アルバムの中の一曲のタイトルなのですが、今の日本の政策を巡る議論でもっとも必要なことを端的に示しているのではないでしょうか。

第153回
原発事故の被害について、外国からも巨額の損害賠償請求を起こされる可能性が高まってきた。一部には、その額は数百兆円レベルに上るとの声もある。東電の温存を認め、国の責任を謳った現在の東電救済スキームの下で、本当にそんなことが起これば、日本はおしまいだ。
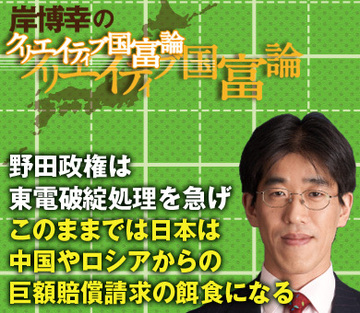
第152回
いよいよ29日に民主党代表選が行われ、次の首相が決まる。候補者たちが大連立や挙党一致など政策実現手段の話ばかり喋るのに対して、メディアもようやく「政策論争を」と言うようになり、この週末は候補者の間で論争が展開されるだろう。では政策論争のどこに注目すべきなのか。
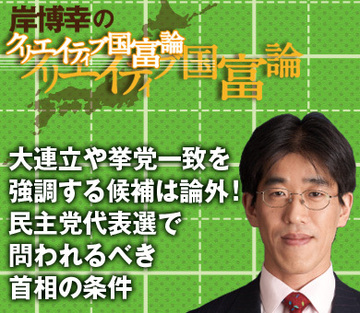
第151回
今年に入って世界各地で頻発する暴動やデモ。その本質的な原因について、ニューヨーク・タイムズのコラムニストであるトーマス・フリードマンが興味深い分析をしていた。
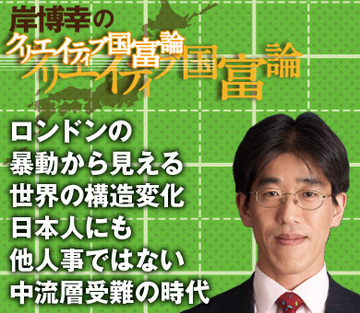
第150回
経産省の3人の幹部(事務次官、資源エネルギー庁長官、原子力安全保安院長)が先週“更迭”されましたが、それでも退職金は割り増し分も含めて受け取ることが明らかになりました。この問題には様々な論点が存在するので、今週はそれについて考えてみたいと思います。
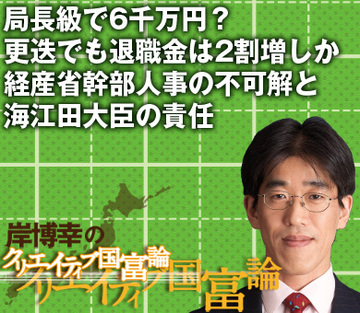
第149回
経産省の幹部3人の更迭が発表された。しかし、そもそも彼らは、この夏の定期人事異動で辞職していてもおかしくない人たちばかり。組織を防衛したい経産省と政治的得点を稼ぎたい海江田経産相による“やらせ人事”と呼ばずして何と呼ぶか。
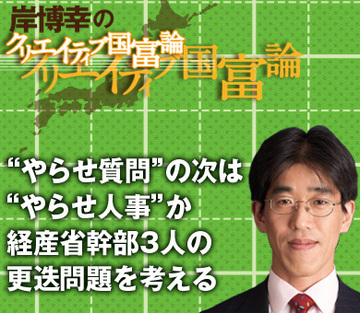
第148回
国会で審議中の原子力損害賠償支援機構法案の修正について、与野党が合意しました。しかし、合意内容を見ると、元々の法案よりも東電に対して更に甘くなりました。こんな修正を許して良いのでしょうか。

第147回
菅首相の暴走に世の人が呆れ返る中で、政府が講じる政策は官僚主導のグダグダの連発となっている。これで本当に被災地復興が速やかに進むのか。企業の海外逃避が加速する“大空洞化”を避けることができるのか。来るべき民主党代表選の争点を考えた。
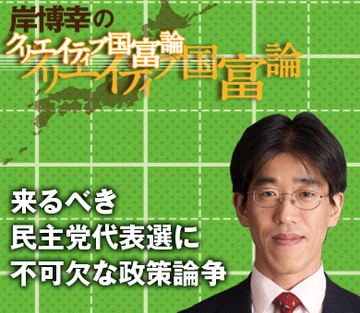
第146回
私がかつて20年ほどお世話になった経産省は、原発事故以来、菅首相の攻撃対象としてすっかり悪者になってしまった。しかし、問題が多いのも事実。もういっそ経産省は、“解体的出直し”とか甘い次元ではなく、解体すべきではないか。
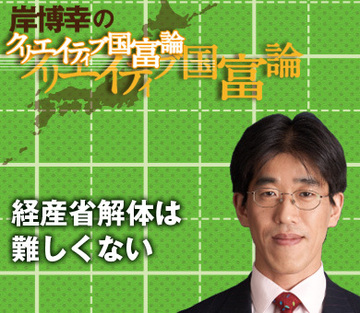
第145回
松本前復興相の辞任や停止中の原発の再稼働を巡る混乱など、政治的な混乱から菅政権の限界が露呈しているが、既に政策面でもこの政権の限界は明らかになっている。その典型例は先月下旬に公表された復興構想会議の提言だ。

第144回
菅首相が目指す脱原発と再生可能エネルギー普及という方向は正しいのに、電力会社と経産省がそれを妨げる“抵抗勢力”となっている、といった論調が目立つようになってきた。しかし、それは本当なのだろうか。

第143回
真偽の程は定かではないが、菅首相が8月に脱原発解散総選挙に打って出るとの噂が永田町を駆け巡っている。ただでさえ問題だらけの再生可能エネルギー特措法案は本当に政争の具に成り下がってしまいそうだ。
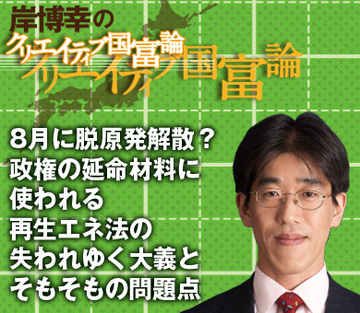
第142回
今回の原賠機構法案は酷いとしか言いようがない。筆者も機構を設立すること自体には賛成だが、問題はとにかく中身だ。最大の問題点は、被災者の救済が主目的の法案のはずなのに、東電を甘やかしながら救済しようとしていることに尽きる。

第141回
被災者向けの仮設住宅について、大畠国土交通相は「8月前半には必要個数を完成させられる」との見通しを明らかにしました。これだけ聞くと、順調に進んでいるように思えますが、実態は違います。それは、南相馬市の例からも明らかです。