
野口悠紀雄
第60回
フィンテックでもっとも重要と考えられているのは、ブロックチェーン技術の応用だ。ビットコインなどの仮想通貨の基礎技術であり、金融産業が将来大きく変わることを予感させる。

第59回
タックスヘイブンの問題は複雑である。パナマ文書問題をきっかけに、税制の公平化を前進させるには、問題の所在を正確に把握する必要がある。

第58回
急ピッチで円高が進んでいる。投機資金の動向は円高を期待する方向へと大きな変化が生じており、実際のデータで確かめることができる。本格的な円高再来に日本企業は備えるべきだ。

第57回
政府は緊急経済対策を講じ、消費喚起を図る予定だ。さらに消費税増税の再延期も検討されている。しかし、消費が停滞するのは構造的な要因によるものだ。したがってそれらの政策でも増加しないだろう。真に必要な方策とは何か。

第56回
マイナス金利はREIT価格を急上昇させた。ただし不動産価格上昇は局所的だ。マイナス金利が長期継続し、預金金利もマイナスになるような事態になれば、大都市の優良物件に投資資金が集中し、二極化現象が拡大する可能性がある。

第55回
マイナス金利の目的は、企業の投資を増加させることだとされているが、果たしてそれは本当なのだろうか?筆者はむしろ、余った資金が設備投資に向かわず、不動産バブルを引き起こすことを懸念している。

第54回
マイナス金利導入は投資を増大させるためとされている。だがインフレターゲットやマイナス金利はもともと多くの問題を抱えている。最も大きな問題は、実質収益率がマイナスである投資も正当化し、経済の縮小均衡を加速させることである。

第53回
安倍内閣は春闘に介入し企業に賃上げを要請してきた。しかし仮に要請通りの賃上げに成功しても、現在の日本経済の構造では、全体の賃金所得増にはあまり寄与しない。問題解決には生産性の高い新しい産業が登場するしかない。
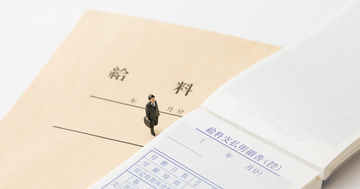
第52回
現在の市場・経済状況を背景として、緊急経済対策が必要との議論が生ずる可能性が高い。本当に重要なのは構造改革だが、緊急対策がどうしてもとられるのであれば、その内容をいくらかでも望ましいものに近づける必要がある。
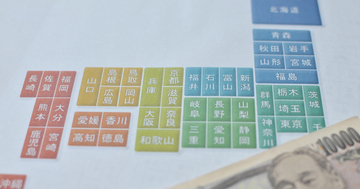
第51回
仮想通貨の基礎技術「ブロックチェーン」に対する関心がにわかに高まっている。日本の銀行や取引所も次々と実証実験を開始。その応用によって金融取引の形は大きく変わる。マイナス金利がこうした動きを加速する可能性もある。

第50回
実質GDPマイナス成長の原因は消費の落ち込みであり、もっと基本的な原因は実質賃金が伸びないことだ。原油価格が大幅に下落する中で、本来これはありえない。ここに、アベノミクスの基本的な問題点が露呈している。

第49回
マイナス金利導入によって金利は急激に下落した。だがイールドカーブを分析すると、今後マイナス幅は拡大ではなくむしろ縮小し、数年後にはプラス金利に復帰する。マイナス金利が経済の構造を大きく変えるようなことはないだろう。

第48回
日銀のマイナス金利導入によって金利は低下するだろう。円安だけが目的なら国債購入は必要なくなる。しかし銀行の収益悪化で国債購入が続く可能性が高く、矛盾が生じる。そして欧州の経験では、実体経済を活性化する効果はない。

第47回
原油をはじめとする資源価格の下落で、本来であれば経済は活況を呈するはずだ。だが実際にはそうなっていない。原材料価格の低下が企業の内部留保に吸収されてしまっているからだ。現在の状態を打破するには何が必要か。

第46回
世界経済が大きく動揺しているが、この変化を利用して日本の実体経済を成長させることができる。資源価格が下落しているからだ。物価の引き下げを通じて、これを実質消費の増加につなげることが重要だ。

第45回
国際的な投機資金の流れが大きく変化している。日本では株価下落と国債利回り低下、そして円高が進んでいるが、これはリスクオフ現象の結果と解釈できる。この動きにより円高が進み、日本経済に大きな影響が及ぶ可能性がある。

第44回
新年早々の株価の変動は、アメリカ金融正常化後の新しい均衡への市場の模索である。しかし日本にとって最も重要な動きは、資源価格や商品価格の下落だ。明らかにプラスのはずのそれが、経済成長に結び付いていないのはなぜか。

第43回
アメリカの金融正常化で、新興国は大きな影響を受ける。そして新しい経済均衡では、先進国は2つのグループに分かれ、経済成長率と為替の両面において対照的な動きを示すことになる。その中で日本はどうなるのか。

第42回
軽減税率について、自公両党の合意が成立した。だが消費税構造の合理化には手がつけられておらず、制度の矛盾はむしろ拡大した。このような問題を政治的な駆け引きだけで決めていけば、消費税制度は崩壊してしまうだろう。

第41回
7~9月期の設備投資額は増加したが、ほとんどが更新投資であり、これは日本経済の回復を示すものではない。伸び悩みの要因は売上が伸びないことだ。「法人税を減税すれば設備投資が増える」という政府の考えは誤っている。
