
野口悠紀雄
第41回
7~9月期の設備投資額は増加したが、ほとんどが更新投資であり、これは日本経済の回復を示すものではない。伸び悩みの要因は売上が伸びないことだ。「法人税を減税すれば設備投資が増える」という政府の考えは誤っている。

第40回
賃金引き上げが経済政策の主要課題となりつつある。「どうすれば賃金を引き上げられるか」を考えるには、「なぜ賃金が上がらないのか」に関する正確な理解が必要だ。そして、政府が行おうとしていることはどれも適切ではない。

第39回
企業利益が歴史的な高水準になっている。それにもかかわらず、経済は停滞している。企業利益の増加は人件費抑制によるものであり、そのために消費支出が伸び悩んでいるからだ。この状況にどのように対処すべきか。
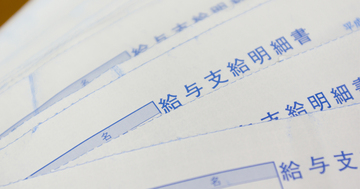
第38回
日本経済は2期連続のマイナス成長になった。その原因を真剣に検討する必要がある。現状から明らかなのは、経済政策が内蔵する要因のために長期的な停滞から脱出できないということだ。経済の基本構造にメスを入れる政策が必要だ。

第37回
フィンテックでは多数の新しいサービスが登場し、中には伝統的な大銀行に匹敵するほどの時価総額になった企業もある。なぜこのような急成長ができるのか、今後の成長可能性はどう評価されるのか、分析する。

第36回
フィンテックについてはバラ色の未来が訪れるような報道が多い。だがデジタル革命は一般に破壊的な影響力を持つ。大変動に対処するため欧米の金融機関は既に積極的な取り組みを行なっている。日本の金融機関は対応できるのか?

第35回
日本の金融市場はきわめて異常な姿になっている。この状態は安定的ではなく、本来は出口を探らなければならない。だが現実には低金利状態を続けざるをえず、のみならず追加緩和を求められるという悪循環に陥っている。

第34回
政府は軽減税率に関する財務省案を撤回し、新たな仕組みを考えるとした。日本で軽減税率が問題となるのは、インボイスがなく、免税や簡易課税という特例が存在するからだ。この機会に消費税の構造を合理的に改革すべきだ。

第33回
TPPに対する論評では、そのマイナス面が十分考慮されていない。最大の問題はTPPが中国を太平洋圏から締め出し、それによって日本の輸出市場が失われることだ。中国は独自経済圏の形成に進んでおり、この危惧が現実化しつつある。

第32回
鉱工業生産指数や在庫指数の動きから判断すると、7~9月の実質GDPもマイナス成長になる可能性が高い。重要なのは、これが構造的な問題であることだ。金融緩和や財政拡大では対処できない。必要なのは経済構造の転換だ。

第31回
安倍総理が発表した「新3本の矢」は、「金融緩和政策から足を洗う」という政策転換の表明だ。しかしこれは経済政策の失敗から国民の目をそらすものである。いま必要なのは、思いつき的キーワードを乱発することではない。

第30回
米国の利上げは今後確実に行われる。それにより経済混乱が懸念されるのは、資金流出が進む“中国以外”の新興国である。一方、円レートがどうなるかはきわめて見通し難い。このような状況下で必要な経済政策とは何か。

第29回
軽減課税に関し財務省が提案した「還付方式」は一見、日本の特殊事情に合わせた現実的なやり方に思える。だが実際は矛盾と無理を重ねてきた消費税の問題点を隠蔽するものであり、導入すれば将来に大きな禍根を残すだろう。

第28回
IoTによる製造業の生産性向上が期待されているが、その実現には多くの困難な問題がある。解決するには、ビットコインの基礎技術であるブロックチェーンの応用が不可欠だ。現実の世界はその方向に動きつつある。

第27回
アメリカの証券取引所や大手銀行が新たな取り組みを始めている。ビットコインの背後にある「ブロックチェーン技術」を、証券取引や銀行内部で使おうとしているのだ。一方、日本の金融機関は、新しい技術を無視している。

第26回
現在生じている株価下落は、リーマンショック後続いてきた金融市場での世界的なバブルの終了と捉えるべきである。金価格下落に始まり新興国、原油と続いた「新しい均衡を求める動き」が、先進国株式に表れ始めているのだ。

第25回
4~6月期のGDPマイナス成長は、日本経済が停滞の罠から脱出できていないこと、そしてこれまでの経済政策の行き詰まりを明確に示している。「一時的」として無視するのでなく、経済政策の基本を転換させる必要がある。

第24回
TPPに経済的な効果はほとんどない。これが妥結しなかったからといって、日本経済に大きな影響があるわけではない。より重要なのは、中国のリアクションだ。とりわけAIIBのような動きは軽視すべきではない。

第23回
新しい経済動向として「シェアリングエコノミーの拡大」がある。情報技術の進歩によって、個人が供給者になるという変化が生じているのだ。だが日本では、さまざまな参入規制が新しい技術の利用を阻んでいる。

第22回
新しい情報技術の時代において、われわれの生活と経済活動の安全を確保する必要がある。いまや国の安全保障で最も差し迫っている問題は、サイバー戦争だ。安保関連法案をめぐる議論には、この視点がまったくない。
