
野口悠紀雄
第8回
利ザヤ縮小による金融機関の利益減少に対処する根本的な対策は、新しい技術を導入することだ。これまで金融機関は技術にあまり関係がなかったが、いま新しい技術が登場し、事態が急速に変化しつつある。

第7回
銀行はいま大きな構造問題に直面している。貸付金利がゼロ%に収斂し、銀行にとっての主要な収益である資金運用収益が、ゼロになる可能性があるのだ。そうなれば、銀行のビジネスモデルの基幹が崩壊する。
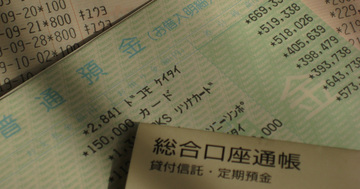
第6回
企業動向の観点から見ると、ユニコーン企業が情報分野で技術開発を進めるだろう。アメリカの学生の就職希望先も、ここだ。なお、DAOという新しい企業群が地平線上に姿を現している。

第5回
企業のスタートアップ資金は、これまでは株式市場のIPOで行なわれてきた。しかし、今後は分散市場のICOでなされるだろう。仮想通貨はすでに独自の経済圏を形成し、日本円は蚊帳の外に置かれている。

第4回
最近、自律的組織がクラウドセールによって資金調達を行なう方式(IOC)が登場し広がっている。この方式が広がれば、従来の金融のシステムを根底から覆すことになるかもしれない。

第3回
日銀は、金融緩和の枠組みを改めた。量的政策から金利政策への転換というが、量的政策の側面が「オーバーシュートコミットメント」として残っており、矛盾を含むものとなっている。長期金利のコントロールも難しい。

第2回
日本の情報関連などの新しい技術の対応が遅れるのはなぜか?GAFA企業に代表される企業活動の新しい動向を受け入れられないこと、企業が閉鎖的でオープンイノベーションに対応できないこと、などが挙げられる。

第1回
実体経済を改善する上で最も重要な課題は、技術革新を進め、その成果を現実の経済活動に取り入れることだ。「技術立国」と言われた日本だが、情報やフィンテックなどの新しいタイプの技術では、著しい遅れが目立つ。

第76回
日銀は9月に総括的検証を行なう。日銀は輸入物価の下落に対応して国内物価が十分に低下していないこと、それが実質賃金を十分に引き上げておらず、実質消費を抑えていう状況を認めるべきだ。

第75回
日本銀行は、9月の金融政策決定会合で、異次元金融緩和の総括的な検証を行なうとしている。その内容は、これまでの金融緩和政策が経済活動に与えた効果の分析が中心となるだろう。

第74回
日本銀行は、9月に金融政策の見直しをするとしている。マイナス金利はどう評価されるのか。見直し表明は、将来金利の予想にいかなる影響を与えたか。これらの問題について検討する。

第73回
住宅建設は増加しており、これはマイナス金利の影響と解釈できなくはない。マイナス金利拡大による住宅建設の促進を図るべきだとの意見もある。そこで、住宅建設増加の要因を検証してみた。

第72回
イギリスの経済構造は、日本のそれとは大きく違う。しかし、そのことが、日本では必ずしもよく知られていない。日本と同じような産業構造の国であると考えると、EU離脱問題を正しく理解することができない。

第71回
この数年間、日本の大企業の利益は、軒並み史上最高益を記録していた。その多くは円安よるものだ。英EU離脱があり、円高が進む中で、企業の期初見通しよりも減益額はさらに大きくなりそうだ。

第70回
円高が進んでいるが、いくつかの指標を見れば、現在の為替レートは決して異常な円高ではないことがわかる。企業は円安に頼らない事業展開が必要である。インフレ目標を基本とする金融政策も見直すべきだ。

第69回
イギリスの株価は、離脱直後の落ち込みから回復し、現在、年初来最高値を記録している。一方、大陸諸国の株価は6月前半より低い水であり、離脱はイギリス経済にとって有利であることを示している。

第68回
「イギリスのEU離脱は経済的に不合理な決定であり、世界経済を混乱させる望ましくない決定だ」とされることが多い。しかし、この議論は大いに疑問だ。とくに、金融活動について、イギリスの離脱には十分な理由がある。

第67回
参議院選挙における大きな争点は、アベノミクスの評価だ。さまざまな経済指標について、安倍晋三内閣発足直後と現在とを比較してみよう。

第66回
三菱東京UFJ銀行が国債の入札における「プライマリー・ディーラー」の資格返上を検討中と報じられた。これは日本の金融政策の行き詰まりを象徴するもので、今後の金融情勢に大きな影響を与える可能性がある。

第65回
厚生労働省が先日発表した4月の全国の有効求人倍率は、3月から0.04ポイント上昇して1.34となった。しかし、内容を分析すると、人手不足の深刻化であり、賃金が低い分野での超過労働需要であることが分かる。
