
野口悠紀雄
第24回
イノベーションを生み続けるITビジネスでは、UberやAirbnbのような中央集権的なサービスも遅からず陳腐化し、いずれ不要になると考えられる。規制の議論も、根本から見直す必要がある。

第23回
トランプ大統領の政策は、シリコンバレーを中心とする米国のハイテク産業の発展を阻害する危険がある。これは、米国経済に甚大な悪影響を与える。米国経済をリードしているのは、これらハイテク企業群だからだ。

第22回
2016年7~9月期までは、実質消費が順調に増えていた。消費者物価が低下して実質賃金が上昇したためだ。しかし、10~12月期では、円安で実質消費の伸びが鈍化している。このままでは、実質賃金と実質消費の減少が再現する。
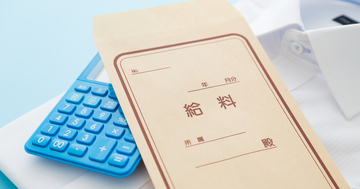
第21回
シリコンバレーには、想像を絶する本社オフィスがある。現在の米国を牽引しているのは、こうした企業だ。トランプ大統領が移民抑制的な政策を取れば、こうした企業の成長は抑えられ、米国経済は打撃を受けることになる。

第20回
米ラストベルト(さびついた工業地帯)の都市デトロイトは、いま荒廃から抜け出そうとしているが、回復は容易でないだろう。しかし、その郊外には、驚くべき「未来都市」が成長している。その違いとは。

第19回
トランプ大統領は、ラストベルトの労働者に支持されたといわれる。「ラストベルト」とは、「さびついた工業地帯」という意味だ。そこは、本当にさびついて、どうしようもない地域なのだろうか?

第18回
高齢者が元気になっているのに、65歳以上の労働力人口比率は低下している。その原因は、制度にある。とくに、社会保障制度が就労のインセンティブを阻害している。

第17回
高齢者の定義を75歳以上とする提言が公表された。高齢者が元気になっていることを踏まえれば、適切な考えだ。必要なのは、高齢者が働く社会を実現することだ。

第16回
ビットコインの時価総額が史上最高値を記録している。2017年には三菱UFJ銀行の仮想通貨が一般の利用に供されることもあり、金融や通貨に関する基本的な状況が大きく変化すると予想される。

第15回
米国大統領選の結果判明後、円安が進んだ。株価も上昇した。2013~14年頃の円安と違い、今回は、ドル高の側面が強い。そのため、アメリカの政策によって大きく影響される。将来どう推移するかには、大きな不確実がある。

第14回
トランプ氏が11月初めに米国次期大統領に決まって以来、米国企業の時価総額ランキングに大きな変動が生じている。金融とエネルギー関係の企業の順位が上昇し、その半面でハイテク企業の順位が低下している。

第13回
ライドシェアが社会的摩擦を伴いつつも、拡大している。その究極的な姿は、ブロックチェーンで運営される自動的なライドシェアサービス。それは、ドライバーがフリーランサーとして独立することを可能とする。

第12回
各国の中央銀行が、仮想通貨の検討に熱心に取り組んでいる。その主要な目的は金融政策の有効性確保だが、他方において、銀行預金の消滅、プライバシー喪失など、大きな問題がある。

第11回
アメリカ大統領選でドナルド・トランプ氏が勝ち、大方の予想に反して円安が進行した。今後さらに円安が進むのだろうか?為替レートにはいくつかの不透明な要素があることを指摘する。

第10回
ITが可能とする柔軟な働きとして、クラウドソーシングやシェアリングエコノミーの発展によって、組織を離れて働くフリーランサーが増加している。

第9回
情報技術の発展に伴って、働き方の改革が可能になっている。柔軟な働き方の導入は、さまざまな利点を持ち、成長戦略の重要な課題と考えられている。だが、日本ではそれほど普及していない。

第8回
利ザヤ縮小による金融機関の利益減少に対処する根本的な対策は、新しい技術を導入することだ。これまで金融機関は技術にあまり関係がなかったが、いま新しい技術が登場し、事態が急速に変化しつつある。

第7回
銀行はいま大きな構造問題に直面している。貸付金利がゼロ%に収斂し、銀行にとっての主要な収益である資金運用収益が、ゼロになる可能性があるのだ。そうなれば、銀行のビジネスモデルの基幹が崩壊する。
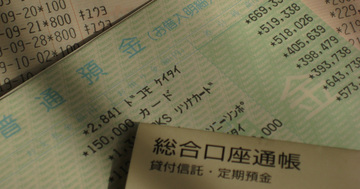
第6回
企業動向の観点から見ると、ユニコーン企業が情報分野で技術開発を進めるだろう。アメリカの学生の就職希望先も、ここだ。なお、DAOという新しい企業群が地平線上に姿を現している。

第5回
企業のスタートアップ資金は、これまでは株式市場のIPOで行なわれてきた。しかし、今後は分散市場のICOでなされるだろう。仮想通貨はすでに独自の経済圏を形成し、日本円は蚊帳の外に置かれている。
