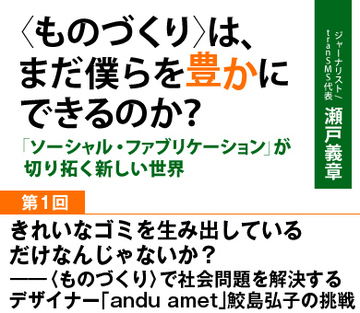瀬戸義章
第10回・最終回
限られた資源や低い技術力でつくられた製品は、本当に「安かろう悪かろう」なのだろうか? 世界のエンジニアがいま注目する「適正技術」を、25年以上もインドネシアの田舎で実践している日本人に学ぶ、「限られているからこそ」生まれるイノベーション、そして新しい「ものづくり」のあり方とは?

第9回
ガラパゴスと言われて久しいが、ハイテク以外で日本のものづくりはもはや役に立たないのだろうか? MIT在学中に「世界を変えるイノベーター」に選ばれた遠藤謙氏がインドで出会った「安物」の義足とそこから得た学びをヒントに、先進国も途上国も関係なく「役に立つ」ものづくりの力の使い方に迫る。

第8回
携帯電話で送金し、送電網なしに送電するという「新しい現実」が生まれているアフリカで、日本のものづくりはどんな役割を果たせるのだろうか? 東大発のテクノロジー「デジタルグリッド」と現地ケニアの携帯送金サービスを組み合わせて人々に電気を届けるという、イノベーティブな取り組みを紹介する。

第7回
〈ものづくり〉に関わるには、企業に属さなければならない時代は終わった。「つくり手」のプラットフォームであるファブラボでは、誰もが互いに学びあい、次なるイノベーションの種が生まれている。今回は8/21~27開催の世界ファブラボ会議をレポート、これからの〈ものづくり〉の可能性を探る。

第6回
今までは公にするものではなかったはずの設計図やアイデアというものづくりにおける「命」を公開し、イノベーションを加速させる動きが次々と生まれている。鎌倉で生まれた鎌倉のためのアイデアが、ケニアの問題を解決し、産業となりつつある事例に見る、オープンソースとものづくりの本当の関係とは?

第5回
「ものづくり」こそが日本産業の要であり、これからも我々の生活を豊かにする――。よく耳にするこの言葉は、果たして本当なのだろうか? MITもインド辺境で出会って衝撃を受けた、「自分の暮らしを変える力」としてのものづくり、そして世界中が注目する「ファブラボ」の可能性に迫る。

第4回
よい素材、高価なテクノロジーを使ったからといって、よい「もの」がつくれるとは限らない――。よく聞く言葉だが、その本質を理解しているだろうか? いま途上国で起こっている「ゴミ」を「資源」にした産業革命とも言える事象を読み解く3つの切り口から、真に必要な素材を見る「目」の養い方に迫る。

第3回
使い手の顔、見えていますか?――「使い手の声=ニーズ」をつかむことは、ものづくりには欠かせない。一方で、日本企業が海外で苦戦していることもまた、この点だという。途上国向けのプロダクトデザイン&ビジネスコンテストで最優秀賞を獲得した著者が語る、「真のニーズ」の聞き取り方とは?

第2回
僕たちは、意味のある〈もの〉をつくれているのだろうか? ――実際にプロダクトデザイン&ビジネスコンテスト「シード・コンテスト」に参加した著者が、課題を抱える現場である東ティモールを訪れることで経験した、〈ものづくり〉が本来持っている「人と人とをつなぐ」という力とその効果とは?
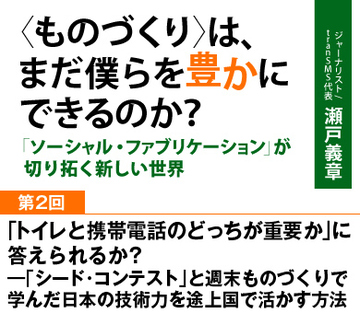
第1回
かつて豊かになることを約束してくれた〈ものづくり〉は、もう僕らを豊かにしてくれないのか?――挫折した一人の起業家が見つけた、ものづくりが本来持つ可能性を通して、大量廃棄が前提の時代で傷ついた使い手=消費者と作り手=生産者をもう一度つなぐ「ソーシャル・ファブリケーション」に迫る。