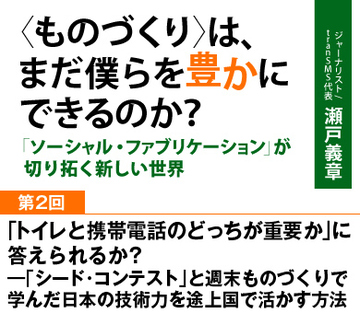ハイテク以外の分野で、日本のものづくりはもはや役に立たないのだろうか?
「ガラパゴス」という言葉が日本の〈ものづくり〉の世界で言われるようになって久しい。一方で、ものづくりに携わる人に話を聞いても、途上国や他の先進国はおろか、日本人相手ですら、役に立っているという実感が薄れているのを感じる。では、エンジニア、もっと言うと「つくり手」が「つかい手」の役に立つということは、いったいどういうことなのか?
今回は、マサチューセッツ工科大学(MIT)の博士課程だった2012年に、科学雑誌「テクノロジーレビュー」にて、35歳以下の「世界を変えるイノベーター35人」に選ばれたこともある〈義足〉研究者・遠藤謙さんが、インドでつかんだ気づきをヒントに、〈ものづくり〉の力の正しい使い方とは何なのか、考えてみたい。
小さなライトで「つかい手」の世界は変わる
――「役に立つ」というものづくりの原点を求めて
2012年9月、僕は、東南アジアの最貧国である東ティモールを訪れた。
発展途上国のためのプロダクトデザイン&ビジネスプランコンテスト「シードコンテスト(See-D Contest)」によるフィールド調査に参加したからだ(シードコンテンストについては、第2回、第3回を参照)。コンテスト参加者の12名とともに、東ティモール東部のピティリティ村に1週間滞在する。現地の課題を肌で感じることが目的だった。
当時のピティリティ村は、3ヵ月前に電気が通ったばかりで、まだ電力供給が不安定。だから滞在4日目、当然のように停電が起きた。まっ暗な中で、村人たちは料理をしたり、水汲みをしたりしている。そんな状況をチャンスと捉えたのは、法政大学デザイン工学部の学生だ。彼は、自分でつくったリストバンド型ライトの試作品を持参しており、暗闇で現地の人に実際に使ってもらう機会を探していた。
 リストバンド型ライトが灯って喜ぶ子どもたち
リストバンド型ライトが灯って喜ぶ子どもたち
夜道を歩いていた子どもたちに、ライトを渡し、事情を説明する。10歳ほどの男の子が手首にライトをはめてスイッチを押すと、まぶしい光があたりを照らした。その途端、子どもたちは満面の笑みを浮かべてはしゃぎ出した。踊るように喜ぶ子どもたちの姿を見て、つくり手の一人であるその学生は、言葉も出ないほど興奮し、感動していた。子どもたちと一緒に、夜道を走りまわっていた。
「自分がつくったものを、使い手が喜んで使ってくれる」ということは、これほど嬉しい体験なのかと、すぐそばにいて感じたものだ。